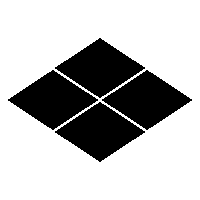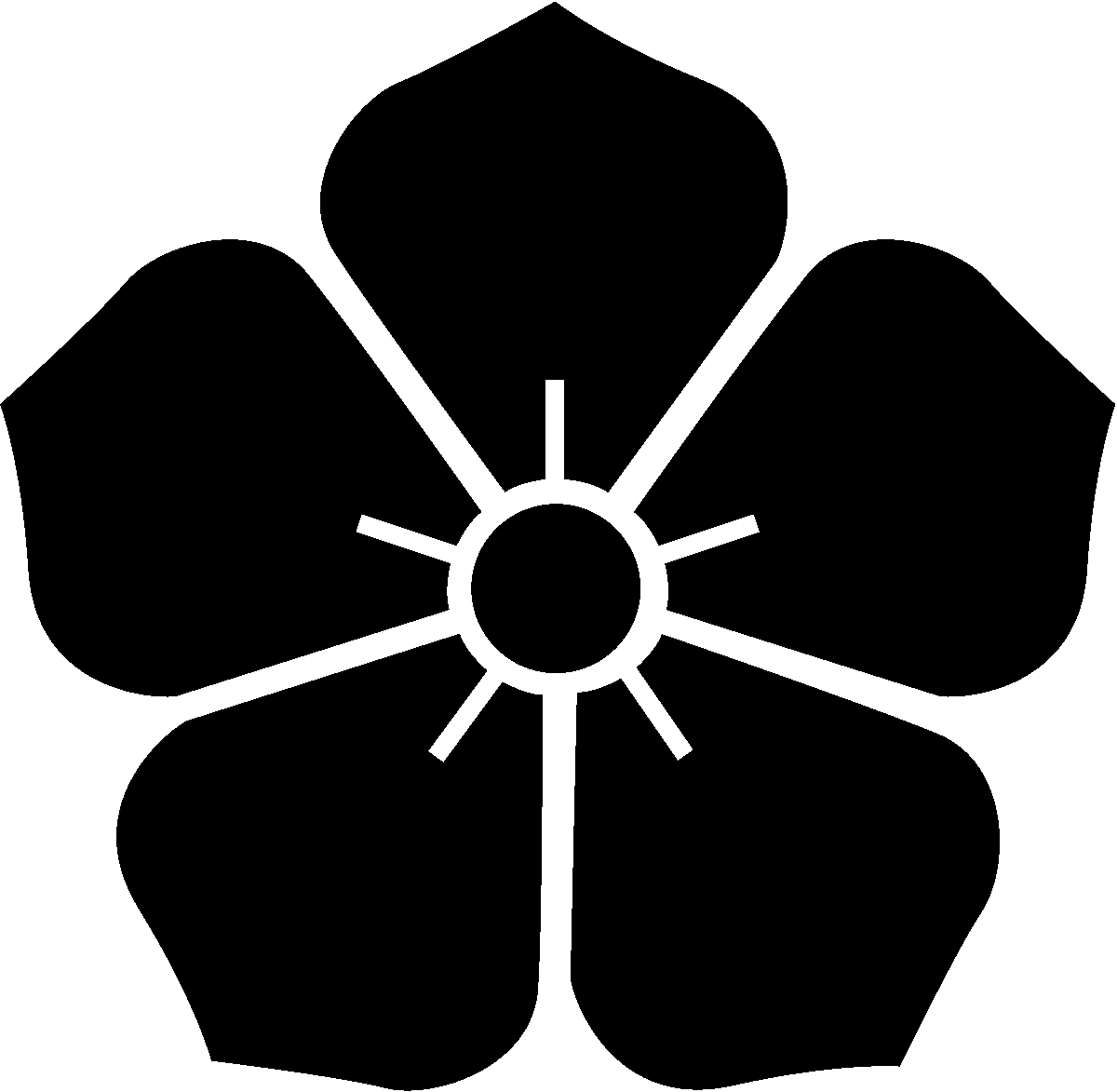惟任退治記現代語訳-戦国時代記編

村井貞勝は本能寺の門外すぐの場所に住んでいた。本能寺での騒ぎを耳にして初めは喧嘩かと思い、それを鎮めようと着の身着の儘外に走り出て様子を見てみたがその騒ぎは喧嘩によるものではなく、本能寺が明智光秀の軍勢二万に取り囲まれている騒ぎの音だった。村井貞勝はどうにか本能寺の中に入ろうと色々試みたが適わず、織田信忠の陣所となっていた妙覚寺まで急いで走り事態を信忠に伝えた。
信忠はすぐにでも本能寺に馳せ参じ父と共に戦い、最後は父と共に腹を切ると家臣たちに話したが、明智軍の包囲が厳重であったため、翼でもなければ本能寺の中に入ることはできそうになかった。まさにこれこそ
※咫尺千里:すぐ近くなのにものすごく遠くに感じること
信忠は妙覚寺は戦をするには不向きであるため、他に近くで戦えて最後は自刃できる場はないかと家臣に尋ねると、村井貞勝は誠仁親王(正親町天皇の息子)がおいでの二条御所が良いと言い、信忠を二条御所まで案内した。すると誠仁親王は輿に乗って内裏にお移りになり、信忠は五百人の兵と共に御所に入った。
明智軍に遮られたことにより、二条御所に馳せ参じることができた信長の馬廻はわずかに一千騎ほどで、信忠のもとにいたのは弟の織田又十郎信次、村井春長父子三人、団平八景春、菅屋九右衛門父子、福富平左衛門、猪子兵助、下石彦右衛門、野々村三十郎幸久、赤沢七郎右衛門、斎藤新五、津田九郎次郎信治、佐々川兵庫、毛利新助、塙伝三郎、桑名吉蔵、水野九蔵、桜木伝七、伊丹新三、小山田弥太郎、小胯与吉、春日源八ら歴々の侍たちであり、彼らは死を覚悟し明智の軍勢が攻め入るのを待ち構えていた。
明智光秀は、主君織田信長が自害し本能寺に火がかけられたのを見ると安心し、織田家の家督を継いでいた信忠の居場所を尋ねた。すると信忠は二条御所に立て篭もっているとのことだった。それを聞いた光秀は兵を休ませることなく二条御所に急行した。しかし二条御所ではすでに死を覚悟した侍たちが大手門を開き、弓・鉄砲隊に前面に構えさせ、他の兵たちも思い思いに武器を手に取り前後を守っていた。
明智軍の先駆けが馬具も整えないまま攻めかかると、矢と鉄砲が次々と放たれてきた。それにたじろぐ明智軍を見ると、信忠の兵は内から一気に攻め出し、押しては退いて、退いては押すの攻防を数時間続けながら戦った。明智軍は武具をしっかりと締め直し、まだ戦える兵に代わるがわる攻めさせた。一方信忠の兵は素肌に帷子だけをまとった軽装で勇ましく善戦を見せたのだが、明智軍は長太刀や長槍を揃えて攻撃してきたため、こちらで五十人、あちらで百人と次々と討ち倒され、遂には御殿のすぐ近くまで攻め入ってきた。
信忠と信次兄弟は腹巻をまとい、百人ばかりの近習は具足をまとい戦った。そして信忠はその中でも一番に打ち出て、十七〜八人の敵兵を討ち取っていった。また、近習たちも果敢に攻め出す信忠に負けじと、刀で火花を散らしながら戦い、敵を方々に蹴散らしていった。
その際明智孫十郎、松生三右衛門、加成清次ら明智軍屈指の侍たち数百人が一気に斬りかかってきた。信忠はそれを見るとその中に飛び込み、これまで稽古してきた兵法、秘伝の術、英傑一太刀の奥義を繰り出し、次々と敵兵を薙ぎ倒していった。すると孫十郎、三右衛門、清次の首は信忠により次々と刎ね落とされていった。そして近習たちも力の限り太刀を振り続け、御所に攻め込んできた明智軍をことごとく討ち果たしていった。
もう何も思い残すことなく最期の戦を戦い切り、父信長と共に逝こうと二条御所の四方に火を放ち、御所の中心まで退くと十文字に腹を掻き切った。他の精鋭たちも熊や鹿の毛皮で作った敷物を並べ、その上で信忠を追うように腹を切り、皆一斉に炎に包まれていった。信長は四十九歳、信忠は二十六歳であり、悼み惜しむべしと民の誰しもが涙を流した。
ところで、明智光秀と同郷で美濃出身の松野平介一忠は、その夜は京の都の外にいた。そして夜襲の報せを耳にし駆けつけたが間に合わず、到着した時に本能寺での戦はすでに終わっており、信長もすでに自害したと聞くと、諦めて妙顕寺まで走り、追腹を切ろうと覚悟を決めた。その時斉藤利三が一忠を明智側に勧誘したが、一忠は信長に恩義があると言いそれを断り自刃した。一忠は元々は医者であり、文武両道の優秀な男だった。普段から歌道もたしなみ、侍になったのちも学問を怠ることをしなかった。そして以下がその一忠の辞世の句である。
そのきはに 消ゑ残る身の 浮雲も 終には同じ 道の山風
手握活人三尺劔、即今截斷尽乾坤
(手に我の命を助けた約90cmの刀を持ち、今まさに天と地を斬り断つ)
このような句を残して腹を切ると臓腑を引き出しながら朽ち果てた。まさにこの時代では他に類を見ない無双の働き振りだった。人々は一忠ん最期を聞くと涙を流し袂を濡らしたものだった。