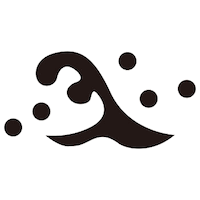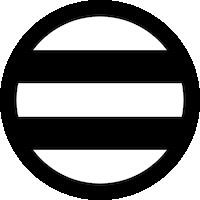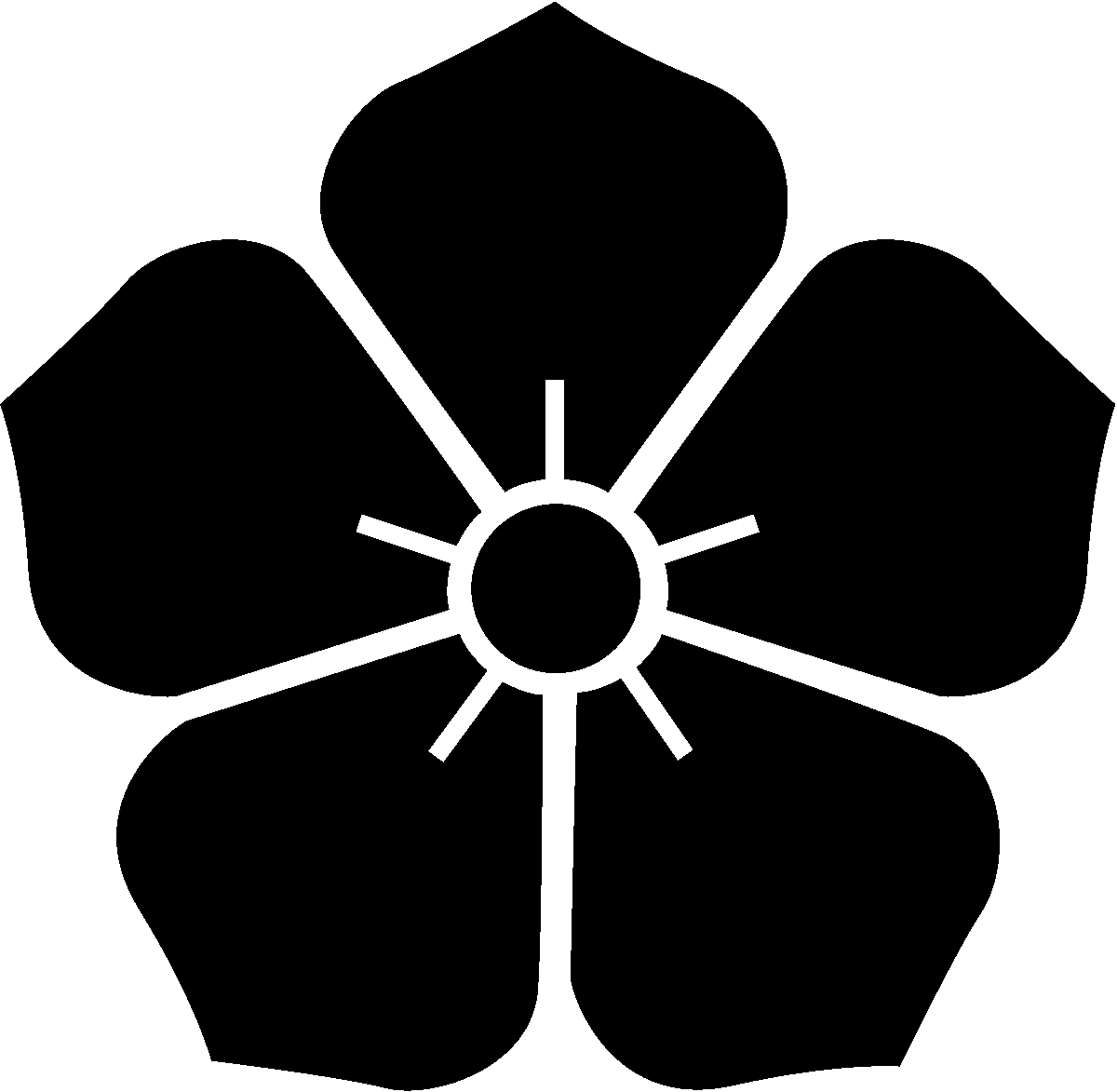
明智光秀はなぜ主君を討たなければならなかったのか?!
明智光秀はあの日なぜ本能寺で謀反を起こしたのだろうか。定説では信長に邪険にされノイローゼ気味だったとか、信長を恨んでいたとか、天下への野望を持っていたとか、様々なことが伝えられている。しかし筆者が支持したいのは明智憲三郎氏の著書『本能寺の変 431年目の真実 』にて証拠をもって結論づけている、土岐氏再興への思いだ。
明智家は元来「土岐明智」とも称する土岐一族で、光秀が家紋として用いた桔梗の紋も、土岐桔梗紋と呼ばれる土岐氏の家紋だ。土岐氏とは室町時代に美濃を中心にし隆盛を誇った名家で、土岐氏最後の守護職となった頼芸(よりのり)は、斎藤道三の下克上によって美濃から追放され、これにより200年続いた土岐氏による美濃守護は終焉を迎えてしまう。そして大名としての土岐氏も事実上滅んだことになり、土岐一族は美濃から散り散り追われる形になってしまった。そのひとりが明智光秀だったというわけだ。
長曾我部元親が突然信長に対し強硬姿勢に出た理由
本能寺の変の直前、長曾我部元親はそれまでは友好的だった織田信長に対し、所領問題で抗戦的な態度を見せ始めていた。しかし両家が戦えば長曾我部の軍勢など、織田の軍勢の前では子ども同然だ。それは元親自身分かっていたはずだ。それでも元親が信長に敵対したのは、光秀の存在があったからこそだった。光秀であれば何とか信長を説得してくれるはずだと踏んでいたのだ。だがその目論見は外れ、信長は遂に長曾我部征伐軍を四国へと送ってしまう。
ではなぜ元親は光秀の存在を当てにしたのか?長曾我部と織田を結んだのは元々光秀の功績だったわけだが、ここにもやはり土岐氏が絡んでくるのだ。元親の正室は石谷光政の娘で、石谷氏(いしがい)もやはり美濃の土岐一族なのだ。そして元親の正室の兄が石谷頼辰という明智光秀の家臣であり、頼辰は斎藤家から石谷家に婿養子となった人物で、斎藤利三は実の弟に当たる。
石谷頼辰=斎藤利賢の実子であり後に石谷光政の養子になる。長曾我部元親の正妻の義理の兄に当たり、明智家の重臣である斎藤利三の実の兄。
つまり光秀は家臣頼辰と元親の関係から長曾我部家と懇意になり、長曾我部と織田のパイプ役となっていたのだ。そして光秀自身も、長曾我部と連携を図ることは明智家にとって大きなメリットがあると考えていたようだ。近畿を治める明智と四国を治める長曾我部が連携すれば、光秀の織田家での立場をより強固なものにできる。外様大名として肩身の狭い思いをしていた光秀にとり、長曾我部家と連携するメリットは非常に大きかった。
このような関係があったからこそ、元親は光秀の後ろ盾を当てにし、信長に対し強硬姿勢を取ってしまったのだった。だが光秀の懸命な説得も虚しく、信長は長曾我部征伐軍を四国に送り込んでしまった。これに慌てたのは光秀と元親だった。ふたりとも、まさか信長が本気で長曾我部を攻めるとは考えていなかったのだ。
土岐家縁戚の長曾我部滅亡を黙ってみてはいられなかった明智光秀
明智光秀の夢は土岐家の再興だ。そのためには長曾我部家の協力が不可欠となる。元親の正室が土岐氏の娘である以上、元親自身も土岐家の縁戚ということになる。いずれは両家が協力し、土岐家を再興させるつもりだったのだ。だが信長はその長曾我部を滅ぼすつもりで征伐軍を四国に送ってしまった。
もしここで長曾我部が滅亡してしまっては、光秀の土岐家再興の夢も潰えてしまう。そもそも土岐家の縁戚である長曾我部が攻められ、土岐明智である光秀が黙って見ていることなどできようはずもない。光秀は何とかしようと信長に取り入るわけだが、しかし信長はそんな光秀を相手にしようとさえしなかった。
さて、信長が徳川家康の接待役である光秀のやり方が気に入らず、役を解任し足蹴にしたという話はあまりにも有名だ。だがこのエピソードも明智憲三郎氏の歴史捜査によれば実際はそうではなく、光秀がしつこく長曾我部への恩赦を求めたため、信長が激昂し足蹴にしたらしいのだ。つまり光秀はそれほどまでに土岐家再興のためにも長曾我部を守りたかったのだ。
だが何をどうしても信長の長曾我部征伐軍を止めることはできなかった。あとはもう信長を討ってでも止めるしか術はない。光秀がそんな思いに駆られていたタイミングで、信長は本能寺にて家康を持て成すことになった。家康を待つ間、信長は僅かな護衛のみで本能寺で過ごしていた。この一瞬とも言える信長の隙を狙い、光秀は信長を討ったのだった。すべては長曾我部を守り、土岐家を再興させるために。
敵は本能寺にあり!
「敵は本能寺にあり!」、この言葉は光秀が突発的に口にしたものではない。幾重もの手回しをし、状況をしっかり整えた上で言い放った言葉だった。光秀はノイローゼでもうつ病でもなかった。夢実現のため、周到な準備をした上で謀反を企てたのだ。だが残念ながらその準備のいくつかが信長を討った後に上手く機能せず、謀反そのものは成功するも、信長を討った僅か11日後に光秀も山崎の戦いで討たれてしまった。
光秀は決して信長への恨みを晴らすために謀反を起こしたわけでも、ノイローゼで錯乱した状態で本能寺に攻め込んだわけでも、天下を横取りするためにクーデターを起こしたわけでもなかった。純粋に土岐家の再興と盟友である長曾我部元親を守るそのため、泣く泣く主信長を討ったのだった。
もしこの時光秀が信長を討たなければ、光秀は土岐縁戚である長曾我部を見捨てることになっていた。つまり信長を討とうと討つまいと、光秀はどちらにせよ自らの裏切りに苛まれたことになる。土岐縁戚である長曾我部を守るならば信長を討つしかなく、主に従うならば土岐家縁戚である長曾我部の滅亡を黙って見ているしかない。果たして誰がこの光秀の苦しい立場を責めることができよう。
明智光秀という人物は、決して主を討った極悪人ではないのだ。そして自らの野望のために主を討った謀反人でもない。確かに謀反を起こしはしたが、それは決して利己的な目的によるものではなかった。
明智光秀という人物の真実を知るためにも、ぜひ『本能寺の変 431年目の真実 』をお手に取ってもらいたい。一般的な歴史書のような堅苦しく読みにくい文章ではなく、まるで推理小説を読むような面白さとスピード感がある一冊となっている。筆者もこの本との出会いがなければ、この先もずっと織田信長や明智光秀を勘違いし続けていたかもしれない。たくさんの証拠を示しながら本能寺の変を紐解いている良書です。