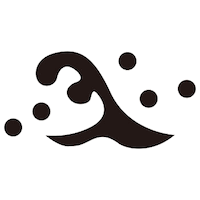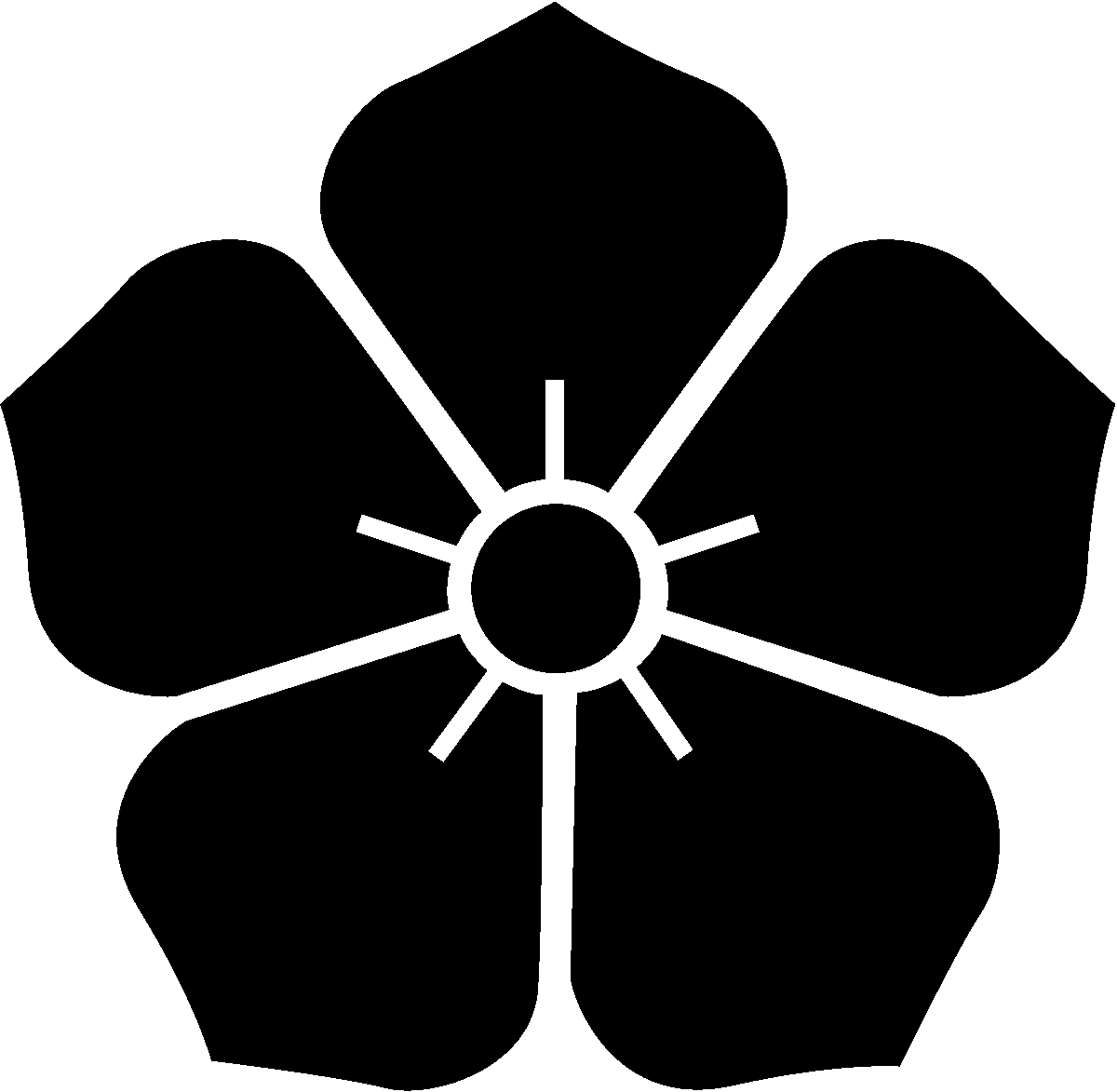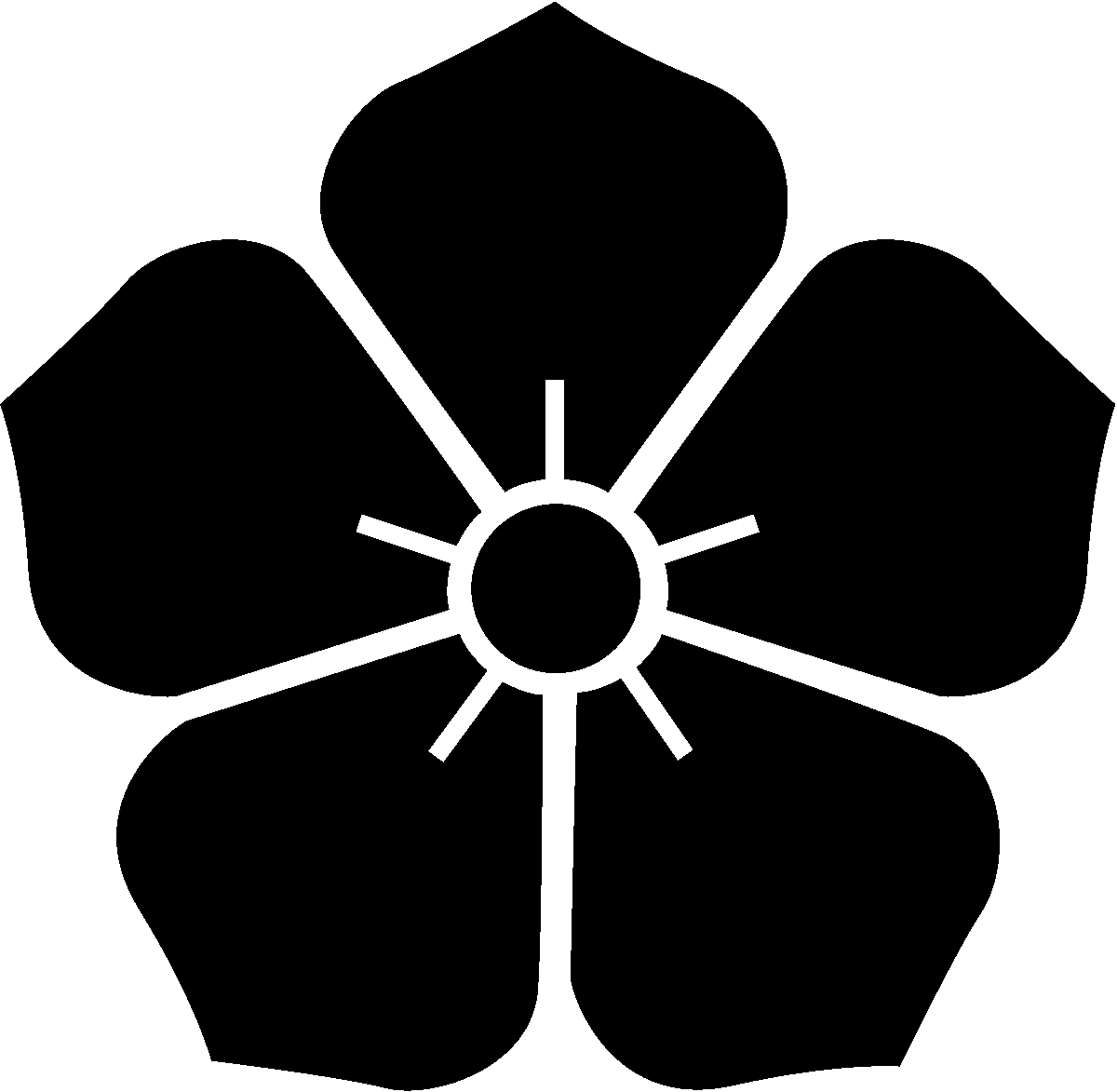
斎藤利三(としみつ)と言えば、明智家に於いては重臣中の重臣とも呼べる臣下だった。春日局の父親としても知られる利三だが、同じ美濃国の斎藤姓でも斎藤道三とは血縁関係にはない。元々の美濃守護代であった斎藤家の血筋で、父親は斎藤利賢(としかた)、母親は蜷川氏の娘、光秀の叔母、光秀の妹もしくは姉と諸説ある。今回はこの斎藤利三という人物の人柄に迫っていきたい。
頑固者の稲葉一鉄と何らかの衝突があった斎藤利三
斎藤利三という人物は、少々問題児だったようだ。元々は稲葉一鉄の与力だったようだが、その一鉄とは何らかの理由で衝突があったようだ。そして『当代記』という『信長公記』を元に編纂された資料には、信長から勘当されているとも記されている。それぞれどのような問題があったのかは詳しく記されてはいないが、しかし何らかのいざこざがあったことは確かなようだ。
ちなみに稲葉一鉄という人物は美濃三人衆(安藤守就、氏家卜全)の一人で、美濃国内では非常に有力な人物だった。そして「頑固一徹」という言葉はこの稲葉一鉄が由来となっている。恐らくは利三は、その頑固者の一鉄の考え方に同調できなかったのだろう。だが問題はこれだけでは済まなかった。
斎藤利三が原因で何度も信長に殴られた光秀
稲葉一鉄の元を去り、明智光秀に与した斎藤利三だったが、この状況を一鉄は気に入らなかった。確かに利三は一鉄の娘を娶っていたのだから、一鉄が怒りを感じたことも理解はできる。『明智軍記』や『稲葉家譜』の記述からは、光秀に有能な家臣を奪われたと一鉄は感じていたようだと読み取ることができる。そしてさらに、那波直治が利三を追うように光秀の傘下に加わろうとした。再び光秀に家臣を奪われたと感じた一鉄は信長にこれを報告し、信長は光秀を呼びつけ、直治だけは一鉄の元に返すように命じたようだ。
この時に信長が人前で光秀を叱り飛ばし、さらには2〜3回殴ったことで辱めを受け、それを逆恨みして光秀が本能寺の変を起こしたと主張する歴史学者もいるが、筆者はそうは思わない。本能寺の変当時、天下統一を目前にした信長と光秀は現代で言えば総理大臣と副総理のような立場にあった。それだけの立場にあった光秀が、果たしてそんなことを理由に主君を討つだろうか。そもそも信長が光秀を何度も殴ったという話は、どうやら後世の創作である可能性も高い。
本能寺の変は斎藤利三がけしかけた事件だった?!
さて、斎藤利三には頼辰(よりとき)という兄がいた。しかしこの兄は石谷家の養子となり、石谷頼辰と名を改めている。この頼辰の妻の妹が長曾我部元親の正室となっており、その繋がりがあったために明智光秀は、織田家と長曾我部家の取次として交渉役を任されていた。しかし実際に交渉に当たっていたのは光秀ではなく、斎藤利三だったようだ。
そしてこの繋がりがあったために、縁戚となっていた長曾我部家を滅ぼそうとしていた信長を止めるため、斎藤利三が光秀に対して本能寺の変を嗾けたという説もまことしやかに語られている。だがこの説も説得力には乏しいように感じられる。織田家と長曾我部家の問題は、信長の家臣の家臣が物を言っていいような次元の話題ではない。もちろん交渉役を務めていたのは利三であったわけだが、しかし交渉役と言っても実際には信長の意思を元親に伝え、元親の意思を信長に伝えるというのが主な役目であり、利三が個人的に意見を言えるような状況ではなかったはずだ。
確かに利三の感情論としては、利三と元親は義理の兄弟であったため、信長の長曾我部討伐を聞いた際は利三も心苦しかったはずだ。だが元々の元凶は元親にもあった。本能寺の変が起こる前年、長宗我部元親は織田家と交渉をしながらも、織田家の宿敵である毛利と同盟を結んでいたのだ。これはつまり元親の織田家に対する裏切り行為であり、これが元凶となって信長が長曾我部討伐を企てたとしても、利三には納得できたことのはずだった。このような理由から、筆者は利三が本能寺の変を嗾けたという説には信憑性がないと感じている。
光秀はまず、利三ら5人だけに本能寺への討ち入りを打ち明けた
斎藤利三は、明智光秀にとってはまさに忠臣だ。明智秀満と共に、光秀が最も信頼を寄せたのが斎藤利三だった。であれば、当然光秀の明智家を守りたいという強い意思や、土岐家再興に対する情熱も知っていたはずだ。それを知った上でもし利三が本当に本能寺の変を嗾けていたのだとすれば、利三を忠臣と呼ぶことなどできなくなる。なぜなら本能寺の変を起こせば土岐家再興どころか、明智家がそのまま滅ぶ恐れもあったからだ。そして実際に明智家は滅んでしまった。忠臣であれば、そのような進言は絶対にしなかったはずだ。
さて、本能寺の変の直前、光秀は5人の信頼できる家臣だけを集めて本能寺への討ち入り計画を最初に打ち明けたようだ。その5人とは斎藤利三、明智秀満、溝尾庄兵衛尉、藤田伝五、明智光忠のようだ。しかしここで疑問が浮かんでくる。光秀も含めこの5人はすべて本能寺の変で戦死、もしくは処刑されている。なのに何故後世に書かれた軍記物などで、光秀がこの5人だけに打ち明けたということがハッキリと書かれているのだろうか。とてもこの5人が死ぬ間際にそれを誰かに打ち明けたとも思えない。
本能寺の変は利三が嗾けたという説を上述したが、しかし『備前老人物語』は、それが真実であるのかはわからないが、利三と秀満は最後まで討ち入りには反対していたと伝えている。これらのことを色々と考えると、結局は真実を伝えているものはほとんど皆無に等しく、書かれている多くのことは後世の創作であったり、噂話をそのまま真実として記しただけであることがよくわかる。特に軍記物は今でいう歴史小説と同じ類もので、ベストセラーを狙って面白おかしく書かれている物であり、その記述を資料として信頼することはできない。
利三処刑後も途絶えなかった斎藤利三の血脈
さて、本能寺の変で信長を討った後、斎藤利三は山崎の戦いで先鋒として羽柴軍と戦った。しかし傷を負い、その傷が原因で病にも侵されかけ力を失った利三は、ついには堅田で捕縛されてしまう。ちなみにこの時利三を捕縛し秀吉に差し出したのは明智半左衛門という味方のはずだった人物だった。明智半左衛門は光秀を裏切ったが、しかし半左衛門の父親である猪飼昇貞(いかいのぶさだ)は最後まで光秀に忠義を尽くし、本能寺の変で戦死している。
半左衛門によって捕縛された利三は六条河原で打ち首にされた。『言経卿記』によれば、斎藤利三は当初から本能寺の変を起こした主要人物として見られていたようだ。さて、このようにして斎藤利三はその生涯を閉じたわけだが、しかし利三の血脈はここで途切れることはなかった。結果的には斎藤利三と稲葉一鉄は喧嘩別れのような形になっていたが、しかしその後利三の娘福が稲葉一鉄の孫(養子)に当たる稲葉正成の後妻となり、その後は江戸幕府第三代将軍家光の乳母となり、さらには江姫(浅井長政と市姫の三女)のもとで大奥を取り仕切るようになっていく。もちろん彼女こそがかの春日局だ。同じ本能寺の変の当事者の子孫であったにも関わらず、明智光秀の子孫に対する扱いとは雲泥の差があったようだ。