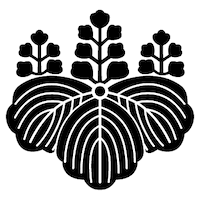真田家に積年の恨みを持ち続けた徳川家康
関ヶ原の戦いで徳川率いる東軍を相手に戦った真田昌幸と真田信繁(真田幸村)は、西軍敗戦後、九度山(高野山)に蟄居させられた。だが昌幸・信繁父子としては、いつかは必ず赦免されると考えていたようだ。そもそも真田父子は、実のところ関ヶ原の戦いそのものには参加していなかった。あくまでも上田城を攻めて来た徳川秀忠軍を撃退しただけ、なのである。
関ヶ原の戦いの直前に行われた上田城攻防戦を第二次上田合戦と呼ぶわけだが、徳川と真田の因縁は天文13年(1585年)の第一次上田合戦まで遡る。徳川家は幾度となく真田家に苦しめられ、家康自身は昔年の恨みから真田家のことは目の上のたんこぶのように思っていた。だが徳川家の家臣たちの多くは関ヶ原の戦い後、真田を赦免すべきだと家康に進言していた。
だが幾度となく真田家に苦しめられたことから家康はなかなか首を縦に振ることはなく、第二次上田合戦で足止めをされ、関ヶ原に遅参する羽目になった徳川秀忠も真田家への怒りを抑えることができなかった。家臣たちの説得により、家康は少し態度を軟化させたようだが、しかし実際には秀忠の頑なな反対により赦免されることはなかった。
父弟は救えなかったが13万石の藩主となった真田信之
父と弟が九度山に蟄居させられて以来、真田信之は赦免してもらえるようあちこちに根回しをした。家康の軍師とも言える本多正信、徳川四天王である本多忠勝(信之の舅)・榊原康政・井伊直政の3人に頭を下げ、家康に赦免してもらえるように頼んで回っていた。
『常山紀談』によれば家康は最終的には赦免を与えようとしたらしい。だが秀忠が真田への怒りを抑えることができず、赦免は実現しなかった。秀忠は「昌幸を誅す(ちゅうす=殺す)」とまで口にしており、関ヶ原遅参に対する相当の恨みを真田昌幸に対し持っていた。
信之の依頼を榊原康政は快諾し、当時リンパ系の病気に苦しんでいた井伊直政も家康を説得すると約束してくれている。そして本多正信は初めから真田を擁護するような姿勢を取っており、本多忠勝は信之の舅であることから、真田の赦免を家康に強く進言してくれていた。だが繰り返すが秀忠の怒りが収まらなかったことにより、昌幸・信繁父子の赦免が実現することはなかった。
ちなみに「昌幸を誅す」という秀忠の言葉を伝え聞いた信之は、「父を誅す前にまず自分に切腹を命じて欲しい」と言ったと伝えられている。敵の子は敵、それならば昌幸の子である自分も徳川家家臣とは言え切腹するのが筋、というのが信之の信念だった。
結局昌幸の赦免は実現することなく、慶長16年(1611年)6月4日、昌幸は65歳で九度山にて病没してしまう。しかも赦免が実現しなかったことから、正式な葬儀を執り行うことは認められなかった。昌幸の亡骸は家臣によって九度山で火葬されたようだが、どのような葬いがされたのかは今となっては知る由もない。
徳川の監視(監視役は浅野幸長:よしなが)もあったことから、きっと本格的な葬儀を行うことはできなかったのではないだろうか。もし葬儀が許されない中で立派な葬儀をし、それが秀忠の耳に入れば真田家をひとり守る信之に火の粉が降りかかってしまう。それを避けるためにも信繁や家臣は、本当に細やかな最低限の葬いしかしてあげられなかったのではないだろうか。
真田昌幸という戦国時代きっての謀将の最期としては、あまりにも寂しいものとなってしまったわけだが、しかし真田信之の奔走もあり、真田の家が取り潰される事態だけは避けることができた。そして真田信之はその後9万5000石の上田藩の祖となった。さらにはその後松代藩に転封し、13万石を得ることになった。