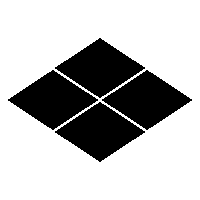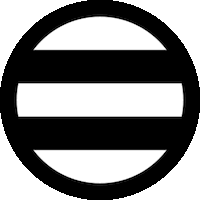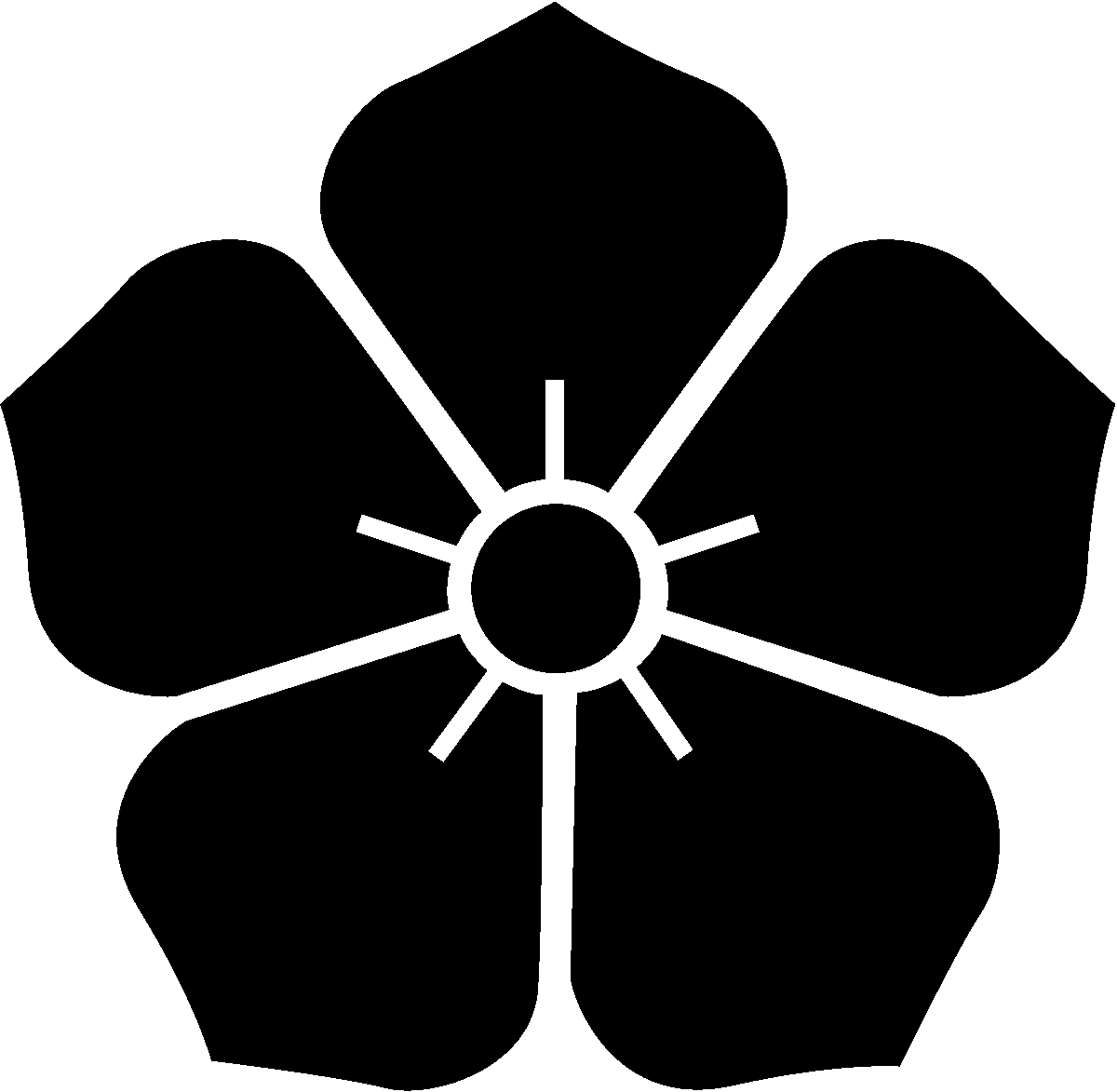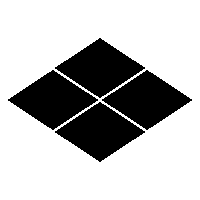
織田信長や上杉謙信が恐れた武田勝頼
武田勝頼の最期は実に呆気ないものだった。父信玄の従甥であった小山田信茂の裏切りに遭い、最期は一説によれば100人にも満たない僅かな共の者と逃げ場を失い、天目山で自害したと伝えられている。勝頼のこの自害により、450年続いた甲斐武田氏は信玄亡き後あっという間に滅亡してしまった。だからと言って、武田勝頼は決して愚直な武将だったわけではない。
事実信玄の死後は強過ぎる大将と謳われるほどの戦いを見せていた。だが負け知らずであったがために勝頼のプライドはどんどん高くなってしまったようだ。本来は退くべき戦を退かずに挑んでしまった。勝者の奢りとも言うべきだろうか。重臣たちはしきりに退くことを提言したが、しかしここで退いてはは武田の名が廃るとばかりに、勝頼は無謀な戦いに挑んでしまう。それが長篠の戦いだった。
織田信長は上杉謙信に対し「勝頼は恐るべし武将」と書状を書き、謙信もそれに異論はなかったようだ。長篠の戦いは1万5000の武田勢に対し、織田徳川連合軍は3万8000だった。数の上では織田徳川連合軍が圧倒的に上回っている。しかし信長はそれでも勝利を確信することができなかった。
そのため佐久間信盛に武田に寝返った振りをするように命じた。勝頼はあろうことかこれを信じてしまい、戦いが始まれば織田方の重臣である佐久間信盛が内応することを前提に戦いに挑んでしまった。つまり武田勝頼は長篠では織田方に騙され、天目山では血族である小山田信茂に裏切られたことになる。武田勝頼は織田信長や上杉謙信が恐れる名将ではあったが、生きるか死ぬかの戦国時代に於いては人を信じ過ぎたことが仇となってしまった。
武田信玄は『孫子』を熟知する軍略家だった。しかし勝頼はこの時『孫子』を無視した状態で戦に挑んでしまう。もし勝頼がもっと織田方が整えていた準備を把握できていれば、武田軍に勝ち目がないことは火を見るよりも明らかだった。だが勝頼は最強の武田騎馬軍団を過信してしまい、信長の誘いに乗り沼地の多い設楽原(したらがはら)に陣を敷いてしまった。沼地ではいくら最強と言えど、騎馬軍団の威力半減してしまう。
一方の織田徳川連合軍が沼地の先に用意していたのは馬防柵だった。騎馬隊が侵攻できないように木でフェンスを作り、その隙間から鉄砲を撃てるようにしていた。この戦略により武田騎馬軍団は一網打尽にされてしまう。
天正3年(1575年)5月21日、早朝に始まった死闘は8時間にも及んだという。だが武田軍に勝機はなく、この戦いで土屋昌次、山縣昌景、内藤昌豊、原昌胤、真田信綱・信輝兄弟(ふたりとも真田昌幸の兄)が討ち死にし、撤退時に殿(しんがり)を務めた馬場信春も、勝頼が無事に撤退したことを知ると討ち死にしてしまった。たった一度の戦でこれだけ名のある武将たちが次々命を失った戦も珍しい。
この敗戦により武田家は一気に衰退していき、天正10年(1582年)3月11日、天目山の戦いで勝頼が自害したことにより、名家武田氏は歴史からその名を葬られてしまった。

織田信長という人物は冷酷で、男色でもあったという定説が現在では当たり前のように知られている。だが明智憲三郎氏が書いた『本能寺の変 431年目の真実 』という本を読むと、それは羽柴秀吉が本能寺の変後に作ったイメージに過ぎないことがよくわかる。
』という本を読むと、それは羽柴秀吉が本能寺の変後に作ったイメージに過ぎないことがよくわかる。
明智憲三郎氏は本能寺の変を起こした明智光秀の子孫であると言う。だがこの本は決して先祖を擁護するような感情論的な本ではない。本能寺の変を徹底的に歴史捜査し、推測ではなく、戦国時代に書かれた書状や日記などで証拠を固めながら書かれた良書だ。
当サイト戦国時代記では、本能寺の変にまつわることは主にこの本の情報を基にし、今までの定説に縛られることなく事実のみを発信していきたい。
信長の時代に生きた人々の日記などからは、信長は決して冷酷な人間ではなかったことがよくわかる。例えば本能寺の変であるが、明智光秀の謀反を知り、信長が真っ先に取った行動は女子供など弱者を逃すことだった。
そして信長に男色のイメージがつけられたのは羽柴秀吉が書かせた『惟任退治記』によってだった。惟任日向守とは明智光秀のことで、秀吉自らが逆臣光秀を討ったことを宣伝するために書かせたいわゆるプロパガンダ本だ。森蘭丸は歴史好きであれば誰もが知る名だと思う。だが蘭丸と書かれたのは『惟任退治記』によってで、秀吉は蘭という字には男色のイメージがあるため、森乱丸を森蘭丸とわざと変えて書かせたようだ。
さらには女遊びが好きだったという信長のイメージも、やはり本能寺の変後に秀吉が書かせたことだった。明智憲三郎氏の著書によれば、秀吉が織田政権を奪取しやすくなるよう、信長を負のイメージで固めたのだという。その証拠に関しては上述した本を読んでいただきたいところだが、読めばなるほど納得できる。
信長という人物は確かに激情家ではあったようだ。だが決して冷酷な人間でも男色でもなく、女にだらしのない人物でもなかったのだ。今日までに作られた信長の負のイメージは、すべて秀吉が信長の死後に作り上げたものだったのだ。
織田信長は天下統一を直前にし、最も信頼を寄せていた家臣に裏切られ49歳でこの世を去った。もし本能寺の変が起こっていなければ徳川幕府が開かれることはなく、きっと織田幕府が開かれていたのだろう。だが織田幕府が徳川幕府ほど長くは続かなかったであろうことは、当時信長が考えていたことを思えばよくわかる。それについてはまた別の巻にて書いていきたいと思う。
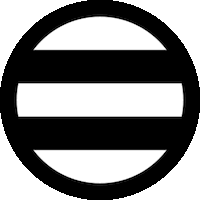
麒麟がくる第6回「三好長慶襲撃計画」は、ほぼ全編フィクションで話が進められたのではないだろうか。劇中の出来事を追っていくと時系列が明確になっていなかったり、年齢設定が正確ではないように感じることが多くなってきた。例えば劇中は天文十六~十七年(1547~1548年)あたりを描いていると思われるが、この頃の第十三代将軍足利義輝はまだ13~14歳程度でしかない。劇中の将軍はさすがに14歳には見えなかったのではないだろうか。
三好長慶の暗殺が企てられた連歌会
さて、今回は細川晴元が画策した連歌会に三好長慶が招待され、そこで長慶が暗殺されそうになるという場面が描かれていたが、この出来事もフィクションではないだろうか。確かに細川晴元と三好長慶という主従の間にはいざこざが生じていた。だがこのような連歌会で暗殺が企てられたという事実は筆者はまだ読んだことがない。確かに戦国時代にはよくある話のようにも見えるため、「絶対にそんな事実なかった」とは言い切れないが、しかしあくまでもこれはフィクションの枠の中に納まっていくは思う。
足利義輝は天文十六年(1548年)7月19日に細川晴元によって京を追われ近江国坂本に父義晴と共に落ちている。その10日後両者は和睦し、義輝も京に戻ってはいるのだが、劇中に描かれたのはこの直後の出来事ということになるのだろう。この時の義輝は確かに細川晴元に対し良い心象は持っていなかったはずだ。そのため三好長慶・松永久秀という細川晴元にとっての天敵(実際には晴元の家臣)に手を差し伸べたことにも理解は示せる。だが義輝の立場は常に不安定だったと言える。
劇中この時代の足利義輝はまだ子供だった
細川晴元は細川家嫡流の名門中の名門だった。同じ苗字の細川藤孝(細川護熙元総理はこちらの血筋)とは異なる細川家であり、細川晴元の細川家は、まさに将軍直属の重臣(室町幕府の官領職)だった。立場的には足利義輝の下に細川晴元、その下に三好長慶(晴元の家臣)、三淵藤英(幕府奉公衆)、細川藤孝(幕府警護役)という形になる。だがこの頃の力関係は細川晴元の臣下である三好長慶が勢力を増してきており、細川晴元にとっては頭痛の種になっていた。それ故の暗殺未遂という描かれ方だったのだろう。
この頃の足利義輝はまだ若年だったこともあり、書状にされそれほどの効力はなかった。そのため大御所として義輝を支えようとした父第十二代将軍義晴や、母慶寿院の署名で書かれることも多かったという。つまりこの頃の義輝はまだそれほど幼かったはずであり、明智光秀が三淵藤英を説得しようとする熱弁を耳にし、それに心を打たれ威風堂々「あの者(光秀)の後を追え」と即興の判断などできる年齢には至ってはいなかった。しかし劇中では能をも楽しむ姿が描かれていた。ちなみに足利義輝となるのは天文二十三年(1554年)であり、それまでは足利義藤という名前だった。
筆者が今一番気になるのは遊女タケの存在
この暗殺を止めようとする光秀だが、もちろん明智光秀が三好長慶と松永久秀を救ったという史実は存在しない。いや、もしかしたらあったかもしれないが、少なくともそれを示す資料は残されてはいない。また、実際には明智光秀と細川藤孝が出会うのは、光秀が美濃を追われ越前に逃れたあとだと思われる。
さて、筆者はタケという人物が今非常に気になっている。劇中のタケは恐らくは伊平次と一緒にいる遊女だと思われるが、実は史実の光秀は越前の竹という人物に世話になったとされている(光秀は竹を助けた服部七兵衛尉に感謝の書状を認めている)。このタケがその竹なのかはわからないが、しかし史実と名前が被っているだけに筆者は個人的には非常に気になっている。もしかしたらこの遊女は越前の人間であり、光秀が越前に逃れた後、もしかしたら劇中で重要な役どころになってくるのかもしれない。いやしかし、ただ偶然名前が被っただけかもしれない。これもまたドラマを見続ければ見えてくるのだろう。


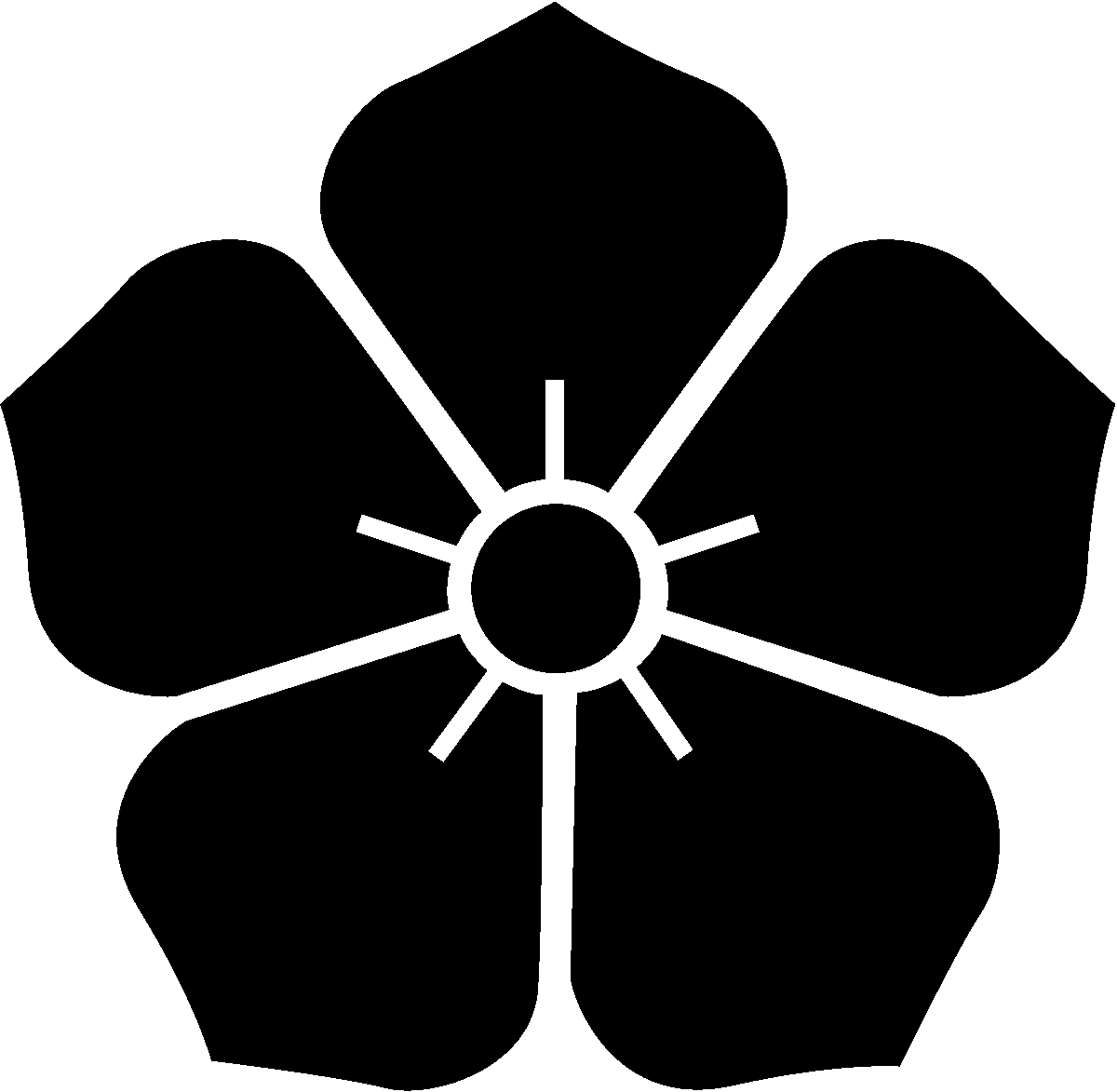
斎藤道三と斎藤義龍父子の仲は、最終的には長良川で戦火を交えるほど険悪なものへとなっていく。この長良川での戦い以降、明智家は斎藤道三に味方していたものと思われている。だが反対に、明智家が土岐家を追放に追いやった道三に味方するはずはない、という見方をしている史家もいる。だが正確な資料が残されていない上では、明智家が実際にはどちらの味方をしたのかを断言することはできない。
明智家は本当は道三と義龍のどちらに味方したのか?!
『明智軍記』を参考にするならば、どうやら明智光安(光秀の叔父)が城主を務める明智城は道三側に付いていたようだ。ただし『明智軍記』は本能寺の変から100年以上経ったのちに書かれたものであるため、情報が正確ではない記述も多々ある。そのためこれを信頼し得る情報だとは言い切れないわけだが、しかし今回は『明智軍記』の記述も参考にしていきたい。
ここで明智家が斎藤道三に味方するはずがないという論理も合わせて見ておくと、斎藤道三は光秀が再興を夢見た土岐家を美濃から追いやった人物だった。その人物に味方するなど考えられない、という論理であるわけだが、筆者は個人的にはそうは思わない。戦国時代は力を持つ者こそが正義だった。つまり力がなければ、力を持つものに従うしかない。
さらに言えば斎藤道三の正室である小見の方は、光秀の叔母だったとされている。となれば、血縁者の側に味方するのは自然であったとも言える。光秀は家を何よりも大切に考えていた人物だ。それならば明智家の血縁者である小見の方を正室に迎えている道三に味方する方が自然に見え、『明智軍記』に書かれていることにも違和感を覚えることはない。
幼少期から光秀に一目置いていた斎藤道三
長良川の戦いが起こったこの頃、明智光秀はまだまだ土岐家の再興を現実的に考えられるような状況ではなかった。明智家は武家とは言え最下層とも言える家柄で、武家というよりは土豪に近い水準にまで成り下がっていた。このような状況では土岐家のことまで心配することなどとてもできなかったはずだ。
そもそも斎藤道三は明智光秀には幼少の頃から一目置いており、彦太郎(光秀の幼名)に対し「万人の将となる人相がある」と言ったとも記録されている。このような関係性があったことからも、道三と義龍が戦った際、明智家が道三に味方したと考えることに不自然さはないようにも思える。
斎藤義龍の父親は斎藤道三と土岐頼芸のどっちだったのか?!
斎藤義龍は長良川で父道三を討った後に明智城を攻め落とした。この戦いで明智光安が討ち死にし、光秀ら明智一族は越前へと亡命するしかなくなってしまった。ではなぜその亡命先が越前だったのか?明智光秀の父明智玄播頭(げんばのかみ)こと明智光隆の妻は、若狭の武田義統の妹だった。そしてこの武田家は越前朝倉家に従属していた。恐らくはこの武田家を通じ、当時は非常に裕福だった越前に仕官を求めたのではないだろうか。
ちなみに斎藤義龍には土岐頼芸の子であったという説もあるが、斎藤道三の子であったことが記された書状なども残されており、その信憑性は低いようだ。仮に義龍が本当に頼芸の子だったならば、光秀が義龍に味方することが自然にも思えるが、しかしそうしなかったということは、やはり義龍は道三の子だったのではないだろうか。
義龍は父道三を討った後、中国で同じようにやむなく父親を殺害した人物から名を取り范可(はんか)と名乗るようになった。また、父親殺しの汚名を避けるためか道三を討つ際は一色を名乗っていたようだ。これらのことを踏まえるならば、もし義龍が本当に頼芸の子で、道三の子ではないのだとすれば、范可という名も一色という名も名乗る必要はなかったはずだ。
道三は小見の方を娶った後に明智城を攻めたのか!?
このように総合的に考えていくと、斎藤義龍の父親はやはり斎藤道三で、義龍は弟たちに寵愛を示していた道三によって廃嫡される可能性があったために、土岐氏を美濃から追放した極悪人を討伐するという名目によって長良川の戦いへと発展していったと考えられる。そしてかつての主君に忠誠を誓っていた安藤守就、稲葉一鉄、氏家卜全の美濃三人衆は道三に対し良い印象を持ってはおらず、長良川ではこの美濃最大の有力者たち3人が義龍側に付くことにより、道三はあっけない最期を迎えることになってしまう。
そして光秀の叔母である小見の方が道三の正室だった明智家としては、その小見の方を見捨てることなどできず、感情はどうあれ道三に味方するしかなかったのではないだろうか。ちなみに小見の方は天文元年(1532年)に道三(当時の名は長井規秀)に嫁いでいる。だが『細川家記』によれば、光秀の父である玄播頭は土岐家が道三に敗れた戦で道三に明智城を攻められ討ち死にしているらしいのだが、信憑性に関しては確かとは言えないらしい。
確かに明智家から小見の方を娶り、その後で明智城を攻め、なお小見の方を正室にし続けたとなると、やや辻褄が合わなくなる。となると光秀の父はもしかしたら、土岐家と斎藤道三による抗争とは無関係の戦で戦死したのではないだろうか。だとすれば辻褄も合う。
明智城を守る明智光安の苦悩
こうして考えていくと、やはり小見の方が道三に輿入れした天文元年以降、明智家は道三側とは一貫して良好な関係を維持していたのではないだろうか。そう考えなければ、圧倒的な兵力差がある中で明智家が義龍側ではなく、あえて道三側に味方した理由も、義龍が明智家を明智城から追いやった理由も説明がつかなくなる。
確かに斎藤道三はかつての主君である土岐家を美濃から追放した人物だ。しかし世は戦乱だったとしても、明智城を守る光秀の叔父光安としては、妹である小見の方を見捨てることなどできなかったのだろう。そう考えるともしかしたら長良川の戦い以降、明智家は明らかに道三に味方したわけではなく、立場を鮮明にせず自らに味方しなかったために業を煮やした義龍によって明智城を攻められたのかもしれない。だが今となってはその真実を知るすべはない。
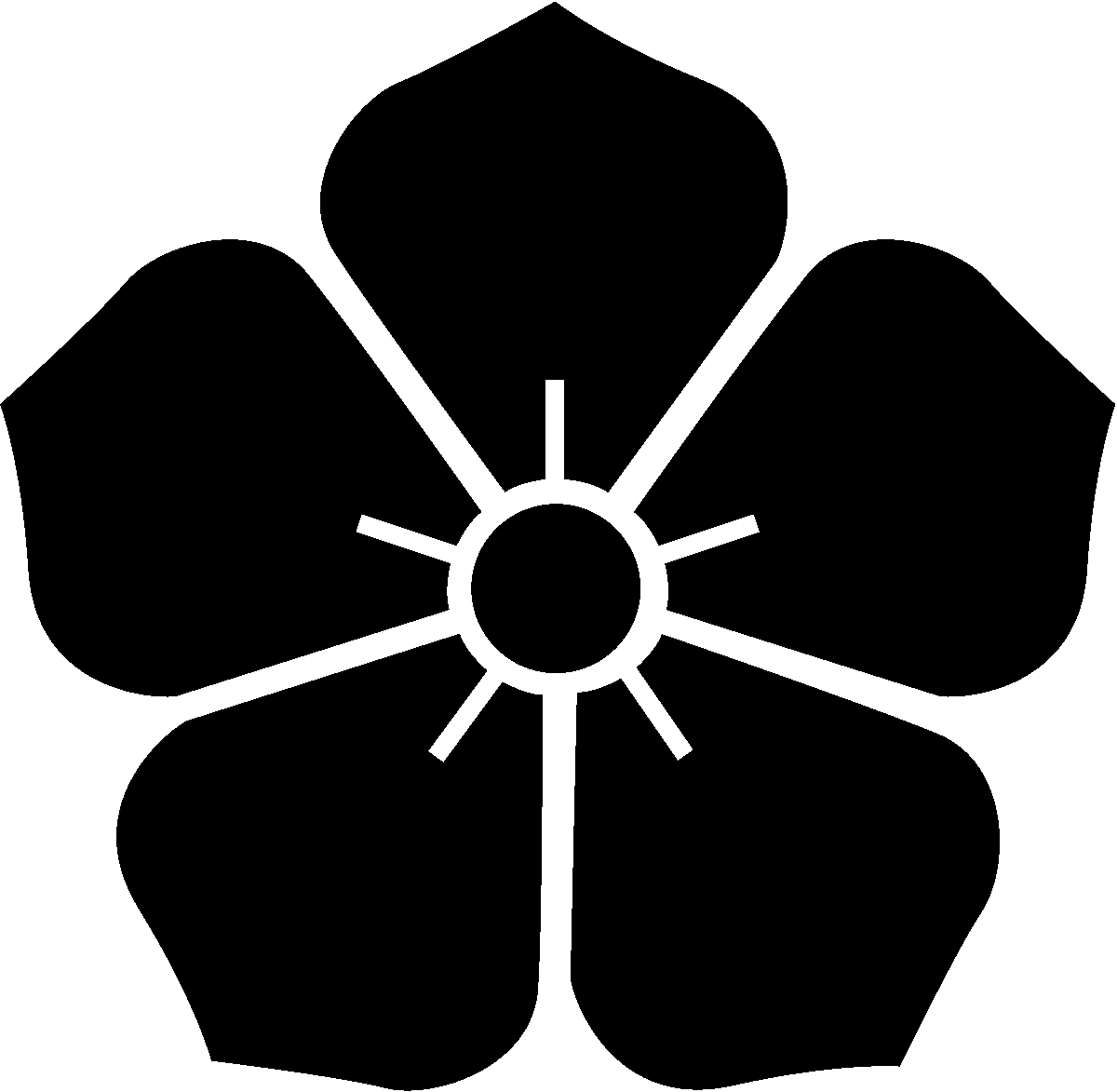
明智光秀という人物は時に、義理に堅くない武将として語られることがあるが、実際にはそんなことはなかった。義理堅く律儀な人物だったということが、光秀が残している書状などから読み取ることができる。
朝倉家の被官とは言え正式な臣下ではなかった光秀
光秀がなぜ義理堅くない武将として語られるかと言えば、それはひとえに主を次々と変えていったためだろう。順に追っていくと斎藤家、朝倉家、足利家、織田家と転々としている。まず斎藤家に関しては斎藤義龍に明智城を攻められて美濃を追われているため、これは光秀の意志ではない。その後越前の朝倉家に仕官するわけだが、その身分は平社員どころか、契約社員のような一時的なものだった。
その後朝倉家にも籍を置いたまま足利義昭に仕えていくわけだが、これは細川藤孝の推薦によるものであり、決して光秀が朝倉義景を蔑ろにしたわけではなかった。ちなみに足利義昭からすれば、大名家は幕臣であるという考え方があるため、各大名家の家臣は自らの家臣という考えもあったはずだ。
一方朝倉義景からすれば、契約社員1人が掛け持ちで他社で働いていたとしても痛くも痒くもない。そのため光秀は義景からすれば「欲しければあげるよ」という程度の存在だったと言える。
朝倉家と足利家に於いての明智光秀の地位とは
足利義昭の側近として織田家に出入りするようになると、光秀は織田信長に気に入られるようになる。その理由の一つとして、光秀が信長の正室である濃姫の従兄妹だったことも影響していたのだろう。この頃の光秀はまだ正社員と呼べるような地位は手にしていなかった。越前はもう完全に去っていたとしても、足利義昭自身「流浪の将軍」状態であり、家臣をしっかりと養う力を持っていたわけではない。そのような状況だったため、義昭と信長の取次役を務めているうちに、信長から頼まれる仕事の割合が少しずつ増えていった。
そうしているうちに光秀は初めて正式な家臣として織田家に仕えるようになる。光秀は決して、義景や義昭を踏み台にしていったわけではない。朝倉家と足利家では光秀は契約社員程度の身分であり、それを信長が初めて正社員として迎えたのであって、光秀が義理に堅くない人物であったからではなかった。
朝倉家が滅んだ直後に光秀が認めた書状の内容
光秀はよく筆を手にする人物だった。例えば束の間の休暇を取り旅行を楽しむと、親しい友人に向け、今でいう絵葉書のような手紙を書くこともあった。そして知人の体調が優れないと知れば、すぐに見舞いに出向いたり気遣いの手紙を書くこともあった。
光秀はどうやら越前にいた頃、竹という人物に世話になっていたようだ。だが朝倉家は後に織田信長に攻められ滅ぶことになる。朝倉家が滅んだ後、光秀は服部七兵衛尉(はっとりしちへいのじょう)という人物に「朝倉が攻められた際、竹を助けてくれてありがとうございました」という内容の書状を認めている。光秀が本当に薄情な人物だったとすれば、果たしてこのような書状を認めただろうか。
ちなみに戦国時代には、光秀のように二つの家で被官することは決して珍しいことではなかった。また、他家からの引き抜きも日常茶飯事であり、光秀のように仕官先を転々とする武将はどこにでもいた。だが確かにそれが元でいざこざが起こることもあり、戦がなくなった江戸時代には、他家からの引き抜きは幕府によって禁止された。
さて、この巻を読んでもらえれば、明智光秀という人物が決して義理堅くない人物ではなかった、ということがおわかりいただけると思う。朝倉義景や足利義昭を裏切ってきた人物なのだから、織田信長に刃を向けたのも不思議ではない、という考え方は間違いであると筆者は考えている。明智光秀という人物は、実は非常に義理堅い人物だったのだ。
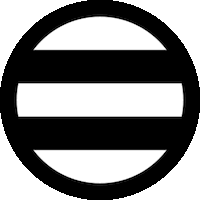
戦国時代のドラマを見ていたり、小説を読んだりすると必ず「上洛」という言葉が出てくるわけだが、果たして上洛とは一体何のために行われていたのか?そして上洛の意味はどこにあったのか?
各国に派遣された元々は外様だった守護大名
上洛について話をする際、まず考えなければならないのは室町幕府についてだろう。室町幕府とはいわゆる足利幕府のことで、戦国時代であれば足利義輝や、室町幕府最後の将軍となった足利義昭などが首長を務めていた幕府のことだ。足利幕府は元来、二十一屋形と呼ばれた各国の守護大名たちと相互関係を結びながら成り立っていた。そして守護大名は本来、洛内(京の都)にいることが義務付けられていた。
守護大名とは足利家の系譜にある人物が、その地を治めるために将軍によって各国に派遣された立場の人物のことだ。そのためその土地とは無縁の者ばかりで、それ故できるだけ早くその土地に馴染もうとし、守護大名たちはその土地の地名を名字に用いることが多かった。このように元々はその土地に所縁のない守護大名だったが、土地を治める年数が長くなるにつれ、その土地の有力者たちの厚い支持を得られるようになって行く。
そうなってくると元々は外様だった守護大名たちも力や経済力を持つようになり、次第に規則を破って洛内を出て下国(げこく:京から自らが守護している国に帰ること)してしまう守護大名が増えていった。そして戦国に世ともなると、洛内になお留まる守護大名はほとんど細川家だけになってしまう。
上洛とは?
将軍家直属の軍隊は1000~2000人程度の規模でしかなかった。この勢力だけではとてもじゃないか謀反や大規模な一揆を抑え込むことなどできない。そのため何か問題が起こると、将軍家は守護大名たちに出陣の要請を出し、それぞれの小規模な軍隊を集結することによって大軍隊を編成していた。だが上述の通り、戦国時代になると洛内に留まっていたのは細川家だけで、足利家は細川家だけを頼らざるを得ない状況に陥っていた。
ただ、その状況は戦国時代に突入する以前から続いており、もし細川家が衰退してしまったら、足利家も滅びの道を辿る運命にあった。それを防ぐために将軍は下国してしまっていた守護大名たちに、幕府に協力するように要請を出していた。その要請に応えて京の都に戻ろうとすることを「上洛」と言った。
では戦国時代において、大名が上洛する利点はどこにあったのだろうか?それは守護職を維持することや、官位を賜ることにあった。幕府から守護職や官位を賜ることにより、大名は幕府という大きな後ろ盾を得られるようになる。守護職=幕府に認められた大名、となるわけで、これによって国衆や有力者などの支持を集めやすくなり、治政も行いやすくなった。過去には守護職を剥奪されて衰退していった大名家もあるため、各国の大名たちはどうしても守護職を失いたくなかったというわけだ。ちなみに武田信玄は甲斐と信濃の守護職を務め、上杉謙信は越後の守護代を務めていた。織田家に関しては尾張守護職である斯波家(三官僚と呼ばれた名家中の名家)の家臣で、ただの奉行でしかなかった。そのため上洛してもなお、武田や上杉などから「田舎大名」と揶揄されることになる。
幕府の役割とは?
さて、幕府の長である足利将軍は一体どのような役割を担っていたのか?「戦国時代の将軍様はお飾りでしかなかった」と言われることもあるが、実際はそんなことはなかった。確かに力を失いつつあったという現実に間違いはないわけだが、しかし将軍の存在意義は戦国時代においても非常に大きかった。だからこそ武田信玄や上杉謙信という超大物であっても、上洛の要請にはしっかりと応じている。
将軍とは、今でいう最高判事のような存在だった。幕府の最大の役割は調停にあり、何か問題が起こると幕府に訴状を提出して裁定を仰ぐというシステムになっていた。つまり幕府とは最高裁判所のような存在だったわけだ。だが力を持った大名たちは問題を自分たちで解決できるようになり、幕府を頼ることも少なくなり、それによって幕府は資金源を失い始め力を失っていたというのが戦国時代においての室町幕府だったようだ。
織田信長が上洛するまでは、経済力を失っていた室町幕府のある京の都は荒れに荒れていた。とても都と呼べるような状況ではなかったわけだが、そこに登場し京の都を再建することによって織田信長はあっという間に幕府の信頼を得ていった。だがこの頃になると頼りの細川家も完全に力を失っており、その細川家はもはや織田の軍門に下っていた。
実は本来世襲制ではなかった守護職
室町幕府最後の将軍となった足利義昭の時代になると、室町幕府を支える家は完全に織田の一強となっていた。そして信長は思いのままに将軍と幕府を利用しようとし、それを嫌った足利義昭が各大名に上洛を求める書状を乱発していった。この義昭の要請により信長は幕府の救世主から朝敵という立場にされ、武田信玄や上杉謙信もその朝敵を討つという大義名分を得て、織田を討つために上洛を目指した。
大義名分という意味では、まだ義昭が将軍になりたての頃、信長は上洛の要請に応じなかった朝倉義景を将軍家に対する謀反者と断罪し、その謀反者を成敗するという大義名分を得ることにより、越前へ侵攻していった。戦国時代において大義名分は非常に重視されており、織田信長でさえも戦を仕掛ける際には必ず大義名分を用意していた。
上洛とはこのように、大義名分として利用されることも戦国時代には多かった。さて、最後にもう一点付け加えておくと、実は守護職というのは元々は世襲制ではなかった。だが長期間にわたり国替えが行われなかったために各守護大名たちが力をつけてしまい、徐々に幕府の手に負えなくなっていった。もし幕府が数年に一度転封(国替え)を実施していたら、室町幕府もまた違った終焉となっていたのだろう。

『惟任退治記』とは、天正10年(1582年)10月15日に行われた織田信長の葬儀の直後、織田信長がどのようにして明智光秀に討たれ、どのようにして羽柴秀吉が光秀を討ち信長の仇を取ったのかということを、秀吉が大村由己(おおむらゆうこ)という御伽衆に書かせた軍記物だと伝えられている。軍記物とは現代でいうところの歴史小説のようなもので、ノンフィクションではなく、フィクションも多分に含まれている。そのため歴史研究においては、ノンフィクションのみが記されていると思われる日記や書状などを一次資料と呼ぶのに対し、フィクションも含まれている軍記物は二次資料と呼ばれている。
ただ、軍記物といっても100%フィクションというわけではなく、史実通りのことが書かれていることが多いのは現代の歴史小説と同様だった。ただ、書いた者や書かせた者の主観が含まれることが多いため、事実が捻じ曲げられていたり、物語そのものが創造されていることも多い。だがそのあたりを踏まえて読んでいくと、軍記物は歴史ファンにとっては非常に楽しめる読み物だと言える。今回、戦国時代記では『惟任退治記』という、12編からなると言われている『天正記』の1編を、現代語訳どころか、現代小説風に書いてみたいと思う。言葉遣いなどはまさに現代小説風になっていくが、書かれている内容や意味は、原文通りにし、筆者の脚色等は一切排除した内容にしていきたい。
惟任退治記(1)皇居が移動して来たかのように賑わう安土城
世間というものは栄えたり衰えたりということを繰り返すことによって成り立っている。南山(なんざん:高野山のこと)の春の花は咲き誇ったかと思えば逆風により散っていき、東嶺(とうれい:京都の東山のこと)に美しい秋月が見えたかと思えば厚い雲がそれを覆い隠してしまう。そして力強く根を張る樹齢長き松の木でさえも伐採されることを自ら避けることはできず、寿命万年といわれる亀でさえもいつかは死んでしまう。また、朝顔の花に落ちる露や、荘子が見たという自ら蝶となり花の上で100年遊んだという夢の目覚めのように、世の栄華というのは実に儚い。
亡くなった後に太政大臣に叙せられた織田信長公は、長きにわたり日ノ本のリーダーとして国家を主導してきたが、その亡くなる前、信長公は近江の安土山に城郭を築いた。大きな石で土台が作られた建物の屋根が連なり、天守閣は天まで届きそうなほどに高くそび、それら煌びやかな建物が鏡面のような琵琶湖の水面に映り、その美しさは言葉で表すことなどできない。
恐れ多くも正親町天皇をはじめとし、朝廷に仕える公家たちも身分の上下問わず、毎日のように信長宛てに連絡を入れ、続々と安土城に集まってきた。その様子はまるで皇居が安土城に移動して来たかのようだった。三管領と呼ばれた室町幕府の名家、斯波家、細川家、畠山家の人間で、信長公を崇拝しない者は誰一人としていない。そして信長公は彼らと、100羽の鷹を集めて鷹狩りに出かけたり、千とも万とも言われた数の馬を集めて馬揃え(軍事力を誇示し諸大名に力を見せつけたり、軍の士気を高めるために行われた一大行事)を行った。
朝廷の者たちは、私欲のない清らかな政治を志し、曲がったことは正すと言いながらも、夜になると奥に控えていた3000人の美女たちを欲しいままにした。正しいことを行うと言いつつ毎夜催された宴は、いくら楽しんでも尽きることがなかった。唐(とう:中国の王朝名)の玄宗皇帝が所有していた温泉付きの驪山宮(りざんきゅう)や、洛陽(らくよう:中国河南省の非常に栄えていた都市)の上陽殿(宮殿)の娯楽でさえも、安土城の物ほどではなかっただろう。


惟任退治記全文掲載

永禄10年(1567年)11月、この頃初めて織田信長が「天下布武」の朱印を使い始めたとされている。一般的には「武力を以って天下を治める」と理解されているが、しかし実際にはそういう意味ではなかった。この言葉は臨済宗妙心寺派である沢彦宗恩(たくげんそうおん)が信長に進言したとされているが、しかし実際にそうであったという明確な記録が残っているわけではないようだ。
天下布武、岐阜命名は沢彦の助言によるものだった
沢彦宗恩は、吉法師(幼少時の信長)の守役であった平手政秀と親交があったことから、その平手政秀の推薦により吉法師の教育係に任命された僧侶だった。そして平手政秀が信長の蛮行の責任を取る形で自刃(自刃の理由は諸説あり)を果たした後も、信長の相談役として仕え続けた。天正15年(1587年)に死去したことはわかっているが、しかし生まれた年などの記録はまったく残っておらず、よく名が知られた戦国時代の僧侶であるにも関わらず、非常に謎が多い人物でもある。
一部ではこの沢彦が「天下布武」という言葉を信長に進言したとされているが、実際にそうだったのかはもはや誰にもわからない。だが常時信長の側に仕えていたことは事実であるため、今日ではその可能性が高いと考えられている。ちなみに稲葉山という地名を岐阜に変えた際の助言も沢彦が信長に与えており、この時沢彦は岐阜、岐山、岐陽という三案を伝え、その中から信長が岐阜を選んだとされている。
天下布武とは武力で天下を治める、という意味ではなかった?!
さて、ここからが本題であるわけだが、「天下布武」とは決して武力を以って天下を治めるという意味ではない。ではどういう意味かというと、「足利将軍を中心にし、乱れていた畿内の秩序を取り戻す」という意味となる。天下というのは日本全国ではなく、政の中心地だった畿内のことを指し、武とは武家、つまり足利将軍のことを指している。
この頃の信長は多くの書状に「天下布武」の朱印を使っているわけだが、仮に「武力を持って天下を治める」という意味であったなら、信長はこの朱印を用いることで、全国の大名たちに宣戦布告していた、ということになる。だが実際には宣戦布告として受け取られることはなく、戦国時代では「天下=畿内」「武=足利将軍」という意味はごく一般的な言葉として使われていたようだ。
天下布武から天下静謐へ
信長は永禄11年(1568年)に足利義昭を奉じて上洛を果たしている。つまり第13代将軍足利義輝が松永久秀と三好三人衆の陰謀により殺害され、その後義輝の従兄弟である足利義栄が第14代将軍の座に就くも約半年ほどで死去したことにより乱れ切っていた畿内の秩序を、信長はその時に取り戻したということになる。これによって天下布武は達成されたと考えることができる。
そしてあまり知られてはいないが、信長は「天下布武」を成した後は「天下静謐(せいひつ)」を自らの政治的標語としている。天下静謐とは、取り戻した秩序を維持するという意味だ。信長と義昭の関係が良好だった頃は、義昭が政治面での静謐、信長が軍事面で静謐を担う分業制を敷いていた。だが仲違いし義昭を追放した後は、信長は天下静謐を全面的に自らの職責としていく。
最後に一点付け加えておくと、信長は義昭を利用し、義昭も信長を利用していたとよく言われるが、しかしこれは信長と義昭に限った話ではない。室町幕府では将軍家とそれを支える大名家、つまり細川氏や六角氏などは、お互いにお互いを利用し合うことで力を維持してきたという歴史がある。つまり信長と義昭がお互いを利用し合ったことは、当時の将軍家と有力大名の間ではごく自然なことだったということを伝えて、この巻を締めくくることにしたい。
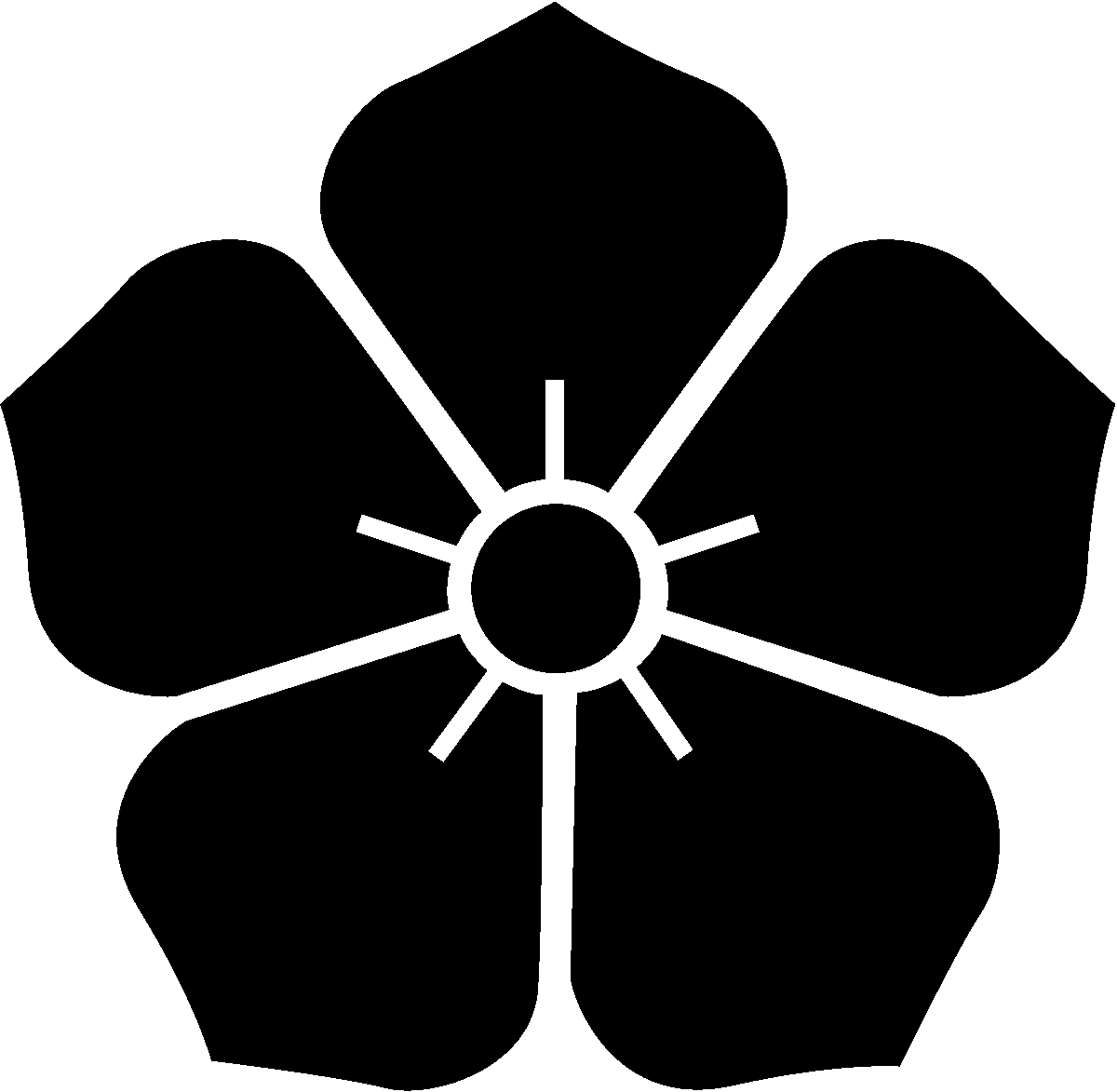
明智光秀は過度のストレスによりノイローゼに陥り、半ば錯乱状態であるかのように思いつきで信長を討った、という説もある。だが筆者はこの説にはあまり信憑性を感じることはできない。そもそも仮に光秀がそんな状態であったならば、斎藤利三や明智秀満と言った側近たちが気付いていないはずがない。もし光秀がノイローゼで側近たちがそれに気付いていたのであれば、普通に考えれば明智家を守るため、命を賭してでも光秀の盲動を防いでいたはずだ。逆に光秀の異常を察知できないような家臣を、側近と呼ぶことなどできるだろうか。
愛宕百韻はあくまでも戦勝祈願のための連歌会だった
あくまでも筆者個人としては、光秀は多少の心労は抱えていたとしても、ノイローゼではなかったと思っている。その論拠となるのは、光秀は頻繁に茶会や歌会を催しているし、戦が小休止している時にはちょっとした旅行に出かけ、旅先から友人に向けて書状を送り、幸せのお裾分けまでしているのだ。つまり光秀はただ辛い戦さの日々を過ごしていただけではなく、茶や連歌、旅を楽しむという余裕も心には持っていたのだ。
もし本当にノイローゼだったら、歌会で丸一日一緒にいる友人たちの誰かは異変を感じ取っていたはずだが、しかし歌会はどれも滞りなく行われていたようだ。唯一誰かが異変を感じたとすれば、それは本能寺の変の三日目に愛宕山の威徳院西坊(いとくいんにしのぼう)で行われたとされる(三日前は晴れ、雨の日に催されたのなら七日前、という説もある)、いわゆる愛宕百韻と呼ばれる歌会でだろう。光秀はこの時の発句(最初の一句目)として「時は今 天(あめ)が下(した)しる 五月(さつき)哉(かな)」と読んでいる。この句を少し説明すると、時=土岐、天が下=天下、しる=統べる、という意味となり、意訳すると「土岐家が天下を統べる時がやってきた」と解釈することもできなくはない。だが実際に光秀が読んだのは「時は今 雨が下なる 五月哉」だそうです。つまり「統べる」という意味合いは含まれてはおらず、「統べる(しる)」という表現は『惟任退治記』という秀吉が書かせた軍記物で広められた出鱈目だったようです。
ということもあり、上述した句の意味は後付けされたもので、実際には普通に「季節は今は五月、よく雨が降りますね」という梅雨の情景を歌った句でしかなかったようだ。さらに言えば明智憲三郎氏が指摘する通り、「五月哉」と読みつつ六月に信長を討ったことにも違和感がある。そして光秀がこの発句を読むために、わざわざ本能寺の変の三日前にこの歌会を催したとされる説もあるが、そもそも戦国時代当時、歌会というのは戦勝祈願の意味合いが強かった。その証拠にあらゆる出陣の直前に連歌会が催されている。ちなみにこの時の光秀には信長から、中国地方の毛利氏を攻めている羽柴秀吉の救援に向かえという命令が下されており、まさに中国地方に向けて出陣する直前だった。つまりこのタイミングで連歌会が催されたことは、戦国時代の背景を考えればごく普通のことだったと言える。
光秀の妹の死が信長と光秀を仲違いさせたという説
光秀が精神的に追い込まれていたという説を追うと、やはり出てくる話は光秀の妹に関することだ。実は光秀の妹は信長の側室となっていた。この妹の存在によって信長と光秀の関係は良好に保たれていたと言われている。だが彼女は本能寺の変が起こる前年の8月に死去してしまう。妹の死によって信長と光秀の間には緩衝材のような存在がなくなり、それによって二人が衝突し始める、と考える専門家の方もいるようだが、果たして国を代表するレベルの二人がそのような理由だけで仲違いするものだろうか。しかも光秀は妹の死後も変わらず信長のために激務をこなし続けている。そんな光秀を、果たして側室だった光秀の妹の死を境に急に信長が嫌うようになるだろうか。流石にそんな子供染みたことはしないと思うし、そうしたと考える方が不自然だと思う。
さらにもう一点付け加えておきたいこととして、光秀の妹の死があったとしても、信長と光秀が従兄弟同士ということに変わりはない。信長の正室である帰蝶(濃姫)は光秀とは血の繋がった従兄妹であり、つまりは信長と光秀は義理の従兄弟同士ということになる。この関係がある限りは、光秀の妹の死によって状況が大きく変わることはなかったと筆者には感じられる。
誰にも気付かれなかった光秀のノイローゼ
さて、そもそもノイローゼになっている人というのは、周りから見てもすぐにそれとわかる。ノイローゼだという確信は持てなかったとしても、普通の状態ではない、ということは誰にでも察することができる。それがノイローゼという状態だ。冒頭にも述べた通り本当に光秀がノイローゼだったのならば側近は必ず気付いているだろうし、細川藤孝や吉田兼見といった気心の知れた友人や、連歌仲間たちが気付いたことを日記などに記していたはずだ。そして誰かが気付けば、それは必ず信長の耳にも入ったはずだ。だが誰も光秀の精神状態を心配するような素振りは見せていない。
となるとやはりノイローゼ説は、軍記物(江戸時代に流行った当時の歴史エンタテインメント小説)に書かれたあることないことを鵜呑みにした方が、創作である可能性が高い記述を状況証拠として採用してしまい、「本当にそんな状況だったら普通ならノイローゼになってしまう!」という印象論によって書いたことではなかったのだろうか。そもそも本当に光秀がノイローゼだったならば、深い知見によってアドリブで百句、千句と繋げていく連歌を中心人物としてこなすことなどできなかったはずだ。連歌会に集う人物たちは皆深い知見を持ち、とにかく頭の良い頭脳派の人たちばかりだったのだ。ノイローゼだった人が、そんな彼らと連歌で対等にやり合えたとは到底思えない。以上のようなことから、光秀はノイローゼなどではなかったと、これを筆者個人の意見としてこの巻を締めくくりたい。
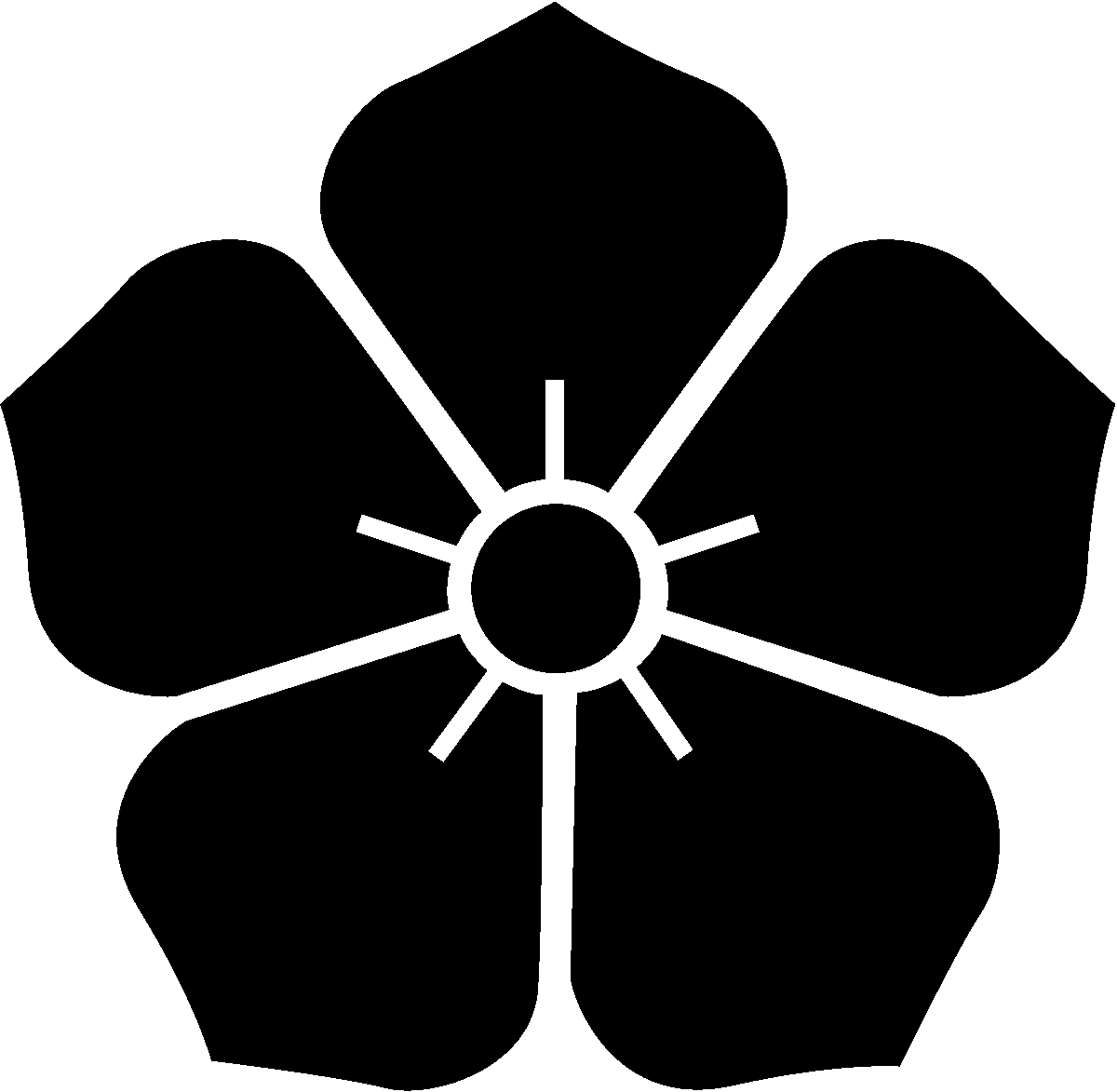
明智光秀は長曾我部家を救うために本能寺の変を起こした、という説もあるが、これは違うと思う。本能寺の変の少し前まで明智光秀は、織田家と長曾我部家の取次役を務めていた。この任を与えられた理由は、光秀の重臣である斎藤利三の兄、石谷頼辰(いしがいよりとき)の義理の妹が、長曾我部元親の正室だったためだ。
明智光秀の顔に泥を塗った長曾我部元親
織田家と長曾我部家の両家は友好的だった時期もあったのだが、それが次第に険悪になっていく。信長としては潰そうと思えば潰せてしまう程度の長曾我部家にできるだけ良くしてきたという意識があったようだが、しかし両家の間でなかなか思うように事が進まないことに苛立ち始めていた。その最中、本能寺の変の前年となる天正9年(1581年)8月、長曾我部元親が、織田家との共通の敵であったはずの毛利家と同盟を結ぶという大事件が起こってしまった。
信長は当然これに激怒したはずだ。信長は、元親の嫡男である信親の名に自らの名の一部を与えているほど長曾我部家を買っていた。つまり元親の毛利家への急接近は、信長に対する裏切り行為に他ならない。この行為は取次役を務めていた光秀の顔に泥を塗るも同然の行為だったと言える。ここまで侮辱されてなお、斎藤利三の縁者という理由だけで光秀が長曾我部家のために本能寺の変を起こしたとは考えにくい。
光秀に合流する姿勢を一切見せなかった元親
さて、本能寺の変が起こる時期、織田家と長曾我部家の間には辻褄が合わない出来事が起こっている。本能寺の変の当日、信長の三男である神戸信孝と丹羽長秀隊が長曾我部家討伐のために出陣している。だがそこから遡ること10日、長曾我部元親は信長に対し、一定の条件を提示しながらも、信長が提示した国分案に同意する書状を認めているのだ。元親は信長に対し恭順の意を示していたにも関わらず、信長は四国に派兵しようとしていた。恐らくは、このような事実を踏まえて、光秀が長曾我部家を救おうとしたという説が出されたのではないだろうか。
だが自らの家を守るためならともかく、自分の顔に泥を塗った長曾我部家を救うために、果たして光秀が主君を討つなどありうることだろうか。筆者個人としてはないと思う。更に言うならば本能寺の変後、長宗我部家は明智光秀に合流する姿勢を一切見せていない。仮に光秀が長曾我部家を守るために本能寺の変を起こしたのであれば、それを元親が知らないはずはないし、もしそれを把握していたのであれば、元親は中国大返しをして見せた羽柴秀吉の背後を突いていたはずだ。だが元親は一切そのような素振りは見せていない。
本能寺の変がなければ滅んでいた長曾我部家
仮に本能寺の変が起こっていなければ、長曾我部家は神戸信孝・丹羽長秀隊によってあっという間に殲滅させられていただろう。織田家と長曾我部家にはそれだけの力の差があった。だが結果的には本能寺の変が起こったことにより、元親は命拾いしたのだった。ちなみに本能寺の変が起こる前の時期に、光秀と元親が交わした密書などは一切残されていない。明智家・長曾我部家の両家共に残っていないのだから、ふたりの間に書状のやり取りはなかったのだろう。となるとやはり、光秀が長曾我部家を救うために本能寺の変を起こした、という説には無理が生じてくる。
明智光秀という人物は、自らの源流である土岐家の再興にこだわりを見せていたことで知られる。いつかは土岐家を再興させたい、それが光秀の最たる望みだったようだ。その望みがあるにも関わらず、他家のために自らの家を滅ぼすようなことは決してしないはずだ。するとすればやはり、自らの家を守るためではないだろうか。そう思うからこそ筆者は、光秀は長曾我部家を守るために本能寺の変を起こしたのではないと感じているのである。