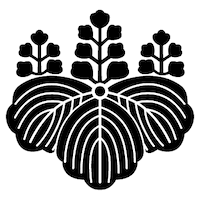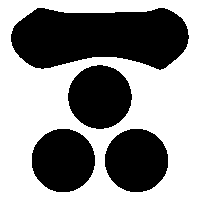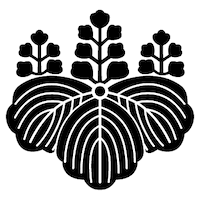
河屋城を落とすと、秀吉は備中高松城(岡山市・清水宗治が城主)に軍勢を集結させた。城の周囲を見渡すと三方が深い沼地になっており、人や馬が通れる場所はまったくなかった。そして残る一方は幾重にも大堀が構えらえており、ここは毛利家が何年もかけて普請(ふしん:築城に関する土木工事)してきた難攻不落の要塞だった。例え日本中の勢力を集めた大軍で攻めたとしても、落とせそうにはなかった。
そのため秀吉は熟考し、水攻めをすることにした。城の周囲2~3里(8~12km)に山のような堤を築き、堤の裏には木材を使って水をせき止めるための柵を作り、大河や小川の河上を辿って開鑿(かいさく:土地を切り開いて道路や運河を作ること)し、岩石を崩し、谷ノ口や水田の用水、溜水に至るまでことごとくせき止めたため、高松城の周囲はたちまち湖のようになってしまった。
そして新しく築いた堤の上に攻撃用の付城(つけじろ)をいくつか作り、さらには大きな船で連隊を組み、「乙の丸」という曲輪(城壁や堀などで仕切られた城の区画)に攻め込み、曲輪を隔てていた壁代わりの建物を次々と取り壊していった。それにより「甲の丸」という曲輪と一つに繋がってしまった。
敵兵は水深を見ながら竹や葦を糸で組み、板を並べて住まいを作ろうとした。その波に漂う陣小屋は、小舟のようにゆらゆらと揺れていた。それはまさに籠の中の鳥や、網の中の魚のような悲しい気分を味わっているようだった。
これとは別に秀吉は、1万少々の軍勢を城から5町10町(500m~1km)隔てて陣取らせ、後方の備えをさせた。すると毛利輝元、小早川隆景、吉川元春は、何とかこの高松城を救わねばと考えた。そして備中表(おもて)にて決死の覚悟で戦おうと、10ヵ国から8万余りの兵を集め、備中高山(こうざん:総社市の高山城)に続く釈迦が峰、不動岳に陣取った。彼らと秀吉との距離は1km程度しかなかったが、その間には大河があったため、すぐに攻め込むことはできず、数日の間は手をこまねいていた。
秀吉は毛利の大軍を攻めるかどうか決めかねていた。攻めれば打ち破る自信はあったが、中国地方の平定について信長に意見を伺ったところ、軽々しい戦はしないようにとのお達しが、使者とともに堀秀政、中川清秀、高山右近、池田元助(池田恒興の嫡男)らが加えられ遣わされた。
そして信長は信忠(信長の嫡男)を伴い京に入った。そして惟任日向守光秀(これとうひゅうがのかみ:明智光秀)を援軍として備中に送り、すぐに着陣し秀吉と相談しながら事に当たるようにと命じた。そしてその戦況によっては信長自らも出陣を厭わない旨をも伝えた。


惟任退治記全文掲載
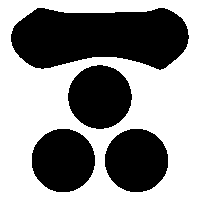
当時、毛利元就は大内義隆の傘下に入っていた。しかしその大内義隆が天文20年(1551年)に陶晴賢に討たれてしまう。この直後こそ元就は陶氏に従属の意を示していたが、しばらくすると大名として独立色を強めるするための行動を取り始める。それにより毛利元就と陶晴賢は敵対関係となり、天文24年の厳島の戦いへと繋がっていく。
毛利元就は天文24年、厳島に宮尾城を築城したのだが、その城が陶晴賢に攻められてしまう。この時陶晴賢は2万人以上の軍勢を率いて厳島に上陸し、島北部の塔ノ岡に本陣を置いた。そして9月21日、宮尾城の攻撃を開始する。宮尾城が攻められているという報せを受けると、元就は毛利隆元と吉川元春を率いて佐東銀山城(さとうかなやまじょう)を出立し、9月24日に厳島の対岸となる草津に到着した。
そこから船で島を時計回りに進み包ヶ浦(つつみがうら)に上陸すると、陶軍の背後に回り博奕尾山(ばくちおさん)に着陣した。この戦いで元就は水軍の協力を得て、陶方の水軍を寝返らせることにも成功しているのだが、しかしそれでも毛利勢は3000人程度という寡兵でしかなかった。陶軍が2万人以上の大軍で攻めて来ている中、とても正攻法で勝てるような差ではなかった。
元就を追うように小早川隆景も厳島に向かい、厳島神社のすぐ西にある大元浦から上陸しようと試みるも、しかし陶方の警護が固く上陸することができなかった。すると隆景はそのまま反時計回りに西へと船団を進めていく。この時小早川勢に加わっていた乃美宗勝が、闇夜に紛れ、敵方の援軍を装い厳島神社の鳥居付近に上陸することを進言した。
一か八かの賭けではあったがこれが上手くいってしまう。暗闇となっている海岸線では、敵味方の区別を付けることは困難だった。小早川勢は筑前からやってくる予定だった陶方の援軍宗像氏を装い、陶方の警護の中を難なく通り抜けてしまった。
10月1日は早朝から暴風雨で荒れていた。恐らく台風だったのだろう。だが毛利元就はこの暴風雨を奇襲の味方に付けた。突撃を合図する太鼓が打ち鳴らされると、博奕尾山に布陣していた毛利本隊が一気に山を駆け下りて陶本陣の背後を突いた。陶方はまさかこんな暴風雨の中毛利勢が攻めてくるとは予想しておらず、本陣は大混乱に陥ってしまう。
しかも毛利本隊とは別に、厳島神社の方からも今度は丘を登ってくる形で小早川勢が攻めて来た。陶方からすれば、その方角は警護を固めていたはずで、敵がいるはずのない方角だった。だが闇夜に紛れ援軍を装い身を潜めていた小早川勢が勢い良く攻め込んでくる。2万以上の陶勢は完全に挟撃させる形となってしまった。
開戦前は陶勢が圧勝すると思われていたこの戦いだったが、しかし2万と3000という兵力差が陶晴賢を油断させてしまった。まさかの形で挟撃されてしまい軍勢は総崩れとなってしまう。陶晴賢は何とかこの窮状を抜け出し大江浦まで兵を退くも、しかしそこで手詰まりとなり自害してしまう。まだ35歳という若さだった。その若さ故に油断という大敵に敗れてしまった。
厳島の戦いで陶晴賢を討ち取ったことにより、毛利氏の勢いは加速されていく。そしてかつて傘下に入っていた大内氏を継いだ大内義長を攻め自刃させると、毛利元就は中国地方を手中に収めることに成功した。毛利氏が独立大名として発展して行く大きなきっかけとなったのが、この厳島の戦いだった。
もしこの戦いで陶氏に敗れていれば、毛利氏はそこで滅亡する可能性すらあった。だが乃美宗勝の機転と元就の奇襲、そして若き陶晴賢の油断により毛利はこの戦いで奇跡的な大勝利を収めることができた。その後毛利氏が版図を拡大させることができたのも、この戦いで勝利した結果あってこそだった。そういう意味で厳島の戦いは、毛利元就にとっては最も意味深い一戦だったと言えるのだろう。
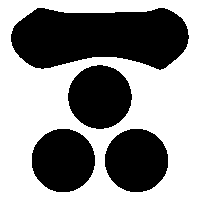
毛利輝元と石田三成は盟友で、お互い助け合った場面が多々ある。この縁があり関ヶ原の戦いでは三成の要請に応える形で、輝元は西軍の総大将に就いている。だが輝元は関ヶ原開戦前に三成を裏切り、東軍に内通してしまった。兵力の分散など、毛利勢が関ヶ原でほとんど打って出なかった理由は他にもあるわけだが、一番の理由は東軍への内通だったようだ。
関ヶ原前の毛利家は、決して一枚岩とは言えない状況だった。まず小早川隆景を失ったことにより、毛利家は豊臣政権では力を失いつつあった。その上御家騒動を家康に干渉されるなどのこともあり、毛利家内は毛利輝元と吉川広家との派閥に二分されていた。もっと言えば政略を担当していた安国寺恵瓊派と、軍事面を担当していた吉川広家派とで関係が上手くいっていなかった。隆景が死んだことによりこの対立がより鮮明化されてしまい、関ヶ原の時点では毛利はまったく一枚岩とはなっていなかったのだ。
輝元の祖父、毛利元就はこうなることを予見していたからこそ「
三矢の教え」を説いたのだろう。だが元就の願いも空しく、毛利家の分裂は日ごとに増してしまい、関ヶ原の時点では修復し難い状況にまで陥っていた。中でも広家は、恵瓊に対し良い感情をまったく持っていなかったと言う。
輝元は三成とも良好な関係を築いていたが、実は家康とも友好関係を結んでいた。そのため輝元が西軍の総大将になったことを聞くと、家康は非常に驚いたと言う。しかしこれを吉川広家が、すべては安国寺恵瓊の考えだと家康に弁明してしまう。つまり輝元は何も知らず、恵瓊の言う通りにしていたら西軍の総大将にされてしまった、というわけだ。
もちろん事実は違う。輝元と三成の関係あってこその総大将への就任であり、家康の毛利家に対する干渉への対抗心もあったようだ。だが最終的に輝元が優先したのは領地安堵だった。
関ヶ原の戦いは、総勢だけを見れば西軍も東軍もほぼ互角だった。この互角の戦力が真っ向から戦えば、どちらに勝利が傾くかはまったくわからない。だが毛利輝元が東軍として戦わないまでも、西軍として出陣さえしなければ、西軍には勝ち目はほとんどない。さらには小早川秀秋の東軍への内通も明らかになっていたため、輝元と秀秋が東軍に味方をすれば、ほとんど100%東軍が勝利するという状況だった。
そこに家康は東軍が勝利した暁には、現在の毛利の領地を安堵するという密約を輝元と結んだ。これにより関ヶ原の戦いが開戦する前日までに、西軍の総大将が事実上西軍から離脱する形となってしまった。この状況ではやはり西軍に勝ち目などまったくなく、開戦後は2時間も経たないうちに西軍は総崩れとなってしまった。
もう一度繰り返すが、輝元が西軍の総大将に就いたのは恵瓊の策略ではない。三成への友情と、家康への対抗心から輝元自らが総大将に就くことを了承したのだ。決して恵瓊が騙したわけではない。家康は広家の弁明を聞いたからこそ毛利の領地安堵を約束したわけだが、しかし関ヶ原の戦いが終わると、輝元が自らの意思で西軍の総大将に就いたという証拠が出てきてしまった。
これにより開戦前は120万石だった毛利家が、関ヶ原の戦いの後は30万石まで減封されてしまう。版図拡大に情熱を注いでいた輝元としては、立ち直れないほどの衝撃だったのだろう。減封後は間も無く隠居し一線から退いてしまった。ちなみにこの時、毛利家の取り潰しという話もあったようだが、吉川広家の尽力もありそれは回避され、30万石への減封で収まったのだと言われている。
だが冷静に考えれば、もし吉川広家が輝元に完全に味方し関ヶ原の戦いで奮闘していれば、西軍が勝利する可能性も決して低くはなかった。そして西軍が勝っていれば120万石以上を手にできた可能性もある。安国寺恵瓊にしても、そのような考えがあったからこそ西軍への参陣を説いていたのだろう。
しかし恵瓊を毛嫌いする広家の対応もあり、毛利家は結局関ヶ原では戦うこと自体を避けてしまった。最終的には周防・長門の30万石は維持できたものの、実はこの30万石は当初、家康は吉川広家に与えると言っていた。だが広家がそれを拒み、30万石は毛利家に与えて欲しいと懇願し、毛利家の改易処分が免れている。
もしかすると広家には、自分の対応が毛利家を取り潰してしまうところだったという罪悪感があったのかもしれない。だからこそ自らに与えられた30万石を、そっくりそのまま毛利家に譲ったのではないだろうか。今となっては真実は定かではないが、広家の一連の行動からは、そのようなことも想像できるのではないだろうか。
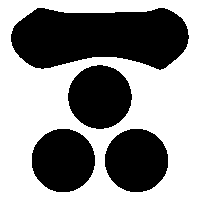
もし毛利輝元が元就の遺言を忠実に守っていれば、もしかしたら関ヶ原の戦いで徳川家康率いる東軍が勝利することもなかったかもしれない。だが領土拡大を目指したことにより兵力が分散してしまい、関ヶ原の戦いで思うような兵動員ができなくなってしまった。そして盟友である石田三成を助けることもまた、できなかったのである。
元就には、国人衆あがりの大名がこれ以上領土を拡大しようとしては、とてもじゃないが治め切れないし守り切れないことがわかっていたのだ。だからこそ遺言で版図拡大を禁じたのである。そして国人衆あがりとして国人衆をまとめることは苦労の連続だが、しかし3人が力を合わせれば今の領土を守り抜くことができると考えていた。「三矢の教え」とはそれを伝えるためのものだったのだ。
では毛利輝元はなぜ元就の遺言を守らなかったのか?豊臣政権に於いて毛利輝元と小早川隆景は共に大老だったわけだが、これは豊臣秀吉が小早川隆景を盟友として見ていたからだ。隆景のいる毛利家であれば、筆頭大老徳川家康の抑止力になると秀吉は考えていた。そのため6人の大老の中でも家康、輝元、隆景は別格の扱いだった。しかし秀吉よりも1年早く、慶長2年(1597年)6月12日、隆景は急逝してしまう。死因は脳卒中だと言われている。
隆景が死去すると、豊臣政権での毛利家の力が少しずつ失われていった。隆景存命の頃は家康と同等だったわけだが、しかし輝元のみになると事情が変わってきてしまう。秀吉は家康の抑止力として今度は前田利家を選んだのである。つまり筆頭大老が家康と利家に変わり、輝元の格が下げられてしまった。輝元はこの処遇により毛利家当主としての誇りを傷つけられてしまう。
その傷ついた誇りを癒すために、関ヶ原開戦の直前になり版図拡大を目指し始めたのだった。そしてこれが元就の遺言を守らなかった原因だと考えられる。隆景が存命中は、隆景が輝元の抑止にもなっていたため、輝元が元就の遺言を破ることもなかった。しかしその隆景が逝去してしまったことにより、輝元は自由に毛利家を動かせるようになった。
毛利家の礎は先代までがしっかりと固めてくれていた。そのため輝元は国人衆あがりの戦国大名の苦労をそれほど知らずして育っていく。いや、実際には父隆元、隆景、元春らが伝えていたのかもしれないが、しかしそれらは輝元にとっては一昔前の話に過ぎなかったのである。だからこそ元春、隆景が亡くなると、輝元は内に秘めていた野心を解放し始めたのであった。
元就が「三矢の教え」を与えた際、輝元はまだ18歳の若者だった。もしかしたら18歳の輝元には、元就の真意を理解するに至らなかったのかもしれない。そして輝元はもはや国人衆あがりの大名ではなく、大名の子の大名という世代になっていた。だからこそ輝元には元就の遺言を守ることよりも、野心を見せ領土拡大を目指した方が毛利家のためになると考え行動したのだろう。
輝元は決して「三矢の教え」や遺言を忘れたわけではなかったと思う。だが輝元自身の判断として、領土を拡大し、毛利の力をさらに強くしていくことが最善だと状況判断したのだ。だが関ヶ原の戦い後の毛利家の姿を見ると、結果的には元就が正しかったということになる。200万石とも言われ栄華を誇った毛利家が、37万石の小大名となってしまったのだから。
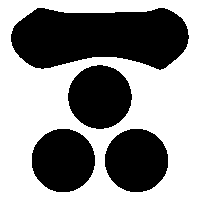
毛利元就は元亀2年(1571年)7月6日、老衰もしくは食道癌にて75年の生涯を閉じた。その病床に元就は2人の息子と家督を継いだ孫を呼び、1本ずつ矢を手渡し、それをそれぞれ折らせた。矢は当然かんたんに折れてしまう。そして次に3本ずつ矢を渡しまとめて折らせた。だが1本なら容易く折れてしまう矢も、3本まとめればなかなか折ることができない。元就はそうして3人を諭し、元就亡き後は3人で力を合わせて毛利家を守るようにと伝えた。これが世に言う「三矢(さんし)の教え」だ。
この時元就に呼ばれたのは孫の毛利輝元(嫡子隆元は41歳の若さで死去)、吉川元春、小早川隆景の3人だった。いわゆる毛利両川と呼ばれた3人で、吉川家に養子となった次男元春、小早川家の養子となった三男隆景、そして長男隆元の子である輝元だ。そして彼らに対し元就は、これ以上の版図拡大はしないようにと遺言を残した。つまり現有の領地をしっかり守り抜くことだけに尽力し、それ以上の領土拡大は行うな、ということだ。
毛利家ほどの大大名であれば、普通であれば天下を目指していても不思議ではない。だがそこには毛利家特有の問題が存在しており、うかつに天下を目指すことができない事情があったのだ。それは毛利家が国人衆あがりの戦国大名だったことに所以している。
戦国大名が県知事だとすれば、国人衆は言わば市長であり、国人衆あがりの戦国大名とは、その国の国人衆のまとめ役という色合いが強いのだ。ちなみに真田家も国人衆あがりとなる。国人衆上がりの戦国大名を、国人衆は自分たちとほとんど対等くらいに考えていたのだ。つまり毛利家は領地の国人衆に対し、絶対的な権力を持っていなかったということだ。
毛利家が少しでも隙を見せるようなら、いつでも自分たちが代わりに国人衆の代表を務める、というくらいに考えていた。そのため一般的な戦国大名と比べると、毛利家は領土をまとめ上げるのに非常に苦労をしていたのだ。その点に関しては真田家と共通している。そしてそういう意味で絶対的なカリスマであった織田信長や、名門武田信玄よりも民政に神経を使っていたのが毛利元就だったというわけだ。
にも関わらず元就は11カ国200万石を治めるまでに毛利家を成長させることに成功した。元就にどれほど高い政治力ががあったのかがよく窺える。国人衆あがりの戦国大名としては、多少誇張されての200万石だったとしても、その手腕はかなり高く評価することができる。ちなみに200万石という数字は太閤検地以前のものであるため、正確な数字ではなかったのかもしれない。もしかしたらもっと多かったかもしれないし、逆に少なかったのかもしれない。
元就は国人衆あがりの戦国大名として国を治める大変さがよくわかっていた。だからこそこれ以上版図を拡大することなく、現有領土を3人で力を合わせて守り抜いて欲しいと遺言を託したのだった。小早川隆景に関してはその遺言を最後まで守り抜こうとしたのだが、しかし関ヶ原の戦いが起こる少し前になると、毛利輝元が領土拡大に意欲を見せていく。だが結果的にはそれが仇となってしまい、関ヶ原後には自らの首を絞めることになってしまった。