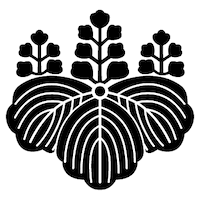
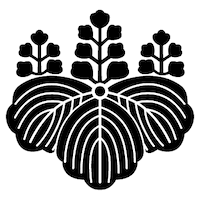
史実と事実に沿って戦国時代を書き記します。
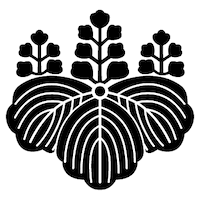

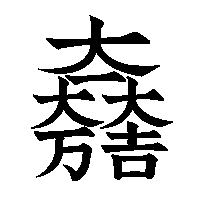
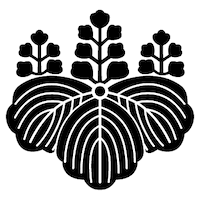



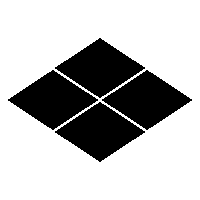


戦国武将たちがまず与えられる名前は幼名(ようみょう)だ。幼名とはその名の通り生まれてすぐ付けられる名前のことで、織田信長であれば幼少期は吉法師、真田信繁であれば弁丸と名乗っていた。13歳を過ぎると男子は元服していくのだが、元服をするまではこの幼名を名乗ることになる。
元服をすませると諱(いみな)と、烏帽子親(えぼしおや)によって仮名(けみょう)が与えられる。「真田」が苗字、「源次郎」が仮名、「信繁」が諱、ということになり、諱は時の権力者などから一字もらうことが多い。信繁の場合は武田信玄から一字もらった形だ。
官位を持っていない武将の場合、仮名で呼ばれることが一般的で、諱で呼ばれることはほとんどない。特に位の高い相手を諱で呼ぶことは失礼に当たり、「信長様」と呼ぶことはまずない。信長は晩年右大臣に就いていたのだが、その役職から信長は「右府(うふ)様」と呼ばれていた。
なお諱というのは元々は、生前の徳行によって死後に贈られる称号のことで、諡(おくりな)とも言われる。漢字も本来は「忌み名」と書くことから、相手を諱で呼ぶことはほとんどなかった。真田源次郎信繁は「源次郎」、竹中半兵衛重治であれば「半兵衛」、黒田官兵衛孝高であれば「官兵衛」と仮名で呼ばれていた。ちなみに信長の仮名は三郎だ。
例えば石田三成はテレビドラマなどでは「治部少(じぶのしょう)」や「治部殿」と官途(かんど)で呼ばれているが、やはり諱で呼ばれることはななく、官職が与えられる前は仮名である「佐吉」と呼ばれていた。
テレビドラマでは時々、諱で「信長様」「秀吉様」と呼ぶ場面が見られるが、実際にそう呼ばれることはなかった。ドラマの場合は視聴者にわかりやすいように、あえて諱で呼ばせているのだろう。だが大河ドラマなど、最近のドラマでは比較的官途が使われていることが多いように感じられる。例えば徳川家康のことも「内府(だいふ)殿」と呼ばせることが多い。
なお治部少(じぶのしょう)というのは明での読み方となる。日本語では「おさむるつかさ」と読むようで、戦国時代当時は役職を唐名(とうみょう)で読むことが一般的だった。現代に於いては、最高経営責任者のことをCEOと英語で呼ぶようなものだ。また、徳川家康のことを内府(ないふ)と呼んでいるドラマもあるが、これは恐らくは間違いだと思う。内府(ないふ)というのは明治憲法下での呼び方であり、戦国時代では内府(だいふ)と唐名で呼ぶのが正解だ。
羽柴秀吉が山崎の戦いで明智光秀を討ち、その経緯を記した軍記物(現代で言うところの歴史小説)を書かせた際、題名は『惟任退治記』だった。この頃の明智光秀は、惟任日向守光秀と名乗っていた。惟任とは天皇から与えられる氏(うじ)であり、源、平、藤原、橘、豊臣などと同じ部類のものとなる。主君信長を討った光秀のことさえも諱では呼ばず、氏で呼んでいることから、やはり当時は諱で呼ぶことが相当憚られていたのだろう。ちなみに光秀の仮名は十兵衛だった。
最後に付け加えておくと、この諱によって引き起こされた事件があった。方広寺鐘銘事件だ。この事件がきっかけで大坂冬の陣が勃発したわけだが、この時は豊臣方が鐘に「家康」と諱を使ったことを理由にし、家康は大坂城を攻める口実としている。