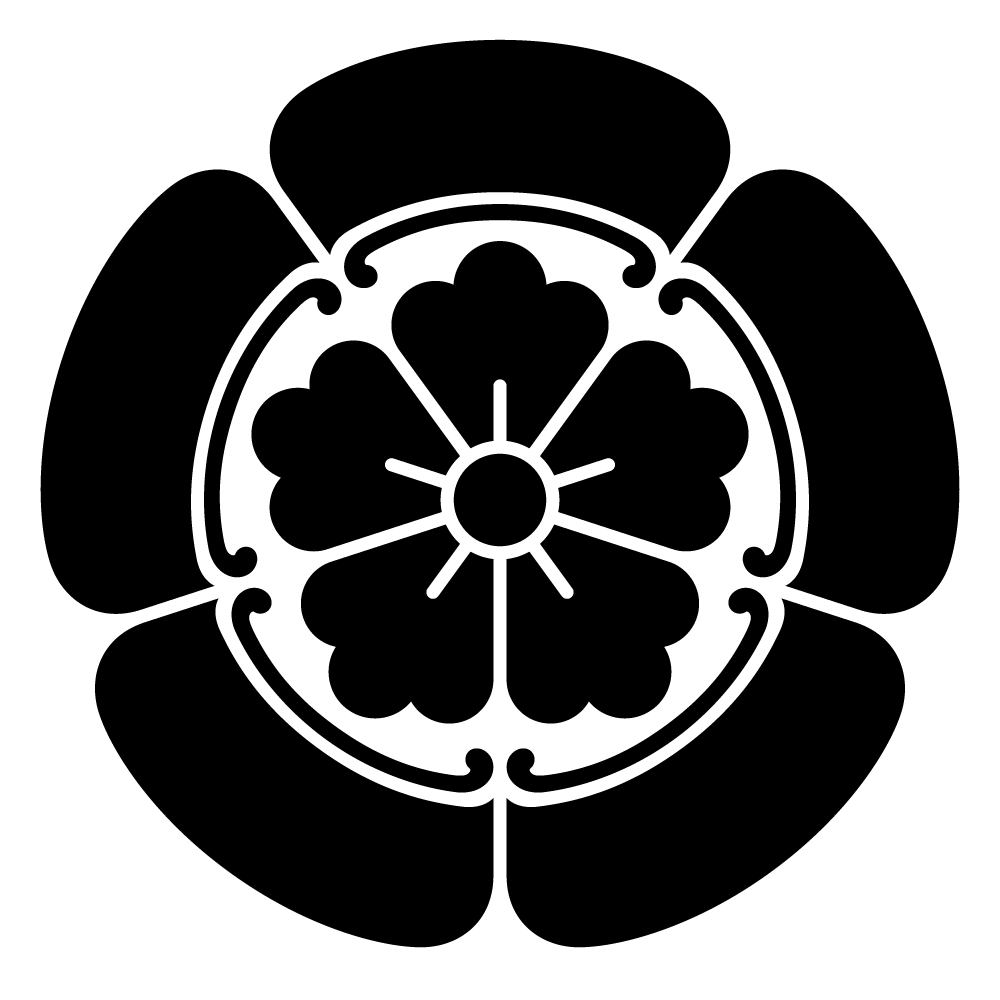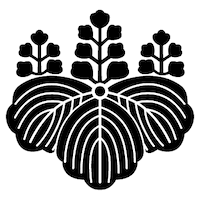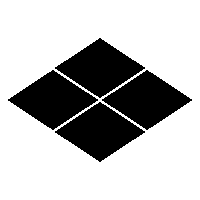惟任退治記現代語訳-戦国時代記編
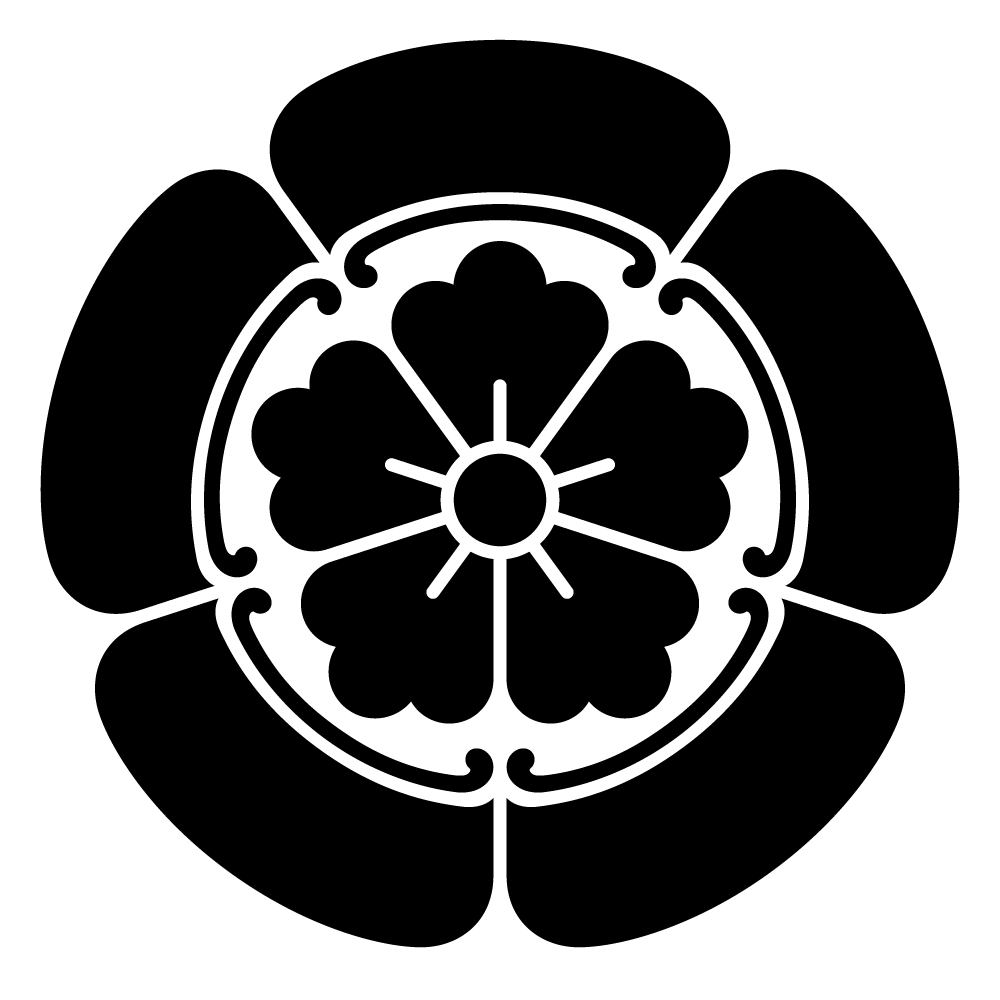
村井貞勝は本能寺の門外すぐの場所に住んでいた。本能寺での騒ぎを耳にして初めは喧嘩かと思い、それを鎮めようと着の身着の儘外に走り出て様子を見てみたがその騒ぎは喧嘩によるものではなく、本能寺が明智光秀の軍勢二万に取り囲まれている騒ぎの音だった。村井貞勝はどうにか本能寺の中に入ろうと色々試みたが適わず、織田信忠の陣所となっていた妙覚寺まで急いで走り事態を信忠に伝えた。
信忠はすぐにでも本能寺に馳せ参じ父と共に戦い、最後は父と共に腹を切ると家臣たちに話したが、明智軍の包囲が厳重であったため、翼でもなければ本能寺の中に入ることはできそうになかった。まさにこれこそ咫尺千里の裏切りとも言えるものだった。
※咫尺千里:すぐ近くなのにものすごく遠くに感じること
信忠は妙覚寺は戦をするには不向きであるため、他に近くで戦えて最後は自刃できる場はないかと家臣に尋ねると、村井貞勝は誠仁親王(正親町天皇の息子)がおいでの二条御所が良いと言い、信忠を二条御所まで案内した。すると誠仁親王は輿に乗って内裏にお移りになり、信忠は五百人の兵と共に御所に入った。
明智軍に遮られたことにより、二条御所に馳せ参じることができた信長の馬廻はわずかに一千騎ほどで、信忠のもとにいたのは弟の織田又十郎信次、村井春長父子三人、団平八景春、菅屋九右衛門父子、福富平左衛門、猪子兵助、下石彦右衛門、野々村三十郎幸久、赤沢七郎右衛門、斎藤新五、津田九郎次郎信治、佐々川兵庫、毛利新助、塙伝三郎、桑名吉蔵、水野九蔵、桜木伝七、伊丹新三、小山田弥太郎、小胯与吉、春日源八ら歴々の侍たちであり、彼らは死を覚悟し明智の軍勢が攻め入るのを待ち構えていた。
明智光秀は、主君織田信長が自害し本能寺に火がかけられたのを見ると安心し、織田家の家督を継いでいた信忠の居場所を尋ねた。すると信忠は二条御所に立て篭もっているとのことだった。それを聞いた光秀は兵を休ませることなく二条御所に急行した。しかし二条御所ではすでに死を覚悟した侍たちが大手門を開き、弓・鉄砲隊に前面に構えさせ、他の兵たちも思い思いに武器を手に取り前後を守っていた。
明智軍の先駆けが馬具も整えないまま攻めかかると、矢と鉄砲が次々と放たれてきた。それにたじろぐ明智軍を見ると、信忠の兵は内から一気に攻め出し、押しては退いて、退いては押すの攻防を数時間続けながら戦った。明智軍は武具をしっかりと締め直し、まだ戦える兵に代わるがわる攻めさせた。一方信忠の兵は素肌に帷子だけをまとった軽装で勇ましく善戦を見せたのだが、明智軍は長太刀や長槍を揃えて攻撃してきたため、こちらで五十人、あちらで百人と次々と討ち倒され、遂には御殿のすぐ近くまで攻め入ってきた。
信忠と信次兄弟は腹巻をまとい、百人ばかりの近習は具足をまとい戦った。そして信忠はその中でも一番に打ち出て、十七〜八人の敵兵を討ち取っていった。また、近習たちも果敢に攻め出す信忠に負けじと、刀で火花を散らしながら戦い、敵を方々に蹴散らしていった。
その際明智孫十郎、松生三右衛門、加成清次ら明智軍屈指の侍たち数百人が一気に斬りかかってきた。信忠はそれを見るとその中に飛び込み、これまで稽古してきた兵法、秘伝の術、英傑一太刀の奥義を繰り出し、次々と敵兵を薙ぎ倒していった。すると孫十郎、三右衛門、清次の首は信忠により次々と刎ね落とされていった。そして近習たちも力の限り太刀を振り続け、御所に攻め込んできた明智軍をことごとく討ち果たしていった。
もう何も思い残すことなく最期の戦を戦い切り、父信長と共に逝こうと二条御所の四方に火を放ち、御所の中心まで退くと十文字に腹を掻き切った。他の精鋭たちも熊や鹿の毛皮で作った敷物を並べ、その上で信忠を追うように腹を切り、皆一斉に炎に包まれていった。信長は四十九歳、信忠は二十六歳であり、悼み惜しむべしと民の誰しもが涙を流した。
ところで、明智光秀と同郷で美濃出身の松野平介一忠は、その夜は京の都の外にいた。そして夜襲の報せを耳にし駆けつけたが間に合わず、到着した時に本能寺での戦はすでに終わっており、信長もすでに自害したと聞くと、諦めて妙顕寺まで走り、追腹を切ろうと覚悟を決めた。その時斉藤利三が一忠を明智側に勧誘したが、一忠は信長に恩義があると言いそれを断り自刃した。一忠は元々は医者であり、文武両道の優秀な男だった。普段から歌道もたしなみ、侍になったのちも学問を怠ることをしなかった。そして以下がその一忠の辞世の句である。
そのきはに 消ゑ残る身の 浮雲も 終には同じ 道の山風
手握活人三尺劔、即今截斷尽乾坤
(手に我の命を助けた約90cmの刀を持ち、今まさに天と地を斬り断つ)
このような句を残して腹を切ると臓腑を引き出しながら朽ち果てた。まさにこの時代では他に類を見ない無双の働き振りだった。人々は一忠ん最期を聞くと涙を流し袂を濡らしたものだった。
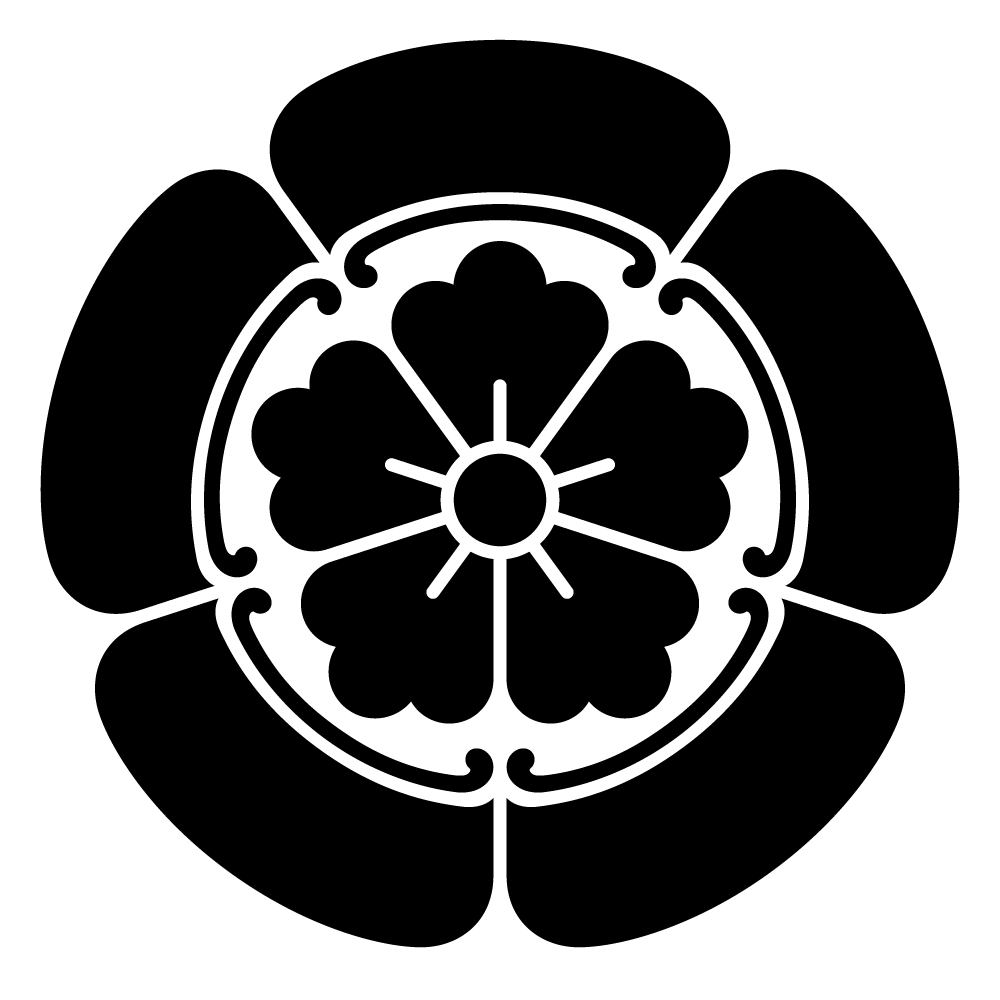
惟任光秀(明智光秀)は信長から秀吉救援の命令を受け二万以上の軍勢を揃えたものの、備中には行かず、密かに謀反を企んでいた。この謀反は決してその場の思い付きなどではなく、長年積もりに積もった信長への恨みにより、この時が好機であると決断したものだった。そして五月二十八日(本能寺の変は六月二日)、光秀は愛宕山で連歌会を催した。その時光秀が読んだ発句(会全体の最初の句)がこれだった。
時は今 雨が下しる 五月哉
(ときはいま あめがしたしる さつきかな)
今になって思うと、この句こそが謀反の兆しだった。しかしこの時誰がそんな光秀の企みに気付いただろうか。
天正十年六月一日、夜半から先の二万の軍勢を率いて居城である丹波亀山城を出立し、京都四条西洞院(きょうとしじょうにしのとういん)にある信長の宿所、本能寺に押し寄せた。信長は光秀が謀反を起こすなど夢にも思っておらず、その日も夜がまだ深まる前、信忠(信長の嫡男)といつものように仲良く語り合っていた。
ここ何年かを振り返ってみると、思い残すことがないほど満ち足りた四十代だったことを喜び、これからも末永くその栄光が続くようにと、村井貞勝をはじめ近習(主君のそばに仕えるもの)・小姓(主君のそばで雑用をする少年)に至るまで優しい言葉をかけてくださった。そうしているうちに夜も更けていったため、信忠は暇を乞い自らの宿所である妙覚寺へと帰っていった。
信長も寝所へと入っていくと、美女たちを集めてそばに侍(はべ)らせた。だが現実はそのような夢のようにはいかない。信長がそうしている間にも光秀は、明智秀満、明智勝兵衛(三沢秀次)、明智光忠、明智孫十郎、斎藤利三を大将とした軍勢を四方に分けて本能寺を取り囲んでいた。
夜明け間近、光秀の軍勢は壁を壊し、門や木戸を破り、一気に本能寺へと乱入していった。信長の命運ももはや尽きていたのだろう。近頃は戦もめっきり減っていたため、信長はほとんど護衛をつけてはいなかった。有力武将たちは毛利攻めのために西国に遠征していたり、北条などを警戒するために東国に置かれているのみで、京付近の護衛は手薄になっていた。
信長の三男である織田信孝も四国の長曾我部討伐の遠征で渡海するため、丹羽長秀、蜂谷頼隆を従え泉堺の津に留まっていた。その他の武将たちも毛利攻めの準備をするためそれぞれの国に戻っていたために、信長は手薄な警護のみで在京していたのだった。
たまたま京付近に滞在していた家臣もいたにはいたのだが、思い思いに都を楽しみ、信長の救援に駆け付けられる状態ではなかった。つまり信長の警護に当たっていたのは小姓百人程度でしかなかった。
信長は夜討ちの報せを受けて森蘭丸に問うと、彼は光秀が謀反を起こしたと告げた。恩を仇で返すということに前例がないわけではない。生きている者はいつかは死にゆく。これは道理であって今さら驚くようなことでもない。
信長は急いで弓を取ると縁側に出て向かってくる敵兵五、六人を射抜き、十文字の槍を手に何人かをなぎ倒し、門外まで追い、追い払った時にはいくつかの傷を負い、寺内へと引き返していった。
森蘭丸(森成利、本来は蘭丸ではなく乱丸。信長が男色だったと捏造するため、秀吉が男色を匂わせる「蘭」という漢字を使わせた)、森坊丸、森力丸の兄弟をはじめ、高橋虎松、大塚又一郎、菅屋角蔵(十四歳)、薄田金五郎(すすきだきんごろう)、落合小八郎らの小姓たちは、最期まで信長のそばを離れず付き従った。彼らは真っ先に駆け出し、名乗るや否や一歩も引かずに戦い続けたが、最後は全員が枕を並べて討ち死にをしていった。
彼らに続いたのは中尾源太郎、狩野又九郎、湯浅甚助(桶狭間の戦い活躍)、馬乗勝介(うまのりしょうすけ、厩から飛び出してきて戦ったらしい)、一雲斎針阿弥(いちうんさいしんあみ、奉行的立場の側近)ら七十から八十人だった。彼らも思い思いに戦いしばらくは防戦に努めたものの、二万の軍勢に攻められことごとく討たれていった。
信長は日ごろ寵愛していた美女たちを刺し殺し御殿に火をかけると、切腹をし果てていった。
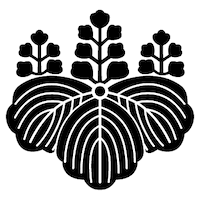
河屋城を落とすと、秀吉は備中高松城(岡山市・清水宗治が城主)に軍勢を集結させた。城の周囲を見渡すと三方が深い沼地になっており、人や馬が通れる場所はまったくなかった。そして残る一方は幾重にも大堀が構えらえており、ここは毛利家が何年もかけて普請(ふしん:築城に関する土木工事)してきた難攻不落の要塞だった。例え日本中の勢力を集めた大軍で攻めたとしても、落とせそうにはなかった。
そのため秀吉は熟考し、水攻めをすることにした。城の周囲2~3里(8~12km)に山のような堤を築き、堤の裏には木材を使って水をせき止めるための柵を作り、大河や小川の河上を辿って開鑿(かいさく:土地を切り開いて道路や運河を作ること)し、岩石を崩し、谷ノ口や水田の用水、溜水に至るまでことごとくせき止めたため、高松城の周囲はたちまち湖のようになってしまった。
そして新しく築いた堤の上に攻撃用の付城(つけじろ)をいくつか作り、さらには大きな船で連隊を組み、「乙の丸」という曲輪(城壁や堀などで仕切られた城の区画)に攻め込み、曲輪を隔てていた壁代わりの建物を次々と取り壊していった。それにより「甲の丸」という曲輪と一つに繋がってしまった。
敵兵は水深を見ながら竹や葦を糸で組み、板を並べて住まいを作ろうとした。その波に漂う陣小屋は、小舟のようにゆらゆらと揺れていた。それはまさに籠の中の鳥や、網の中の魚のような悲しい気分を味わっているようだった。
これとは別に秀吉は、1万少々の軍勢を城から5町10町(500m~1km)隔てて陣取らせ、後方の備えをさせた。すると毛利輝元、小早川隆景、吉川元春は、何とかこの高松城を救わねばと考えた。そして備中表(おもて)にて決死の覚悟で戦おうと、10ヵ国から8万余りの兵を集め、備中高山(こうざん:総社市の高山城)に続く釈迦が峰、不動岳に陣取った。彼らと秀吉との距離は1km程度しかなかったが、その間には大河があったため、すぐに攻め込むことはできず、数日の間は手をこまねいていた。
秀吉は毛利の大軍を攻めるかどうか決めかねていた。攻めれば打ち破る自信はあったが、中国地方の平定について信長に意見を伺ったところ、軽々しい戦はしないようにとのお達しが、使者とともに堀秀政、中川清秀、高山右近、池田元助(池田恒興の嫡男)らが加えられ遣わされた。
そして信長は信忠(信長の嫡男)を伴い京に入った。そして惟任日向守光秀(これとうひゅうがのかみ:明智光秀)を援軍として備中に送り、すぐに着陣し秀吉と相談しながら事に当たるようにと命じた。そしてその戦況によっては信長自らも出陣を厭わない旨をも伝えた。


惟任退治記全文掲載
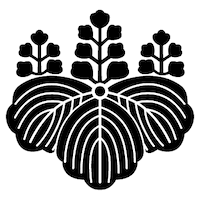
羽柴筑前守秀吉(はしば ちくぜんのかみ ひでよし)とその弟羽柴小一郎秀長は、天正6年に播磨の三木城主である別所長治を攻めて以来、信長から中国地方を制圧するための大将に任じられていた。まず備前(岡山県南東部)・美作(岡山県北東部)を守護していた宇喜多直家を服従させ、さらに播磨(兵庫県南西部)・但馬(兵庫県北部)・因幡(鳥取県東部)を加えた計5ヵ国による軍勢で、天正10年3月15日(1582年)、備前の冠城を攻撃した。
冠城に立てこもる毛利軍も守備を固くし奮戦していたが、秀吉は最初から、抵抗に遭い損害が出たとしても力攻めでこの城を落とし、力の差を毛利、そして味方5ヵ国の軍勢に見せつける腹づもりだった。
秀吉は先陣として杉原家次(秀吉の正室おねの叔父)、仙石権兵衛秀久、荒木重堅(もともとは荒木村重の家臣だったが、村重離反後は秀吉に仕え、のちに木下を名乗る)を送り込み、陣を敷かせた。彼らは水際から攻め入り、重要拠点を押さえていった。この功績に秀吉は満足し、彼らに馬や太刀を褒美として与えた。
実は冠城からは秀吉に対し幾度となく使者が送られていた。だが彼らの懇願を秀吉は受け入れることはせず、大軍で冠城を力攻めし、城内の者の首をことごとく切っていった。
冠城を落とすと秀吉は間髪入れずに河屋城(岡山市北区)を取り囲んだ。するとあまりの大軍に城を守っていた河屋氏(土豪)は恐れをなし、すぐに鎧兜を脱ぎ、毛利の援軍を待つことなく降伏した。これにより秀吉は河屋氏を助命し、追放するだけで終わらせた。


惟任退治記全文掲載
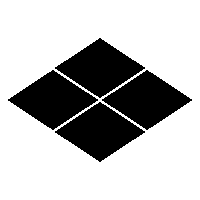
甲斐・信濃の国主武田勝頼率いる武田家は、織田家にとってはまさに長年の宿敵だった。このため織田信忠が信濃に出陣し、高遠城(現在の長野県伊那市)を取り囲んだ。高遠は勝頼の弟である仁科盛信(武田信玄の五男で高遠城主)と小山田昌成が領する土地だったが、川尻秀隆の調略が奏功し瞬く間に城兵たちを討ち破っていった。そしてその勢いのまま新府城(この時点での武田氏の本城)に攻め込んだ。
武田勝頼は織田の猛攻に耐え切れず敗北を喫し、天目山へと逃れていく。だが川尻秀隆と滝川一益も勝頼を追って山中に入り、幾度も戦闘を繰り広げる。その結果勝頼は完全に敗北し、武田勝頼、勝頼の嫡男武田信勝、武田信玄の弟の子武田信豊、武田信玄の弟武田信廉(のぶかど)をはじめとする武田一族はことごとく首をはねられた。
甲斐・信濃・駿河が平定されたという報告を受け、信長も信濃へ向かった。信長がこの三国を視察している際、北条を始めとする関東諸大名の多くが味方として信長のもとに駆け付けた。信長は長年富士山をこの目で見てみたいと思っていた。富士山は天竺(てんじく:インド)、震旦(しんたん:中国)、扶桑(ふそう:日本)三国の中で無双の名山と呼ばれていたためだ。
いま、その富士山を自らの領地に治めるという念願を達成し、そしてその目で拝むことができ、信長はたいそう喜んでいた。そして富士山を見物した後は三河・遠江の領主である徳川家康の居城、浜松城に滞在した。


惟任退治記全文掲載
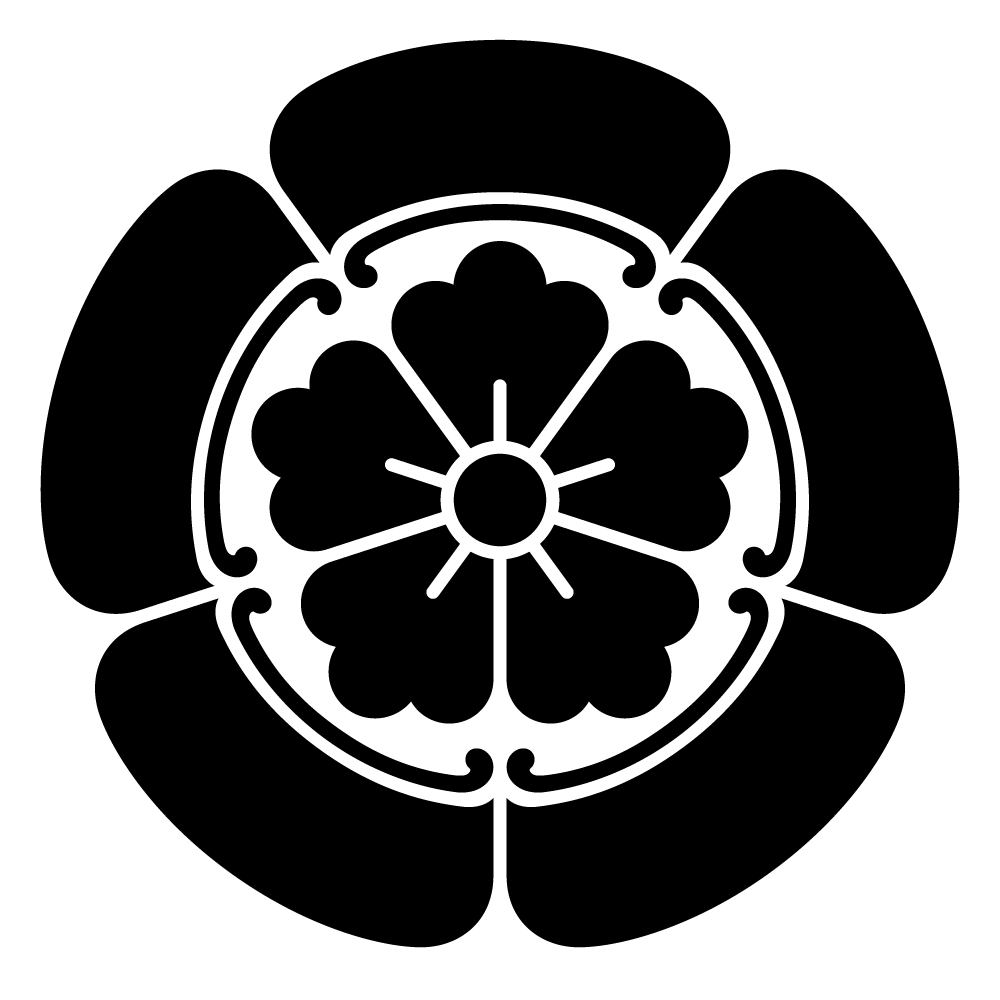
『惟任退治記』とは、天正10年(1582年)10月15日に行われた織田信長の葬儀の直後、織田信長がどのようにして明智光秀に討たれ、どのようにして羽柴秀吉が光秀を討ち信長の仇を取ったのかということを、秀吉が大村由己(おおむらゆうこ)という御伽衆に書かせた軍記物だと伝えられている。軍記物とは現代でいうところの歴史小説のようなもので、ノンフィクションではなく、フィクションも多分に含まれている。そのため歴史研究においては、ノンフィクションのみが記されていると思われる日記や書状などを一次資料と呼ぶのに対し、フィクションも含まれている軍記物は二次資料と呼ばれている。
ただ、軍記物といっても100%フィクションというわけではなく、史実通りのことが書かれていることが多いのは現代の歴史小説と同様だった。ただ、書いた者や書かせた者の主観が含まれることが多いため、事実が捻じ曲げられていたり、物語そのものが創造されていることも多い。だがそのあたりを踏まえて読んでいくと、軍記物は歴史ファンにとっては非常に楽しめる読み物だと言える。今回、戦国時代記では『惟任退治記』という、12編からなると言われている『天正記』の1編を、現代語訳どころか、現代小説風に書いてみたいと思う。言葉遣いなどはまさに現代小説風になっていくが、書かれている内容や意味は、原文通りにし、筆者の脚色等は一切排除した内容にしていきたい。
惟任退治記(1)皇居が移動して来たかのように賑わう安土城
世間というものは栄えたり衰えたりということを繰り返すことによって成り立っている。南山(なんざん:高野山のこと)の春の花は咲き誇ったかと思えば逆風により散っていき、東嶺(とうれい:京都の東山のこと)に美しい秋月が見えたかと思えば厚い雲がそれを覆い隠してしまう。そして力強く根を張る樹齢長き松の木でさえも伐採されることを自ら避けることはできず、寿命万年といわれる亀でさえもいつかは死んでしまう。また、朝顔の花に落ちる露や、荘子が見たという自ら蝶となり花の上で100年遊んだという夢の目覚めのように、世の栄華というのは実に儚い。
亡くなった後に太政大臣に叙せられた織田信長公は、長きにわたり日ノ本のリーダーとして国家を主導してきたが、その亡くなる前、信長公は近江の安土山に城郭を築いた。大きな石で土台が作られた建物の屋根が連なり、天守閣は天まで届きそうなほどに高くそび、それら煌びやかな建物が鏡面のような琵琶湖の水面に映り、その美しさは言葉で表すことなどできない。
恐れ多くも正親町天皇をはじめとし、朝廷に仕える公家たちも身分の上下問わず、毎日のように信長宛てに連絡を入れ、続々と安土城に集まってきた。その様子はまるで皇居が安土城に移動して来たかのようだった。三管領と呼ばれた室町幕府の名家、斯波家、細川家、畠山家の人間で、信長公を崇拝しない者は誰一人としていない。そして信長公は彼らと、100羽の鷹を集めて鷹狩りに出かけたり、千とも万とも言われた数の馬を集めて馬揃え(軍事力を誇示し諸大名に力を見せつけたり、軍の士気を高めるために行われた一大行事)を行った。
朝廷の者たちは、私欲のない清らかな政治を志し、曲がったことは正すと言いながらも、夜になると奥に控えていた3000人の美女たちを欲しいままにした。正しいことを行うと言いつつ毎夜催された宴は、いくら楽しんでも尽きることがなかった。唐(とう:中国の王朝名)の玄宗皇帝が所有していた温泉付きの驪山宮(りざんきゅう)や、洛陽(らくよう:中国河南省の非常に栄えていた都市)の上陽殿(宮殿)の娯楽でさえも、安土城の物ほどではなかっただろう。


惟任退治記全文掲載