戦国大名になるための四つの方法
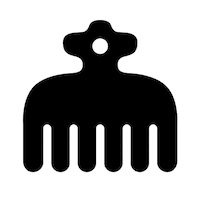
戦国時代に活躍した者たちとして、まず挙げられるのが大名たちです。戦国大名として有名なのは織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、毛利元就、今川義元、武田信玄、上杉謙信などなど、挙げ始めると実に切りがないほどです。
では大名とは何を以って大名と呼ばれたのかと言うと、一般的には二郡以上支配する者が大名と呼ばれたようです。戦国時代は今で言う都道府県を「郡」という単位で分割していたのですが、その郡を二郡以上支配できるようになると戦国大名と呼ばれるようになります。
例えば元々は国人衆の一つだった毛利氏ですが、毛利元就の才覚によって毛利家は国人衆としてどんどん力を付けていきました。その結果二郡以上支配するに至り、さらには他の国人衆を従属化させることで一国人衆から戦国大名へとのし上がっていきました。
ちなみに鎌倉時代を経て、戦国大名へとなっていく方法は主に四つです。一つ目は鎌倉時代より将軍家から守護大名に任命されており、それがそのまま戦国大名になったパターンです。今川氏、武田氏、島津氏がこのパターンですね。ちなみに鎌倉時代には本来守護大名は在京している必要がありましたが、戦国時代になると在国と言って京にはおらず、それぞれの国にいながら
二つ目のパターンは守護代から戦国大名に成り上がるパターンです。織田氏、上杉氏、朝倉氏がこれに当たります。守護代というのは、守護大名が在京している際にその国の政を担う、言わば代理監督のような存在でした。尾張の守護大名は斯波氏でしたが、尾張の守護代を務めた織田氏がどんどん財力を付けていき、それに伴い軍も強化され、守護大名であった斯波氏の力を上回ってしまったことで斯波氏は淘汰されていき、自然と織田氏が斯波氏と代わるようにして尾張の戦国大名となっていきました。
三つ目のパターンは国人衆や地侍から成り上がっていく、上述の毛利氏のパターンですね。そして四つ目は下剋上です。例えばマムシと呼ばれた斎藤道三は主家である土岐氏を攻め、土岐氏を尾張に追放することによって美濃国を乗っとりました。以上が戦国大名になる主な四つのパターンです。
守護大名と戦国大名の違い
そして鎌倉時代から続く守護大名と戦国大名は何が違うかと言うと、守護大名は常に幕府の権威に依存していましたが、戦国大名は独自に国力を付けていきました。例えば元々は守護大名である今川氏などは、鎌倉時代にはあくまでも幕府から駿河国などを預かっているという立場で、幕府の意向に沿わない行動を取ることはできませんでした。
一方幕府の力が弱体化して来た戦国時代では、幕府の権威は尊重しながらも、大名たちは幕府に依存することはありませんでした。例えば織田信長が将軍足利義昭の権威を天下取りの道具として使っていた事例などは、まさにそれを象徴しています。
また、上述の通り守護大名は在京している必要がありました。つまり京にいる将軍のお側に常にいなければならなかったわけです。しかし戦国大名は、かつては守護大名だった武田氏も今川氏も京を離れ、それぞれの国に居を構えていました。
そして法律に関しても、戦国大名は自らの領地で勝手に法律を策定し、独自のルールで国を支配して行きましたが、守護大名の場合は室町幕府が定めた通りにそれぞれ任された国を支配し、勝手に独自のルールを作ることは許されてませんでした。このあたりが戦国時代以前の守護大名と、戦国大名の大きな違いだと言えます。
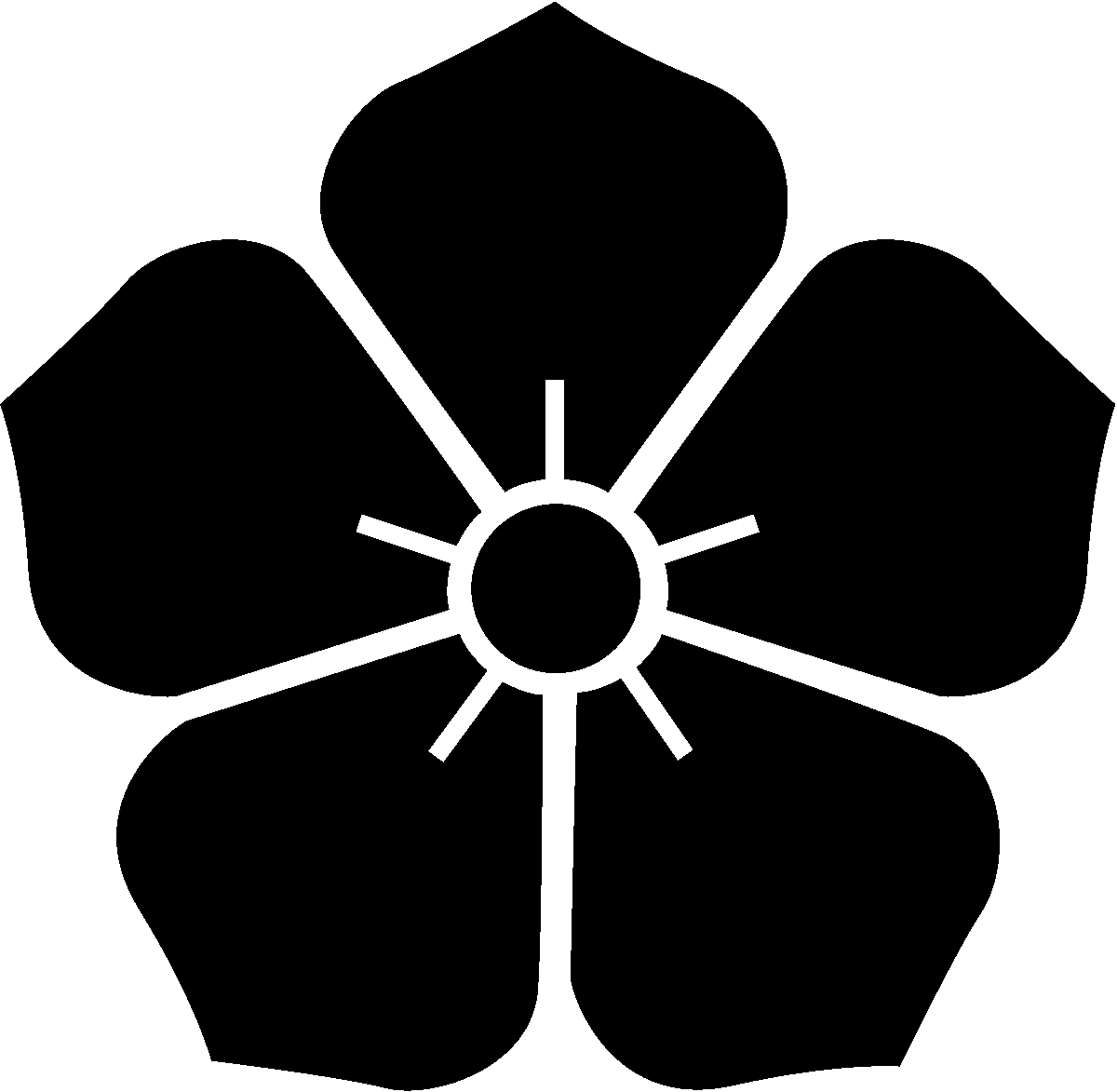

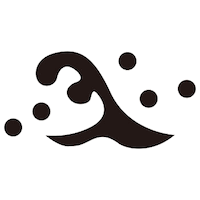 斎藤道三は11歳で京の妙覚寺で僧侶となり、法蓮房と名乗った。だがその後還俗して松波庄五郎と名乗り、油屋だった奈良屋又兵衛の娘を娶り、山崎屋という称号で油売り商人となった。しかもただの商人ではなく、一文銭の穴を通して油を注ぎ、一滴でも溢れたら代金は取らないという手法で売り歩いていた。これが美濃で評判となり、庄五郎は財を成していく。
斎藤道三は11歳で京の妙覚寺で僧侶となり、法蓮房と名乗った。だがその後還俗して松波庄五郎と名乗り、油屋だった奈良屋又兵衛の娘を娶り、山崎屋という称号で油売り商人となった。しかもただの商人ではなく、一文銭の穴を通して油を注ぎ、一滴でも溢れたら代金は取らないという手法で売り歩いていた。これが美濃で評判となり、庄五郎は財を成していく。 本能寺の変が起こる少し以前、一説では2〜3年前とも言われているが、織田家臣団の心は信長から少しずつ離れていこうとしていた。怒涛の1570年代は指揮官としての信長に誰もが付いて行こうとしていたが、信長があることを口にし出すと、家臣団の心配はどんどん膨らんでいったようだ。
本能寺の変が起こる少し以前、一説では2〜3年前とも言われているが、織田家臣団の心は信長から少しずつ離れていこうとしていた。怒涛の1570年代は指揮官としての信長に誰もが付いて行こうとしていたが、信長があることを口にし出すと、家臣団の心配はどんどん膨らんでいったようだ。