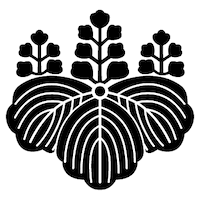鉄砲隊の割合が多かった伊達隊の弱点と、それを利用して戦った真田幸村

慶長20年(1615年)5月6日、誉田(こんだ)の戦いで真田幸村(信繁)と伊達政宗は対峙した。誉田の戦いとは大坂夏の陣に於ける一戦で、誉田陵(こんだりょう・応神天皇が埋葬された古墳)周辺で繰り広げられた戦いのことだ。伊達政宗からすると道明寺の戦いで後藤又兵衛と戦った直後の真田隊との遭遇だった。道明寺の戦いでは伊達の鉄砲隊の前に又兵衛が壮絶な討ち死にを果たしている。
忍びからの情報で、伊達鉄砲隊の威力の凄まじさは幸村の耳にも入っていた。2800の後藤隊を壊滅させた1万の伊達隊はほとんど減っていない。まともに対峙をすれば3000の真田隊に勝ち目はなかった。この時の伊達隊は三分の一が鉄砲隊で、実はこれが強みであると同時に、一つの弱点にもなっていた。
火縄銃を連続して撃てるのは当時は最大でも20発程度だったらしく、それだけ打つと筒内に煤が溜まり、一度手入れをしなければ暴発の危険があった。幸村は、後藤隊と戦った際に伊達隊はすでにある程度鉄砲を消耗していたことを耳にしていた。そのため幸村は伊達隊にどんどん鉄砲を撃たせ、鉄砲を使えなくなるまで時間稼ぎをしたのだった。
鉄砲隊が主力だった伊達隊だけに、鉄砲が使えなくなると戦力が一気に低下してしまった。幸村にとっては敵将伊達政宗を討ち取る好機となった。だが幸村は後退する伊達隊を深追いすることはしなかった。その理由は、幸村が狙っていたのは徳川家康の首だけだったからだと伝えられている。だがそれ以上に、幸村と政宗の間に密約があった可能性があるのだ。
密約を交わしていた可能性がある真田幸村と伊達政宗
実は大坂夏の陣、徳川方として参戦していた伊達政宗は豊臣方への内通が疑われており、逆に豊臣方として戦っていた真田幸村は徳川への内通を疑われていた。その理由はかつて政宗に仕えていた家臣が出奔し、豊臣秀頼に仕えるようになっていたためだと伝えられている。しかもその家臣は一時は幸村の配下にも置かれていたようで、これにより幸村と政宗はいつでも連絡を取り合える状況にあった。この状況によりふたりは内通を疑われていたらしい。
いくつかの資料を読んでいると幸村と政宗は、家康の首を狙う密約を交わしていた可能性があるようだ。そのために誉田の戦いで政宗は真田隊を攻め切らず、幸村も後退した伊達隊を深追いすることはしなかった。何らかの密約があったからこそ、ふたりは本格的にぶつかり合うことを避けた可能性は否めない。
真田隊を中心にして豊臣方も善戦を繰り広げた。だが八尾・若江にて豊臣勢が壊滅させられたため、誉田で戦っていた豊臣勢は大阪城への撤退を余儀なくされる。この時に殿(しんがり)を務めたのは真田隊だったわけだが、全滅させられる可能性が高い殿であるにもかかわらず、伊達隊は真田隊を逆に追うことはしなかった。本来であれば殿隊は敵に背を向けながら戦うため、追う側とすれば簡単に壊滅させることができる。だが政宗はそうはしなかった。
真田幸村は大阪城に戻ると、次男と4人の娘たちを政宗の元へと送り届けた。そして実際政宗は幸村の子を引き取り保護している。ふたりの間に密約がなければ、このようなやり取りが行われることもなかったはずだ。どんな内容だったにせよ、幸村と政宗の間に何らかの密約があったことは、やはり間違いないのではないだろうか。ではその密約の内容とは?戦国時代に同盟を結ぶ理由は二つしかない。お互いの利害の一致と、家を守るためだ。
父昌幸の代から天敵だった徳川家康と、天下取りを狙った伊達政宗
真田幸村は父昌幸の代から天敵であった徳川家康を討ち、自らの名を後世に残すことを目的としこの戦いに挑んでいた。一方伊達政宗は未だ野心を捨て切れず、隙あらばと天下を虎視眈々と狙っていた。つまりこの戦いで家康が敗れれば、両者ともに大きな利益があったというわけだ。
いくつかの資料、書籍でも書かれているように、ふたりはきっと家康を討つための密約を結び、そしてそれが上手くいかなかった時の手筈まで整えていたのだろう。だからこそこの大戦のさなか、幸村は5人の子どもたちをすんなりと政宗の元へ送り届けることができた。
だがこの大戦に関する作戦はまったく上手くいかなかった。豊臣方は所詮は浪人の寄せ集め集団であり、しかもその頂点に立っていた司令官は戦に関しては素人同然の淀殿だった。このような烏合の衆が戦上手の徳川軍に勝てる可能性など最初からなかったのだ。だからこそ幸村や又兵衛が善戦を見せても、別の場所ではすぐに豊臣勢は壊滅させられてしまい、幸村は大阪城に戻るしかなくなってしまった。つまり例えで幸村と政宗の共闘で家康を討つという作戦があったとしても、幸村が大阪城に戻らなければならなくなったこの時点でその作戦は破綻していたことになる。
伊達政宗のお陰で最後まで家康を悩ませ続けた真田幸村
先にも述べたように殿を務めた幸村を、政宗は追撃しなかった。政宗の娘婿である松平忠輝は、政宗に加勢し真田を追撃すると申し出たようだが、政宗はそれを断っている。もしかしたら命を落とす可能性が高い殿を務める幸村を、無事大阪城に戻すために政宗はあえて加勢を断ったのかもしれない。だが今となってはその真実は誰にも分からない。
大坂夏の陣では、徳川方は必ずしも一致団結していたわけではなかった。家康のやり方が気に入らない武将も多く存在しており、この戦いでも豊臣方に内通する機会を窺っていた武将も多かったと言う。だが豊臣方が想像以上に脆く崩れてしまったために、将たちは寝返る機会を失ってしまった。
豊臣方は大阪城まで撤退を強いられる状況になってしまったわけだが、前年の大阪冬の陣とはわけが違った。大阪城の防御は大坂冬の陣の停戦協定により根こそぎ取り壊されており、城の防御能力はないに等しかった。冬の陣で徳川方を苦しめた真田丸の存在も、この時にはもはや過去の話となっていた。
慶長20年(1615年)5月7日、つまり幸村と政宗が対峙した翌日、天王寺の戦いにて幸村は家康本隊を猛攻するも、3000の軍勢では徳川の大軍の前にすぐに力を失ってしまった。この時の真田軍の猛攻にはさすがの家康も死を覚悟したと伝えられている。真田幸村は最後の最後まで家康を苦しませた。かつては上田合戦で、前年は真田丸で、そして大坂夏の陣では天王寺の戦いでまた。
しかし数で圧倒された真田隊は善戦を見せるも松平忠直の部隊によってすぐに壊滅させられてしまい、幸村はそこで壮絶な討ち死にを果たしている。天王寺の戦いで力尽きるまで刀を振るい続けた幸村だが、それもやはり子どもたちが政宗によって保護されたからこそ、心置きなく戦えた結果だったのではないだろうか。
真田幸村のために口を閉し続けた伊達政宗
大阪冬の陣、夏の陣以前より真田家は徳川家の天敵であり、一方の伊達家は徳川に従属していた。つまり幸村と政宗は立場上では完全なる敵同士だった。だが同じ年齢であるふたりは、何かを切っ掛けにしお互いに興味を持ち、人知れず友情を育んでいたのかもしれない。
それが幸村の死後、政宗の口から語られることはなかったわけだがそれは当然だ。敵である幸村と密約をしていたことが公になれば、政宗もただでは済まされない。家康によって切腹を命じられたかもしれないし、伊達征伐軍を奥州に送られていたかもしれない。だからこそ政宗は固く口を閉ざしたわけだが、閉ざしたからこそ幸村との間に何らかの密約があったと想像する方が自然だとは言えないだろうか。
その真実は今となっては誰にも分からないわけだが、ふたりの英傑がこうして繋がっていたと考えることは、歴史好きにとっては果てしなく大きな浪漫とは言えないだろうか。