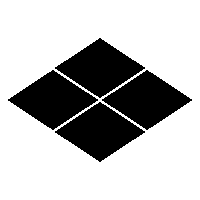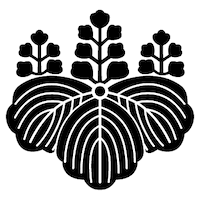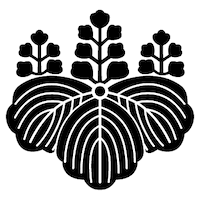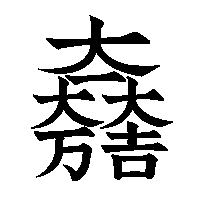天正6年(1578年)、荒木村重は羽柴秀吉の
三木城攻め に加わっていた。だがその10月、突如として村重は主君織田信長に反旗を翻し摂津有岡城に籠城してしまう。なぜ村重が信長を裏切ったのかは諸説あるが、ハッキリとした理由はわかっていない。一般的には信長の苛烈な性格に不安を抱き、毛利の後ろ盾てを得たことで謀反を起こしたとされている。
同じ頃、黒田官兵衛は秀吉の与力として播州(播磨)の案内役を買って出ていた。この頃の官兵衛はまだ小寺政職に仕えており、小寺姓を名乗っていた。官兵衛の進言により主君小寺政職は織田への従属を決めていたのだが、この時人質として秀吉のもとに送られたのは官兵衛の子、松寿丸だった。後の黒田長政だ。
村重の謀反を知ると、官兵衛は村重を説得するために有岡城に単身乗り込んだ。だがその官兵衛がいつまで経っても戻って来ない。その間にも村重は毛利と連携を取り、一時は織田側に靡いていた播州の国衆たちが毛利に付くように状況を変えようとしていた。これに怒りを露わにしたのが信長だった。信長はこの時、知将官兵衛が裏切り、荒木村重に知恵を貸していると判断した。だからこそ音沙汰もなく官兵衛が有岡城から戻って来ないのだ、と。
通常であれば使者は役目を果たすとその後すぐに戻るか、切り捨てられるかのどちらかだ。戦国時代に於いて使者を切り捨てるというのは宣戦布告を意味していた。だが官兵衛の場合はそのどちらでもない。だとすれば、一般的に考えれば官兵衛が村重側に付いたと判断することができる。
信長は秀吉に対し、人質であった松寿丸を切り捨てるよう命じた。当然と言えば当然である。人質とはそのための存在であり、官兵衛が裏切ったと判断されたならば、その人質を殺すのが戦国時代の当たり前のやり方だ。だが松寿丸はまだ9歳と幼かった。秀吉は居城である長浜城で正室のおねに松寿丸を預けていた。そして子に恵まれなかったおねは、我が子のように松寿丸を可愛がっていた。
秀吉もおねがどれだけ松寿丸を可愛がっているのかをよく知っていた。だからこそ信長の松寿丸処刑の命令をおねに伝えるのがあまりにも心苦しかった。そしてそんな秀吉の苦悩を、竹中半兵衛がそばで見守っていた。
その半兵衛が自ら松寿丸の処刑を買って出た。松寿丸を長浜城から自らの本拠、美濃菩提山城へと連れて行った。そして信長にはその後すぐ、松寿丸が処刑されたことが伝えられた。秀吉もおねも大層悲しんだことだろう。例え官兵衛が裏切り者だったとしても、特におねには松寿丸をこのまま我が子として育てたい気持ちがあったはずだ。だが主君信長の命に背くわけにはいかない。だからこそ断腸の思いで、半兵衛に松寿丸の処刑を任せるより他なかったのである。
官兵衛が有岡城に入ってからちょうど1年が過ぎた天正7年10月19日、荒木村重が篭る有岡城はついに落城した。しかもその形が酷く、村重が一族や家臣を残して逃亡するというものだった。そのため一族たちは女子供を含め、全員が処刑されるという最悪の結果になってしまう。
有岡城が陥落した際、狭く汚い土牢に一人の男が幽閉されていた。脚は真っ直ぐ伸びなくなっており、顔には痣ができている。この人物こそが小寺官兵衛であり、官兵衛は織田方を裏切ったのではなく、村重に幽閉されていただけだったのだ。村重には自らの味方に付くよう逆に説得されたようだが、官兵衛は決して織田を裏切ることはしなかった。この時官兵衛を土牢から救出したのは官兵衛の側近、栗山善助だった。
官兵衛は無事に救出され姫路に戻ることができた。だが官兵衛の帰りを待っていたのは、松寿丸が信長の命により処刑されたという報らせだった。官兵衛は嘆き悲しみ、まるで生きて戻った心地がしなかった。
だがその時、別の報らせが官兵衛のもとに届けられた。官兵衛が幽閉されている間に結核により他界していた竹中半兵衛の家の者からの報らせだった。官兵衛は当初半兵衛のことを慕っていたわけだが、しかし半兵衛が松寿丸の処刑を買って出たと聞き、さぞ落胆したことだろう。
竹中家からの報らせはきっと、その詫びだと思ったのかもしれない。だが真実はそうではなかった。半兵衛は処刑を買って出て、松寿丸を長浜城から菩提山城へと連れて行った。その後は半兵衛の家臣である不破矢足の屋敷に松寿丸は置かれた。
事実はたったそれだけだった。
半兵衛は、官兵衛が裏切っていないことを確信していたのだった。だからこそ自ら松寿丸を引き取り、処刑をしたと嘘の報告を行っていた。その報告に信長も満足していた。
信長の命は松寿丸を処刑することだった。だが半兵衛はその命に完全に背いた。なぜそんなことができたのか?半兵衛は自らの死期が近いことを良くわかっていた。半兵衛が自ら処刑役を買って出て、その結果信長の命に背いたとしても、もう半兵衛はこの世にはおらず、さすがの信長であっても死者を処分することはできない。半兵衛はそこまで考えて松寿丸を匿ったのだった。
官兵衛は心の底から半兵衛に対し感謝の意を示した。以降黒田家では竹中家の石餅(こくもち)の家紋を用い、半兵衛の子重門が元服した際には烏帽子親を務めている。
竹中半兵衛という人物は知略に長けた名軍師であったわけだが、最期は自分の死まで利用してしまった。そして死の間際には黒田父子を気遣う手紙まで残している。生前は官兵衛に対し時に冷たく、時に厳しく接した半兵衛であったが、その厳しさもすべて官兵衛のことを考えてのことだった。なぜなら自身亡き後、秀吉を支える軍師は官兵衛しかいないと考えていたからだ。
半兵衛と官兵衛の友情は、親の代だけで途切れることはなかった。半兵衛が他界した21年後に起こった関ヶ原の戦いでは、官兵衛の息子長政と、半兵衛の息子重門が隣り合って陣を敷くことになる。恐らく長政自身、半兵衛によって命を救われた恩を生涯忘れることがなかったのだろう。
<A rel="nofollow" HREF="http://ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&ServiceVersion=20070822&MarketPlace=JP&ID=V20070822%2FJP%2Fsawyer24-22%2F8010%2Fc6328fee-614b-4535-ae83-43d630e87f15&Operation=NoScript">Amazon.co.jp ウィジェット</A>