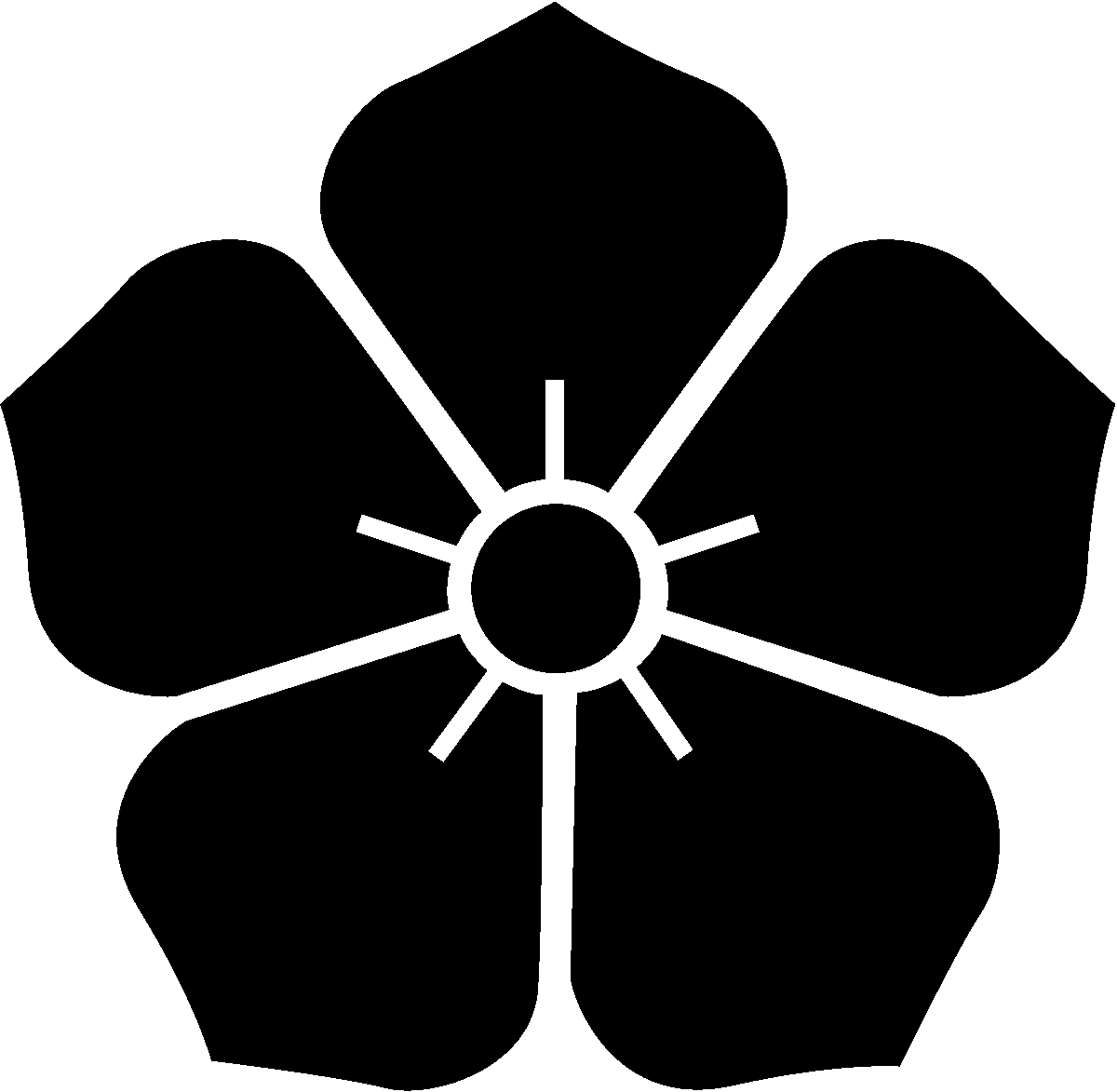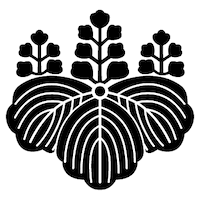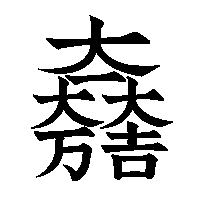年配に多い豊臣秀吉信奉者と、若者に人気の真田幸村
2016年NHK大河ドラマ『真田丸』の主人公としても注目されていた人物、真田信繁こと通称幸村。真田家は大名と呼ぶことはできない土豪出身の一族であり、常に時の有力大名に臣従することにより家を守ってきた。信長、秀吉、家康のように天下を動かしたわけではなく、歴史を動かすような特別大きな武功を挙げたわけでもない。それなのに真田幸村という人物は、今なお歴史ファンから愛された存在で居続けている。
筆者の個人的感想を言わせてもらえるなら、第二次大戦を経験している年代は特に豊臣秀吉が好きな方が多い印象がある。特に中国との戦争を体験していたり、それをよく知る世代の方は秀吉を尊敬しているという方が多い。これには理由があり、かつての大日本帝国軍が中国に侵攻した際、日本政府は豊臣秀吉を英雄として担ぎ上げていた。その理由は戦国時代に秀吉が朝鮮に侵攻していたためだ。当時の日本政府は秀吉を祭り上げ、中国への侵攻を正当化しようとしていたのだ。いわゆるプロバガンダだ。
その影響からか、年配の方に秀吉を尊敬している方が多いように感じられる。だがそれよりも若い世代となると、義に厚く、散り樣が見事だった武将の人気が高まってくる。その中でも一番人気がある人物のひとりが真田幸村だ。
父とは逆に義を貫き散っていった真田幸村
真田幸村の父昌幸は、謀略を得意とする知将だった。謀(はかりごと)が何よりも得意で、真田家を守るためであれば義など二の次だった。事実昌幸は秀吉から「表裏非興の者」と呼ばれ、仕える相手をその時々の都合により目まぐるしく変えていくことを揶揄されている。だが昌幸はそんなことお構いなしとばかりに、真田の家を守ることだけに注力していく。
一方の幸村は義に厚い人物として知られている。慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では、大坂城で最も守備が弱いとされていた南側の守りを受け持ち、かの有名な真田丸という丸馬出(まるうまだし/城の出入り口外側に作られた半円状をした、守備用の土塁)で徳川勢を大いに苦しめた。
この時の豊臣方は家康に対し疑心も持っていたり、豊臣家にかつて仕えていた浪人が中心で、10万という大軍だったと伝えられているが、しかし団結していたかといえば決してそんなことはなかった。まさに寄せ集め集団で、戦術さえもまともに話し合えないような状況だった。それでも幸村は豊臣への恩顧があったため、浪人の身でありながら豊臣勢として大坂城に駆けつけた。
そして慶長20年の大坂夏の陣では、豊臣方敗色濃厚という状況で豊臣方を見限る武将も多かった中、幸村は最期まで豊臣勢として戦い続けた。3,000の幸村勢は、1万の大軍を率いる伊達政宗の侵攻を防ぐなど奮闘し、さらには家康の本陣に肉薄する猛攻を見せるも、しかし真田軍に続く豊臣方の味方がおらず、最後にはとうとう徳川方の大軍の前に力尽きてしまった。
このように義を貫き通し、最期は桜のように見事な散り樣を見せた幸村の姿が、戦国ファンの心を惹きつけてやまないのであろう。戦国時代記では、これから真田幸村の生き様を深く掘り下げていきたいと思う。
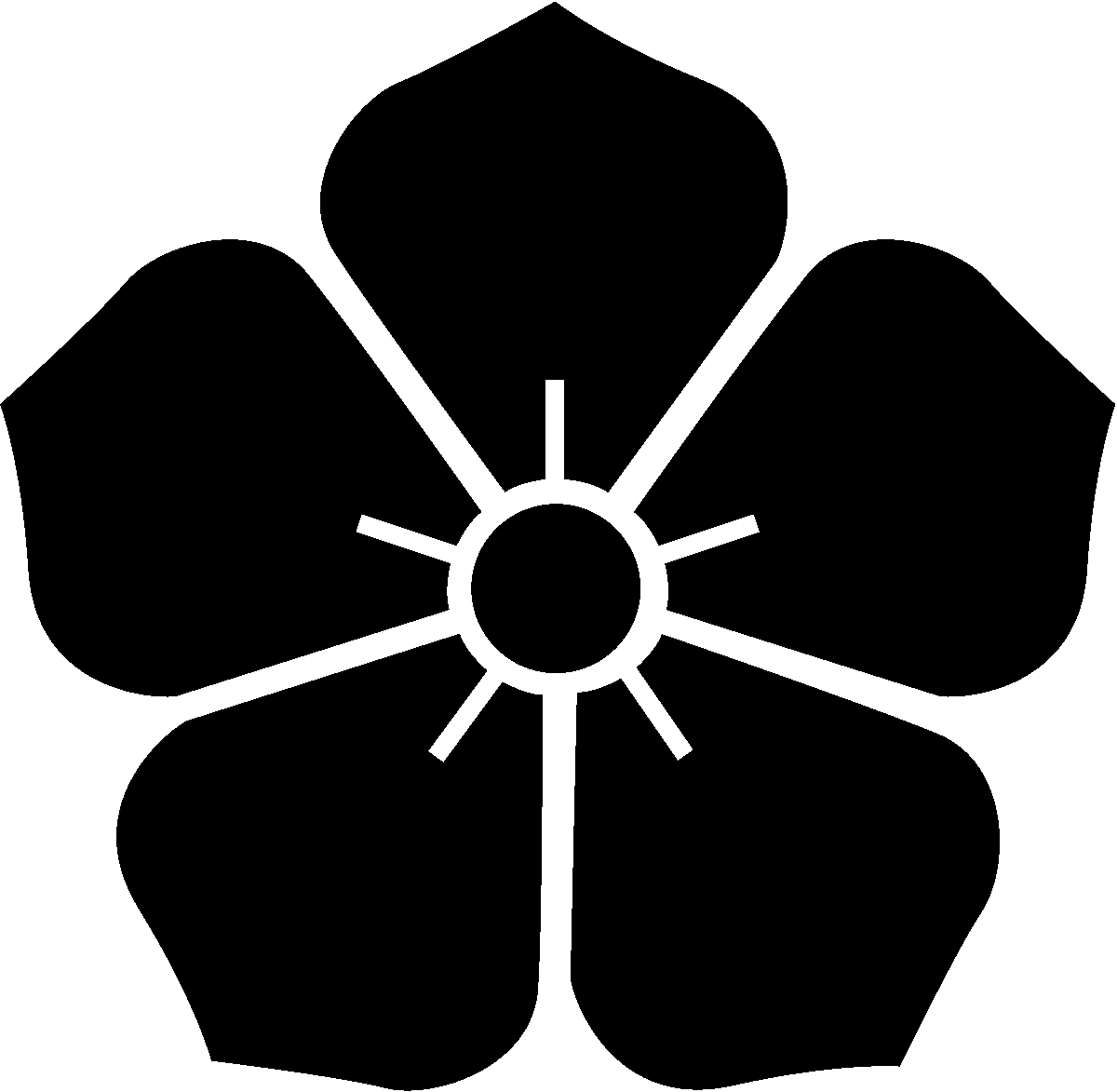
明智光秀の正室の名は煕子(ひろこ)と伝えられているが、この名前は正確に伝えられてきた名前ではなく、『氷点』などで知られる故三浦綾子さんが書かれた『細川ガラシャ夫人』という1975年に発表された小説以来、煕子という名で周知されていったようだ。それ以前はお牧の方や、伏屋姫と呼ばれていたようだが、これらに関しても正確な名であるという資料は残されていない。ただはっきりしているのは、妻木範煕の娘ということだけで、三浦綾子さんはこの父親の名から煕子と設定されたようだ。
幼馴染みだった明智光秀と煕子
光秀が生まれた当時の明智家は決して大きな力は持ち合わせておらず、美濃の小土豪に過ぎなかった。光秀自身も明智家の居館で生まれることはなかったようで、高木家の居城だった美濃の多羅城で生まれている。そして幼少期は妻木家の庇護を受けながら成長したようだ。だが幼少期の彦太郎ことのちの明智光秀は周囲からの評価は非常に高く、斎藤道三をして「万人の将となる人相」をしていたと言う。
そのようなこともあり彦太郎は妻木家からある程度安定した生活を送れるだけの庇護を受けながら育ち、自然な流れとして、元服した明智十兵衛光秀は幼馴染みでもあった妻木範煕の娘、煕子(便宜上そう呼ぶことにする)を娶った。弘治2年(1556年)に斎藤義龍によって明智城を落とされ越前に落ちた際煕子は身籠っていたというから、二人の婚姻は少なくとも1556年以前ということになるわけだが、正確な日付を知ることのできる資料はまだ発見されてはいないようだ。ただ、弘治2年に光秀はすでに29歳だったと言われていることから、婚姻関係を結んだのは一般的にはその10年以上前のことだと思われる。
黒髪を売って光秀を支えたと伝えられる煕子
光秀が越前の朝倉氏に出仕していた頃、光秀は歌会を催すための資金繰りに悩んでいた。その際に煕子が黒髪を売ってお金の工面をしたというエピソードが伝えられているが、これは後年の創作である可能性が非常に高い。まず妻木氏はこの当時、小土豪だった明智家を保護できるだけの力を持っていた。それだけ力を持った家の娘が仮にお金を工面するために黒髪を売ったとなれば、光秀としては妻木家の面汚しとなってしまう。あくまでも筆者の想像ではあるが、恐らくは黒髪を売ったのではなく、売ろうとしただけではなかっただろうか。そしてそうせざるを得ない窮状を父に相談し、実際には煕子の父親である妻木範煕(広忠と同一人物である可能性もある)が支援したと考える方が自然に感じられる。
通常女性が黒髪を切ったり剃髪するのは出家した時だ。しかし煕子は出家などしていないため、仮に出家していないのに髪を切り法師頭巾などを被っていれば、これは戦国時代では非常に不自然な光景として映ってしまう。そのため煕子の実家がそうなることを決して許さなかったはずだ。もちろん実際に髪を売ってお金を工面したのかもしれないが、しかし時代と、妻木家と光秀の力関係を鑑みるならば、煕子の実家が支援したと考える方が自然ではないだろうか。
光秀に深く愛され続けた煕子
煕子は天正4年(1576年)に病死したと伝えられているが、しかしこれについても真実であるかは確信することはできない。『西教寺塔頭実成坊過去帳』に記されているこの情報の信憑性は低くはないと思うわけだが、一方『川角太閤記』では本能寺の変後、明智秀満が光秀の妻子を介錯した後に自刃とも書かれており、情報が一致しない。ちなみに『川角太閤記』とは川角三郎右衛門が江戸時代初期に、当時を知る武士たちに直接話を聞くことによってまとめた、本能寺の変から関ヶ原の戦いまでの豊臣秀吉、豊臣家の伝記とされている。江戸時代初期という、まだ本能寺の変を知る人物が多く生きる時代に書かれているため、他の軍記物とは異なり信憑性はあるように感じられる。
天正4年に病死したのか、それとも天正10年に秀満により介錯されたのか、どちらが真実なのかは今となってはわからない。しかしただ一つ間違いなく言えることは、煕子は光秀によって深く愛されていたということだ。煕子が病に伏せれば手厚く看病をしたり、吉田兼見に診療を依頼したりした。そして病により顔に痣のようなものが残ってしまっても、光秀はまったく気にすることなく煕子を大切にしたという。その光秀にも側室がいたという言い伝えもあるようだが、一般的には煕子が存命中は側室は持たなかったという説が広く伝えられている。この言い伝えからすると、秀満が介錯した光秀の妻は後妻という可能性もあるわけだが、筆者はまだそこまで調べ切ることができていない。もしこれに関する資料をどこかで読むことができれば、またここで書き伝えたいと思う。
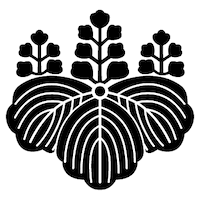
豊臣秀次はなぜ28歳という若さで切腹させられてしまったのだろうか。一般的には謀反の嫌疑がかけられての高野山への追放と切腹だったと伝えられている。だが謀反という線は近年の史家の研究によりほとんどないことがわかってきている。実際に謀反の疑いにより切腹させられたのだとしても、これを冤罪と断言する史家も少なくない。
豊臣秀吉は通常、誰かを攻めたり処分する際にはその理由を明確に書状に示している。だが豊臣秀次の時だけは「不届」としか書いていなかったらしい。「不届き」を辞書で調べると「道理や法に従わないこと」とある。つまり秀次は謀反を起こしたのではなく、何らかの理由によって秀吉に逆らったのである。そしてその理由は千利休と同じであると筆者は考えている。
千利休切腹の真実は別巻にてご確認いただくとして、秀次もあることで秀吉に対し反抗したと考えられている。そのあることとは唐入りだ。秀吉はすでに文禄元年(1592年)に最初の唐入りを実行している。この時は兵を疲弊させただけでほとんど何の利も大義もなかった。そのため秀次はさらなる唐入りを太閤秀吉に、関白としてやめさせようとしたと考えられる。
事実、唐入り反対派の武将たちが関白秀次を中心に集まり始めていたとも伝えられている。唐入りに対して秀吉の決断に異を唱えた、と考えれば上述した「不届」という表現もマッチする。
逆に本当に謀反が切腹の原因だったとすれば、不自然なことも多い。まず秀次の軍勢では秀吉の軍勢にはまったく歯が立たないし、そもそも秀次の重臣たちがまったく軍を動かしていないのである。本当に謀反だとすれば、重臣たちはそれなりに兵を動かすはずだ。それに秀次の切腹後も、秀次の家臣たちはまったく罪を咎められていない。
三条河原で処刑されたのは妻や側女、子どもたちだけであり、家臣たちは殉死した者はいたものの、処刑された者はいなかったようだ。このような事実を追うと、やはり謀反の線はなかったのだろうと思う。
秀次が切腹させられた頃、秀吉はすでに次の唐入りを画策していたと考えられる。つまり
慶長の役だ。秀吉としては今度こそは唐入りを実のあるものにしたいという強い思いがあった。だがそれに対し秀次が異を唱え、秀吉は激昂したのだろう。それでも秀次は唐入りに対し反対姿勢を貫いたため、秀吉はもう「不届」として秀次を処分するしかなくなったのである。秀次の師である千利休同様に。
当時のことを日記に残している何人かの公家は、この頃の秀吉と秀次の関係を「不和」と書き残してはいるが、その不和の理由は誰も書いていない。また『信長公記』などを記した太田牛一にしてもふたりの不和の理由を明確にしていない。本当に知らなかったのかもしれないが、しかし仮に「唐入りに反対したため」と書いてしまったとすれば、書いた本人も秀吉からの処罰を受ける可能性もあるため、理由を知ってはいたが書けなかった、という事情もあるのではないだろうか。
仮に関白秀次が唐入りに対し反対しているということが世間に知れ渡ってしまえば、その唐入りを実行しようとしている秀吉に対する風当たりが強くなってしまう。そしてそうなっては再び唐入りを実行に移すことも難しくなり、将来クーデターをを起こしかねない有力武将たちを国内から朝鮮・明国へと体良く追い出すこともできなくなってしまう。
秀吉としてはとにかく唐入りを成功させ、朝鮮や明国に領地を拡大させたいと考えていた。そのためにも唐入り反対派の中心的存在となっていた秀次の存在が目障りだったのである。だが唐入り反対を理由に秀次を処分しては、上述の通り秀吉の唐入りそのものへの風当たりがさらに強くなってしまう。しかも秀次は関白であり、その影響力は絶大だ。
だからこそ秀吉は秀次に対し謀反の嫌疑を立て、まず高野山へと追放した。ちなみに高野山への追放令の書状は前田玄以、石田三成、増田長盛、長束正家の連名で送られている。
秀次の切腹には三成黒幕説もあるが、それは別巻にて真実ではないことを説明している。
秀吉は、秀次を高野山に追放することにより、反論できない状況に追い込んだ。切腹に関しては秀吉が命じたという説もあるが、実はそうではなく「冤罪を着せられるのなら自ら腹を切る」と、秀次自ら死を選んだ可能性が近年史家によって指摘されている。その理由は秀吉がこの時高野山に送った秀次の処遇を指示した書状に、秀次の切腹に関する記述がまったくないためだ。
どのようなことが書かれていたかと言えば、十数名の世話人は置いていいこと、刀の類は携帯させないこと、家族との面会は禁止させること、ということを主に伝えている。このような書状を秀吉が高野山に送った事実を踏まえれば、秀吉は切腹を命じていなかったと考えるのが自然ではないだろうか。
ちなみにこの書状を高野山に届けたのは福島正則、福原長堯(石田三成の娘婿)、池田秀雄の3名だったようだ。秀次はもしかしたらこの3人が、首実検のために高野山に派遣されたと誤解したのかもしれない。もしそうだとすれば、あまりにも悲劇だったとしか言いようがない。
豊臣秀次はこのような悲運の下、わずか28年という人生を自ら終えてしまったのである。文武両道に勤勉だった秀次が豊臣家を継いでいればと考えると、本当に残念で仕方ないという思いで一杯になってしまう。
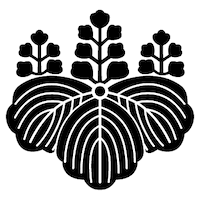
NHK大河ドラマ『真田丸』でも頻繁に登場している豊臣秀次は、幼い頃より死ぬまで叔父秀吉に翻弄される人生を送り続けた。こうまでも自分の好きなように生きられなかった戦国武将も珍しいのではないだろうか。武芸や習い事にも真面目で非常に有能な武将だったのだが、最後は殺生関白と呼ばれるようになってしまい、その有能さを活かすことをできずに28歳という若さで秀吉に切腹を命じられてしまった。
豊臣秀次という人物は永禄11年(1568年)に三好吉房と秀吉の姉である智(とも)との間に生まれた。生年は詳細に記録されていないようだが、後年に残された書状などから逆算をすると、永禄11年生まれが最も有力であるようだ。
ちなみに父親である三好吉房という人物は何度も改姓をしており、最初は木下弥助、その後長尾を名乗り、三好吉房、三好昌之と名を変え、秀次が秀吉の養子となった後は羽柴を名乗っている。
豊臣秀次は28年の生涯で三度も養子に出されている。最初は宮部家だった。宮部とは、浅井長政の臣下であった宮部継潤のことだ。
姉川の戦いに至る前、羽柴秀吉は浅井家臣下の調略に当たっていた。その調略をスムーズに進めるための駒として、秀吉は甥である秀次を宮部継潤の猶子(相続権を持たない養子)とした。
姉川の戦いは元亀元年(1570年)であるため、秀次はまだ2歳ということになる。ちなみに秀次の幼名などは記録に残されておらず、最初に名前が出てくるのは次に養子に出された先での名前、三好孫七郎信吉としてとなる。
宮部継潤と秀次の養子関係は、遅くとも天正9年(1581年)、秀次が13歳の頃には解消されていたようだ。その理由は宮部継潤が秀吉に厚遇されており、養子関係を結ばずとも両者の関係が良好であったためだ。
その後、四国の長曾我部元親と織田信長との関係が悪化してくると、秀吉は四国攻めのための調略に当たるようになる。その時にしっかりと味方に引き入れておきたかった存在が三好康長だった。三好康長とは三好長慶の叔父に当たる人物で、阿波国の有力者だった。長曾我部を攻めるにあたり、阿波国の三好康長をしっかりと懐柔しておきたかったのである。
その調略の道具として、再び秀次は利用された。秀次がまだ13〜14歳の頃になるわけだが、今度は三好家に養子に出され、三好孫七郎信吉と名乗るようになった。一説では天正7年(1579年)の段階で三好家の養子になっていたともされているが、この頃の三好康長はすでに信長に降っており、織田家と長曾我部家の対立もなかったため、秀次を三好家の養子に出す理由がない。そのため近年の史家の研究では、実際に養子となったのは織田家と長曾我部家の対立が鮮明になった天正9年秋頃という見方が有力とされている。
だが両家の対立も、
本能寺の変によって回避されることになり、秀次が三好を名乗った期間も短く終わった。そして天正12年(1584年)の小牧長久手の戦いの後、16歳になると羽柴孫七郎信吉と名乗り、その直後に羽柴孫七郎秀次と名乗るようになっている。こうしてようやく秀次は羽柴一門に戻ってきたのである。
16歳までの秀次はこのように、秀吉の都合によって他家へ養子に出される日々を過ごしていた。こうして見ていくと秀吉は秀次に対しそれほど愛情は持っていなかったのだろう。確かに戦国の世では養子に出されることは珍しいことではないが、しかし28年の生涯で三度も養子になることは珍しい。三度目はもちろん実子を幼くして亡くした秀吉の養子としてだ。
秀吉が甥っ子に対してそれほど愛情を持っていなかったからこそ、戦略上の都合で簡単に養子に出しては戻すということを繰り返したのだろう。そしてだからこそ秀吉は、豊臣秀次に対しあれほど惨い最期を遂げさせた。文禄4年(1595年)7月15日に秀次を自害させると、8月2日には京の三条河原で秀次の妻子を全員処刑してしまった。
この秀次の死が、豊臣家を秀吉一代で衰退させてしまった最大の要因だとされている。もし秀次を自害させていなければ秀吉死後、幼い秀頼が家督を継ぐこともなく、立派な武将に成長していた秀次が豊臣家を継ぐことにより、徳川家康に政権を奪われる隙も与えずに済んだと考えられている。
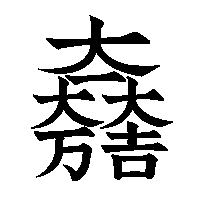
石田三成という人物は本当に誤解されやすい人だ。その理由の一つとして実直すぎるという点を挙げられる。そして実直すぎる故に融通が利かなく、あまり他人を信用しないという性格だったようだ。そしてその性格による対応のせいで、慶長の役では豊臣恩顧の武断派との溝がさらに広まってしまった。
慶長の役とは慶長2年(1597年)に始まった秀吉二度目の唐入りのことで、この朝鮮との戦は慶長3年に豊臣秀吉が死去したことにより終結した。その際、石田三成は国内に留まり、自らが信頼を寄せる軍目付(いくさめつけ)7人を朝鮮に派遣し、戦況や戦功の状況を調査させた。
その7人とは太田一吉(三成家臣)、垣見一直(三成家臣)、熊谷直盛(三成の娘婿)、竹中重利(竹中半兵衛の義弟)、早川長政、福原長堯(ながたか、三成の妹婿)、毛利高政という人選だった。このように三成は軍目付として、自らが信用している人物だけを選んだ。だがこの人選が武断派の不興を買ってしまう。
加藤清正、福島正則、黒田長政、細川忠興らは、軍目付として三成の臣下以外からも選ぶようにと迫ったが、三成はそれを受け入れなかった。その理由は武断派の息がかかった者を選べば、事実を誇張して報告される恐れがあったためだ。それを防ぎ、事実を正確に把握するために三成は自らが信頼している人物のみを軍目付として選んだ。
この7人の報告を受け、最終報告するのは三成の役目だったわけだが、武断派たちはそこで三成が讒言し、自らの武功を過小評価されたのではないかと猜疑したようだ。だが三成は過小評価して報告をしたわけでも、讒言したわけでもなかった。ただ事実をありのままに秀吉の報告したに過ぎなかったのである。決して私情を交えて報告するようなことはしなかった。
武断派たちは三成の思いなどまったく理解しようとはしなかった。文禄の役などでは特に、日本軍は海路を確保することができなかった。そのため兵糧を日本から朝鮮に送ることもできず、送ったとしても輸送船はあっという間に沈められてしまった。それにより朝鮮の日本軍は食糧危機に陥った。それでも武断派は戦いを続けようとしたのだが、三成は兵を無駄に死なせることを嫌い、退却を強く進言したのだった。
慶長の役では慶長3年8月18日に秀吉が死去し、朝鮮攻めが頓挫すると、三成は帰国してきた武将たちを博多で出迎えた。そして「伏見で秀頼公に御目通りされたら一度国に戻り休み、来年また上洛あれ。その折には茶の湯でも楽しもうではないか」と心からの労いの言葉をかけたようだが、加藤清正は「治部少は茶を振舞われるがよかろう。我らは異国で7年も戦い、米一粒、茶も酒もないため稗粥(ひえがゆ)ででも持て成そう」と怒鳴りつけたと伝えられている。
しかし振り返り見れば、兵糧が尽きかけようとしても戦を続けたのは清正ら武断派であり、兵を守るため撤退させようと苦心したのが三成だった。武断派たちはそんなことは決して理解しようとはせず、理不尽にも三成に当たり散らしたのだった。
秀吉の死は、三成にとっては心が千切れるような出来事だったに違いない。自分を武将に仕立ててくれた恩人であり、三成は秀吉の構想を実現させるべき身を粉にして働いてきた。三成にとっては秀吉こそが正義だったのである。慶長の役は8月以降、撤退は12月まで及んだのだが、三成は兵たちが無事帰国できるように、その間も奉行として涙を見せず働き続けた。
石田三成という人物は、自らにかかる疑念に対し弁明することはほとんどしなかった。そのため誤解が解かれることもなく、誤解がさらなる誤解を生んでしまうことも多々あった。そして江戸時代になると徳川家康の敵として、さらに有る事無い事酷く書かれることになってしまう。
秀吉の生前は秀吉のミスをカバーし続け、そのミスも自らが罪を被り、秀吉のカリスマ性が失われないように対応し続けた。そのような事実も武断派たちは決して知らなかったはずだし、知ろうともしなったのだろう。現代の歴史ドラマでも石田三成は未だ悪役として描かれることが多い。だが実際の石田三成は信じた正義を貫き通した、豊臣家最大の義将だったのである。
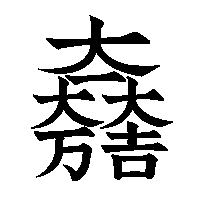
石田三成と加藤清正は本当に仲が悪かったのかと言えば、それは確かであるようだ。そしてその仲を決定的に悪くしたのは文禄の役での一連のやりとりでだった。文禄の役とは天正20年(1592年)4月に始まった唐入りのことだ。ちなみにこの年の12月8日に文禄と改元されたために、この唐入りは文禄の役と呼ばれている。
実は石田三成は唐入りには反対の意を持っていた。だが千利休や豊臣秀次とは違いそれを態度で示すことはなかった。しかし検分のため自らも実際に朝鮮に渡り、兵糧が尽きかけていると知るや否や、三成はすぐに戦線を縮小させようとした。それに異を唱えたのが加藤清正ら、いわゆる豊臣恩顧の武断派武将だちだったわけだ。
唐入り直後は、日本軍は破竹の勢いで朝鮮を攻め立てていた。だが明国が朝鮮の援軍として駆けつけてきた後は日本軍の勢いは少しずつ失われていく。そして見知らぬ土地で食べ物を調達することもできず、病死する者も多数出るようになった。これ以上戦況を悪くしないためにも、三成は戦線の縮小を大将宇喜多秀家に進言したのだった。
しかしこの時点では、槍働きをしている武将たちの手柄はほとんどないに等しかった。つまりこのタイミングで戦が終わってしまうと、兵を消耗しただけで何の得もない状態で帰国させられることになる。それだけは避けたいと躍起になったのが加藤清正だった。
さらに石田三成は軍目付(いくさめつけ)として、加藤清正を讒言(ざんげん)したと伝えられている。讒言とは事実を捻じ曲げて他人を陥れようとする行為のことだが、石田三成は決してそのようなことはしなかった。ただ、事実だけを秀吉に伝えたのである。
どのような事実かと言えば、実はこの戦いで加藤清正は、朝鮮の王子ふたりを捕虜としていた。戦いは少しずつ日本軍が劣勢に傾き始めており、そこへ明国の勅使から清正はある提言を受けた。それは朝鮮の王子をふたりとも無事に返せば、日本軍もこのまま無事に日本に返してくれる、というものだった。
だが清正はこの提案を勝手に蹴ってしまった。しかもあろうことか「豊臣朝臣(あそん)清正」と署名して。しかしこの時の加藤清正は豊臣姓は賜っていない。つまり清正は勝手に秀吉の姓を用い、勝手に交渉を蹴ってしまったというわけだ。三成はこの事実をありのまま秀吉に報告したに過ぎなかった。
さらに清正は明国とのやり取りの中で、小西行長のことを商人扱いし侮辱し、清正の家臣に至っては現地で狼藉を働いてもいた。このような事実が秀吉の怒りを買い、清正はその後帰国と伏見への蟄居を命じられている。ちなみに清正の勝手な越権行為が交渉決裂を招いてしまい、慶長の役へと繋がってしまった。
このように事実は、石田三成は讒言などしてはおらず、事実を報告されたことを加藤清正が讒言されたと歪曲理解してしまっただけの話なのだ。石田三成は、決して加藤清正を陥れようとなどしてはいないのである。だが日頃の不仲が積もり積もったことにより、このような事態になってしまったことは確かだろう。
この出来事により、石田三成と武断派たちとの間には決して埋め切れない大きな溝が生まれてしまった。そしてこの溝を巧みに利用して豊臣家から政権を横奪したのが徳川家康なのである。
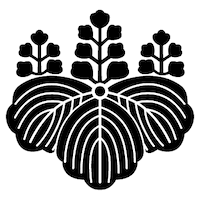
豊臣秀吉はなぜ文禄の役、慶長の役と二度に渡り唐入りを実施したのか?唐入り賛成派の武将というのは実はほとんどいなかった。大それた反論はしなかったものの石田三成でさえも唐入りには反対しており、実際に反乱の火種となりかねなかった豊臣秀次や千利休に至っては切腹させられている。秀吉はなぜ秀次や利休を切腹させてまで唐入りを目指したのだろうか。
実は唐入り構想の原案は秀吉のものではなかった。最初に唐入りを目指すと口にしたのは織田信長であり、それを嫌った明智光秀により信長は討たれてしまった。つまり秀吉は、信長が考えていたことをそのまま自分のアイデアとして取り入れてしまったということになる。
信長は日の本を統一した後は、有力大名たちには刈り取った朝鮮、民国の広大な土地を与え、国内の主要部は織田一門に任せるという構想を練っていた。本能寺の変直前、織田家で最も力を持っていた家臣が明智光秀であり、まさに光秀は朝鮮、民国に移封させられる最有力とされていた。
秀吉も同じことを考えていた。朝鮮、民国に攻め入り領地化し、力を持ち過ぎた大名たちを国内から追い出そうと考えていたのだ。そしてさらには領土を広げることにより、秀吉は大王になろうとしていたとも言われている。一説では実子捨(すて)の死の悲しみを癒すべく唐入りしたとも言われているが、一国を治める太閤(前関白の意)がそのような理由で戦を仕掛けるはずはない。
秀吉も信長同様、有力大名たちを国内から追い出すような形にし、国内は豊臣一門を中心に政権運営していくことを目指したのだった。そしてこれが実現されれば秀吉亡き後、有力大名に後継が狙われる心配もなくなる。秀吉としては先の短くなっていた命、後継が狙われる心配を排除した上で命を全うしたかったようだ。
だからこそ唐入りに意を唱え、クーデターを起こす可能性のあった豊臣秀次や千利休を、下手な言い掛かりをつけて切腹させてしまっている。実際多数の武将たちが秀次や利休を頼り、秀吉に唐入りを中止させるように頼んでいたようだ。秀吉としては唐入り反対派をまとめる役割を果たしていた秀次や利休が邪魔で仕方なかったというわけだ。
武器商人であった千利休としては、実際のところは唐入りという大掛かりな戦をしてくれた方が莫大な利益を得ることができた。それでも利休が唐入りに反対したということは、それだけ国益に繋がらない大義なき戦だと唐入りは見られていたのだろう。そして実際二度に渡り行なわれた唐入りは、大義も成果も何もない戦で、ただただ大名たちを疲弊させただけで終わってしまった。
だが秀吉からすれば、力を持ち過ぎた大名の体力を失わせただけでも、唐入りは成功に値するものだったのかもしれない。だが立派な武将に成長していた豊臣秀次を切腹させてしまったことで、豊臣政権はその後大きく揺らぐことになってしまう。秀次は素行が悪かったとも伝えられているが、しかしそれは切腹を命じた際のでっち上げだと考えられている。実際の秀次は武士としての習い事も真面目に取り組み、勤勉であり、教養にも優れた人物だった。
詳しくはこちらの巻に記しているが、秀次は千利休の愛弟子でもあった。そのため唐入りを阻止するために二人が結託していた可能性も非常に高い。だからこそこのふたりが揃って見せしめとして切腹させられたと考えるのが自然ではないだろうか。
日の本全体としては決して成功とは言えない結果に終わった唐入りだが、しかし秀吉個人からすれば上述の通り唐入りは決して失敗ではなかった。だがその唐入りをめぐっての秀次の切腹などにより、その後豊臣政権が行き行かなくなってしまった。もし秀次に切腹を命じていなければ幼い秀頼が家督を継ぐ状況にもならず、豊臣政権も秀吉一代では終わっていなかったかもしれない。
だが秀次を失ってしまったことにより豊臣政権は大きく揺らぎ、秀吉の死後はあっさりと徳川家康に政権を乗っ取られてしまった。そういう意味に於いては秀吉の唐入りは、特に秀吉の死後は豊臣家に大きな爪痕を残す形となってしまった。
天正19年(1591年) 千利休切腹
文禄元年(1592年) 文禄の役
文禄4年(1595年) 豊臣秀次切腹
慶長2年(1597年) 慶長の役

天正18年(1590年)の小田原征伐以降、真田家に大きな動きはほとんどなかった。しかし文禄元年(1592年)2月、いよいよ豊臣秀吉の朝鮮出兵を実行に移すため、真田昌幸は徳川家康、上杉景勝と共に肥前名護屋城に赴いている。ちなみに名護屋城とは朝鮮出兵の拠点として、天正19年10月から普請され、短期間で仕上げられた城だった。
名護屋城には7万3千もの兵が集結した。その中から実際に渡海して行く部隊人数が細かに定められたわけだが、真田父子は700人の兵を持ち、渡海する際は500人連れて行くようにと定められた。だが実際に真田父子が渡海することはなく、上述の通り家康、景勝と共に名護屋城で秀吉の身辺警護を行い、最後まで渡海命令が下されることはなかった。
この時徳川家康、上杉景勝と近い扱いをされるということは、秀吉の中で真田昌幸の存在はかなり大きかったのだろう。そして戦術家としても、小田原征伐以来、秀吉は昌幸を高く評価していたようだ。大名としての格から、さすがにその後大老になるようなことはなかったが、しかし一連の処遇を見ていくと、秀吉が昌幸のことを高く買っていたことが良くわかる。
同じ戦術家として豊臣家には黒田孝高という存在もまだあったわけだが、しかし秀吉に対し耳の痛いこと言う軍師であるためか、この頃の黒田孝高は秀吉からは遠く離されてしまっていた。その黒田孝高の代わりとして、新たな豊臣恩顧の小大名であり、知略にも優れた真田昌幸を置いておきたかったという気持ちが秀吉の中にはもしかしたらあったのかもしれない。
さて、文禄の役では渡海は命じられなかった真田父子だったが、文禄の役が終わると、その替わりとなる役割が待っていた。それは伏見城の普請役だった。伏見城は秀吉が隠居後に暮らすつもりの城で、大坂と京のほぼ中間に作られたものだった。この城の普請を一部担ったわけだが、真田家は木材の提供と1680人(知行高の1/5)の労働者の提供を求められた。
だが文禄の役で実際に渡海させられるよりは遥かにましと言える勤めだった。しかも伏見城の普請、そして名護屋城への出向の恩賞として、家督を継いでいた真田信幸には下従五位伊豆守と豊臣姓が与えられた。真田信繁(幸村)にも下従五位左衛門尉と豊臣姓が与えられたと伝えられてはいるが、しかし信繁の場合はそれを証明する書状は残されてはいない。
その後文禄4年には秀吉が草津温泉への湯治に出かけるということで、真田家はその饗応役を任ぜられたのだが、実際に秀吉が草津に赴くことはなかったようだ。秀吉はこの3年後に病死してしまうわけだが、もしかしたら伏見から草津へ出かけられないほど、この時の秀吉は体が弱っていたのかもしれない。もしくは慶長の役に向けての準備が忙しかったのだろうか。
このように、小田原征伐以降は真田家にはそれほど目立った動きはない。文禄の役では実際に出陣には至らず、文禄の役後は伏見城の普請を担当した程度だった。真田家は最初から最後まで徳川家や北条家などに振り回されていたわけだが、その北条家が滅亡した小田原征伐から少しの間だけは、因縁の沼田領も安堵されていたこともあり、真田家にとってはつかの間の平穏の時だったのかもしれない。

慶長5年(1600年)9月15日に開戦された関ヶ原の戦い、一般的には東軍徳川家康が勝つべくして勝ったと理解されている。だが決して楽な戦いではなく、実は開戦する以前の前哨戦に於いては家康は賊軍に成り下がる可能性すらあった。いや、事実賊軍として見做され、一時は身動きが取れない状況にも陥っていた。だがこの危機を救ったのが黒田長政、つまり黒田官兵衛の息子だったのだ。
そもそも家康は、自ら蟄居させていた石田三成が挙兵するとは想像だにしていなかったようだ。家康に並び五大老の筆頭だった前田利家が亡くなると歯止めが利かなくなり、豊臣家のいわゆる武断派たちが三成を襲撃してしまう。その仲裁役を担った際、家康は三成に蟄居を命じていた。これにより家康は、三成を政治的には事実上葬ったつもりでいた。だがその三成が大谷吉継の協力を得て挙兵するという噂が湧き起こる。
この時奉行衆は家康に対し、三成と吉継が不穏な動きをしているため牽制して欲しいという要望を送った。だが三成は奉行衆たちを説得し、実は家康が太閤秀吉の遺言にいくつも背いているという事実をわからせた。それにより奉行衆は態度を変え、家康を太閤秀吉に対する反逆者と見做したのだった。
家康は上杉討伐のため7月21日に会津に向かったのだが、その時点で家康の耳に入っていたのは三成と吉継の結託だけだったようだ。家康からすれば、三成と吉継が結託したところで兵力は徳川家の1/10にしか過ぎず、気にする程度の規模ではなかった。だが家康が会津へ出立すると、三成の説得により奉行衆や多くの大名たちが態度を変え、反家康軍として集結してしまう。
道中、家康は多くの不穏な報せを受けた。とてもじゃないが会津に遠征していられるような状況ではなくなり、7月25日に遠征に帯同していた武将たちを集める。いわゆる小山評定(おやまひょうじょう)だ。小山評定では主に上杉景勝と石田三成の、どちらを先に討つかということが話し合われた。その結果三成を先に討つことが決定する。
その後家康はひとまず江戸城に戻るのだが、しばらく江戸城から出立できない状況が続いた。つまり奉行衆たちにより賊軍とされてしまったことで、親家康の大名たちの多くが西軍になびく可能性があったのだ。それは親家康の筆頭とも呼べる福島正則にしても同様だった。
その理由は家康が会津へ向かったことにより、豊臣秀頼が西軍の手に渡ってしまったためだった。秀吉亡き後、まだ幼い豊臣秀頼が淀殿の後見により豊臣家を継いでおり、実際にはまだ豊臣政権が続いていた。だが奉行衆が、家康が太閤秀吉の遺言に背いていると糾弾したことにより、家康は完全に賊軍に貶められてしまう。それによって親家康大名たちがこぞって西軍になびく可能性があり、家康は下手に江戸城を出られなくなってしまった。
だがこの危機を救ったのが黒田長政だった。長政だけは最初から最後まで親家康を貫き、奉行衆が糾弾した後も家康のために動き続けた。まず小山評定で福島正則をけしかけ、反三成で結託するように仕向けた黒幕が黒田長政だった。長政の働きもあり、小山評定の時点では大きな離脱者が出ることはなく、それどころか打倒三成で一致団結することになった。
さらにその後、長政は吉川広家の調略に尽力する。吉川広家と言えば毛利両川の吉川家、吉川元春の息子だ。そして吉川家が支える毛利家当主である輝元は、西軍の総大将の座に就いている。だが吉川広家は、輝元は安国寺恵瓊にそそのかされ知らぬうちに総大将に担ぎ上げられていた、と家康に申し開きをする。
毛利家の政治面を担当していたのが安国寺恵瓊で、軍事面を担当していたのが吉川広家だったのだが、しかしこのふたりは犬猿の仲だったようだ。特に広家が恵瓊のことを毛嫌いしていた。そのため恵瓊側では毛利を西軍に味方させようとし、広家側では家康に味方させようとしていた。
だが申し開きをしても広家はなかなか態度を明確にしなかった。つまり家康に味方するとなかなか明言しなかったのだ。その広家を時には嘘も交えて調略したのが黒田長政だった。最終的に長政はこの調略に成功し、関ヶ原の戦いで毛利軍を出撃させないことに成功する。
もし黒田長政の活躍がなければ西軍総大将である毛利輝元は当然出撃し、西軍からの離脱者も最小限に抑えられていたはずだ。そしてほとんど互角の兵力差の中、遠征軍を率いる東軍家康と、城を盾に戦える西軍とでは実は西軍に分があった。仮に黒田長政の調略がなければ、関ヶ原の戦いは西軍勝利で終わっていた可能性も高い。
長政の調略がなければ福島正則は豊臣秀頼を奉じる西軍に寝返っていた可能性もあり、さらには毛利輝元が出撃してくる可能性もあった。もしこのどちらかでも史実と逆の事実になっていれば、西軍が勝利していた可能性が高い。そう考えると関ヶ原の戦いを東軍勝利に導いたのは黒田長政の手腕によるところが大きいのである。
さすがは黒田官兵衛の息子であり、幼少時は
竹中半兵衛に命を救われ教えを受けた武将だけのことはある。福島正則に対しても、吉川広家に対しても冷静に戦局を見極め、最適なポイントを突いていく能力を持っていた。黒田長政はいわゆる武断派に属されることも多いが、槍働きだけではなく、このような知略にも富んだ名将だったのである。

天正10年(1582)年6月2日、本能寺の変はなぜ起こってしまったのか?!誰が黒幕だったかということでも様々な論争が行われているが、黒幕がいたようには感じられない。本能寺の変について書いた他の巻でも書いたことではあるが、これは織田信長の将来構想に対する家臣たちの不安の産物だったと考えられる。
筆者はこれまで多数の本能寺の変に関する書物を拝読してきた。その中でも多くのことを証拠を用いてスッキリさせてくれたのが明智憲三郎氏の『
本能寺の変 431年目の真実
』という一冊だった。この中で筆者が最も衝撃的だったのが、信長が手勢僅か100人程度で本能寺に滞在していた理由だった。
さて、信長と家康と言えば兄弟同然の間柄として有名だ。信長は家康のことを弟のように可愛がり、家康も信長のことを兄のように慕っていた。これが通説であるわけだが、事実そうだったと思う。本心はさておき、信長と家康の仲を悪く書いた当時の書物はないようだ。
信長が本能寺に滞在していた通説は、本能寺で家康を接待するためだったと言われている。だが明智憲三郎氏の歴史調査によると、事実はそうではなかったようだ。確かに家康を接待するために信長はわざわざ本能寺に家康を呼び寄せた。しかし事実は決して接待するためではなかったと言う。
この時、明智光秀は手勢を控えて本能寺の近くに控えていた。通説のうちにはノイローゼ気味だった光秀が、突発的に本能寺を襲撃したと書かれたものもあるが、これらの考察はすべて推察でしかなく、何の根拠も示されてはいない。だが明智憲三郎氏の著書は違う。証拠をいくつも並べ立てた上で、信長が家康を本能寺に呼び寄せたのは、家康を暗殺するためだと証明して見せている。他の本能寺の関連本とは異なり、証拠が示されているだけにとにかく説得力があるのだ。
信長は、家康に警戒されないように100人程度の手勢だけで本能寺に滞在していた。つまり油断していたわけではなく、家康を警戒させないための芝居だったと言うわけだ。だが信長の誤算は、光秀を信じ過ぎたことだった。これは
金ヶ崎撤退戦と同様だ。金ヶ崎撤退戦でも信長は義弟浅井長政を信じ過ぎ、危うく命を落とすところだった。
一度目は何とか命拾いした。だが二度目は浅井長政よりも遥かに智謀に優れ、経験豊富な明智光秀が相手だった。光秀は影で家康と密約を結んでいたと言う。光秀は、本能寺に入った家康一行を暗殺するために本能寺近くで待機していた。だが光秀は家康と手を結ぶことにより、これを家康暗殺ではなく、信長暗殺に計画を仕立て直してしまったのだ。詳しくはぜひ明智憲三郎氏の著書を読んでもらえたらと思う。
つまり本能寺で本来討たれる相手は徳川家康だったのだ。信長は家康のことを高く買っていた。それだけに自身亡き後、家康が子孫たちの脅威になると考えたようだ。その後家康が豊臣家から天下を奪い取ってしまうように。それを未然に防ぐため、信長は早いうちに家康を屠ってしまおうと考えたらしい。
話をまとめるとこうだ。信長は、家康を暗殺するために本能寺に呼び寄せ、光秀に暗殺を命じていた。だが光秀は家康と手を結んでしまい、家康ではなく主君信長を討ち果たしてしまったというわけだ。
戦国時代に武将たちが最も重視していたのは、いかにして家を守るかということだった。家を守るためなら身内であっても討ち果たすことなど日常茶飯事だった。信長が家康の暗殺を企てたのも織田家を守るためなら、光秀が信長を討ったのも明智家(土岐家)を守るためだった。そして家康が光秀の企てに力を貸したのもやはり、徳川家を守るためには光秀と手を結んだ方が上策だと考えたからだった。
明智憲三郎氏の著書を拝読しながら改めて本能寺の変を考えていくと、これは決して偶発的に起こったクーデターなどではなく、起こるべくして起こった出来事だったということがよくわかるのである。