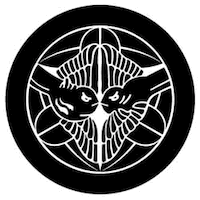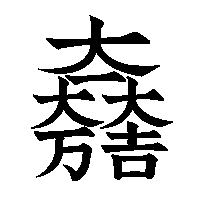戦国時代を語るにあたり必ず登場するのが軍師の存在だ。竹中半兵衛、黒田官兵衛、直江兼続、山本勘助、立花道雪ら戦国時代にはその他にも名だたる軍師たちの存在が多く見て取れる。だが戦国時代そのものにはどうやら軍師という役職は存在していなかったようだ。
江戸時代後期や明治時代になると歴史小説が読まれるようになり、それらの小説により軍師という言葉は一般的になった。そしてそれらの小説に軍師という言葉が登場するきっかけとなったのは、江戸時代以降の軍学者たちによる研究結果だった。学者たちは大名に様々な知恵を提供する役割を担った人物のことを軍師と呼ぶようになり、それが小説の世界へと広がって行き、一般的にもよく知られる言葉となっていった。
歴史ドラマではたまに軍師のことを「軍師殿」と呼ぶシーンが描かれているが、どうやら実際にそのように呼ばれることはなかったようだ。例えば直江兼続のように守護職を持っている人物の場合は「山城守(やましろのかみ)」や「山城」と呼ばれていた。一方竹中半兵衛のように役職に関心のない人物は「半兵衛殿」「竹中殿」と呼ばれていた。
ここでは便宜上「軍師」という言葉を使うが、室町時代から戦国時代初期にかけての軍師は、占い師的な要素が強かった。例えば奇門遁甲などを駆使し方角や運勢を読み、運を味方に付け戦に勝つ手助けを行なっていた。いわゆる陰陽師のような存在だ。
そのため特に戦国時代初期の軍師は、実際には陰陽師ではないが、陰陽師をルーツにするような僧侶などの修験者(しゅげんじゃ)が務めることも多かった。例えば今川義元を支えた太原雪斎(たいげんせっさい)や、大友家を支えた角隈石宗(つのくませきそう)のような存在だ。だが戦国時代が中期に突入すると『孫子』などの軍学に精通した人物が軍師として重用されるようになる。羽柴秀吉を支えた竹中半兵衛や黒田官兵衛のような存在だ。
これが戦国時代も末期に差し掛かり戦が減って行くと、軍学を得意とする軍師の役割も減って行く。その代わりに台頭してくるのが吏僚型の軍師だ。
石田三成や大谷吉継のような存在だ。彼らは戦のことももちろん学んでいるが、それ以上に兵站(兵糧)の確保や金銭の管理に大きな力を発揮した。特に石田三成は近江商人で有名な土地で生まれ育ったため算術を得意としており、豊臣秀吉が仕掛けた朝鮮出兵などでは後方支援として大きな役割を果たした。
ちなみに日本最初の軍師は吉備真備(きびのまきび)という人物だ。奈良時代(700年代)の学者で、中国の軍学を学ぶことによって戦術面に貢献するようになり、藤原仲麻呂が起こした乱を巧みに鎮圧したことでも知られる人物だ。その後鎌倉時代から南北朝時代に入って行くと、今度は楠木正成という軍師が登場する。楠木正成は、戦国時代で言えば真田昌幸のようなゲリラ戦法を得意とする軍師だった。
強い忠誠心を持っていたことから、戦国時代にはヒーローとして崇められ、例えば竹中半兵衛などは「昔楠木、今竹中」「今楠木」となどと呼ばれ、その高い手腕が賞賛されていた。
軍師とは野球チームで言えばヘッドコーチ、内閣で言えば官房長官のような役割になるのだろう。決してトップになることはないが常にトップの傍らでトップを支え、成り行きを良い方向へと向かわせる役割を果たす。
ちなみに軍師は『孫子』などに精通している必要があるが、現代でMBAを取得する際の必須科目にも『孫子』は加えられている。その孫子(孫武)自身も紀元前500年代に活躍した中国の軍師(軍事思想家)だった。
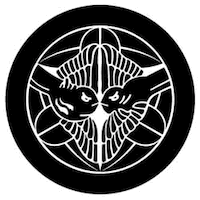
直江兼続が認めた『直江状』は、一般的には徳川家康への挑戦状として知られている。そしてこの『直江状』が関ヶ原の戦いの一因になったとも言われている。だが実際に『直江状』は徳川家康への挑戦状ではなく、単純に上杉家にかけられた嫌疑を晴らしたいという思いが込められた書状だったのである。
『直江状』が書かれたことにはそれなりの原因があった。それは上杉家の、越後から会津への移封である。上杉家は死去する直前の豊臣秀吉の命令により慶長3年(1598年)に移封させられた。これにより上杉家は50万石から、120万石の大大名となる。秀吉が上杉家を移封させたのには、上杉家に江戸の徳川家康の牽制役を務めてもらいたかったからだった。
国替えさせられた際に直江兼続と石田三成が協議し、この年に徴収した慶長2年分の年貢をすべて会津に持っていくことになった。上杉家の後に越後に入ったのは堀秀治で、米倉が空になっていることに驚く。そして上杉家に借米してなんとか窮地をしのいだわけだが、次の年貢徴収(慶長3年分)で、さらに驚くべき事実が発覚した。何と農民の多くが上杉家を慕い、一緒に会津に移り住んでしまっていたのだ。
これにより越後の田畑の多くが耕作放棄されることになり、堀家はほとんど年貢を徴収することができなかった。この状況を堀秀治の家老である堀直政が徳川家康に訴え、更には上杉家に遺恨を抱いたことで「上杉家に不穏な動きあり」と讒言までしてしまった。これは慶長4年の出来事であり、移封を命じていた豊臣秀吉はすでに前年に死去している。
秀吉の死により豊臣政権の中心となっていたのが徳川家康だったわけだが、家康とって上杉家は目の上のたんこぶだった。なにせ上杉家は、徳川家康の牽制役として会津に国替えさせられていたのだから。家康としては何とか上杉景勝を失脚させたかったわけだが、その大義名分を堀秀政の訴えによって得たのだった。
家康は「二心ないのであればすぐに上洛せよ」と上杉家に迫る。だが上杉家は移封させられたばかりで会津国内もまだ落ち着いていないため、落ち着いてから秋にでも上洛したいと返す。だが家康はすぐに上洛をしようとしない上杉家に二心ありと決めつけてしまう。これに対し不満を示したのが上杉家であり、『直江状』だったのである。
『直江状』には主に、家康は堀家の讒言は究明しようともせず鵜呑みにしたのに、なぜ上杉家の言い分は聞こうとしないのか、それは不公平であると書かれている。これは決して家康への挑戦状ではなく、上杉家の純粋な訴えだった。現に先には秋に上洛したいと伝えていたが、『直江状』では夏に上洛すると繰り上げており、豊臣政権にも家康に対しても喧嘩など売っていないのである。
そして「二心がないのなら上洛せよ」という家康の要求に対し、謀反の疑いと上洛をセットにして考えて欲しくはないとも訴えている。上杉家としてはあくまでも、会津の領国支配が落ち着いたらすぐにでも上洛する旨を示しており、二心がないから上洛するのではない、ということを直江状では訴えられている。
小説やテレビドラマではストーリーをドラマティックにするため、『直江状』は家康への挑戦状として描かれることも多い。しかし真実はそうではない。上杉家の「真実を究明して欲しい」という思いが込められただけの書状だったのである。
ちなみに家康が真実を究明しようとしなかった理由の一つには、上述したように年貢について協議した相手が石田三成だったからという可能性がある。慶長4年と言えば関ヶ原の戦いが起こる前年であり、この頃の石田三成と徳川家康はほとんど敵対しているような状態だった。慶長4年3月には、家康により五奉行石田三成は蟄居させられており、家康と三成の関係は冷え切っていた。
そのような状況だったこともあり、家康は三成が絡んでいることに対して知らない振りをしていたのかもしれない。だが家康が知らない振りをしたことにより直江兼続と、失脚していた石田三成が連絡を取りやすくなり、それが関ヶ原の戦いを引き起こす三成の挙兵に繋がった可能性もある。
この時三成と兼続が連携を取っていた証拠は残っていないため、真実は定かではない。だが隠密裏に行われていた作戦の証拠が残させるケースはほとんどないため、証拠がないからと言って、ふたりの連携がなかったとは言い切れない。もちろん連携があったと言い切ることもできないわけだが、親友であったふたりだけに、その可能性は十分にあったのではないだろうか。
『直江状』を受け取った家康はそれを読み激怒したという。そして関ヶ原の戦い3ヵ月前の慶長5年(1600年)6月、家康はついに上杉討伐のために会津に出陣していく。そしてこの機を狙っていたかのように石田三成は打倒家康を掲げ、大阪で挙兵したのだった。
史家の分析では石田三成と直江兼続は協力関係にあり、『直江状』を送れば家康は必ず会津に出陣すると予測し、その隙を突き三成が大阪で挙兵し、上杉家と共に家康を東西から挟み撃ちする作戦を練っていたとするものもある。上述の通りその証拠は残されていないわけだが、やはり可能性としては十分にありえたと考えるべきではないだろうか。
何故ならもし三成と兼続の連携がなく『直江状』を送ったとすれば、単純に上杉家が家康に攻められる戦に終わり、そうなればこの頃の上杉家だけでは家康に勝つ力などなく、上杉家は滅ぼされていた可能性も高かった。連携があったからこそ上杉景勝は直江兼続に命じ、家康を刺激する可能性の高い『直江状』を書かせたのではなかっただろうか。
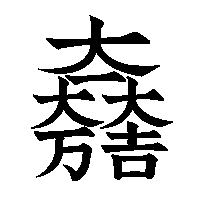
石田三成という人物は、とにかく周囲から誤解されやすい性格だった。どうやら率直に物を言い過ぎてしまう嫌いがあったようで、意に反し言葉にも棘があったらしい。だがその実像は決して冷徹な人間ではなく、心に熱いものを秘めた人物だった。そして誰よりも日本という国と豊臣政権のことを深く愛し、そして考えていた。自身のことなど二の次だったのだ。
近江出身の三成には、近江商人の血が流れていた。近江商人と言えば「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」を信条とする商人たちのことだ。つまり売る側も買う側も幸せになり、それによって世間全体も良くしていこうという信念だ。三成もこの近江商人の信念を受け継いでいた。だが三成自身はと言えば、買い手と世間の幸せばかりを考え、自らの幸せなどほとんど考えていなかった。
その好例となるのが佐和山城だ。佐和山城と言えば「三成に過ぎたるもの」と揶揄されたほどの名城で、三成が関ヶ原の合戦後に京都の六条河原で処刑されると、その城は東軍によって接収され、井伊直政(井伊直虎のはとこ)に与えられた。その際将兵たちは「三成のことだから秀吉のように、さぞや財宝を蓄えているのだろう」と考えていた。だが彼らは佐和山城に入り驚くことになる。
佐和山城内は財宝に溢れかえるどころか、驚くほどに質素だった。壁にも庭にも装飾品らしいものは一切なく、生活感さえ感じられないほどだったようだ。三成は「残すは盗なり。つかひ過して借銭するは愚人なり」という言葉を残している。これは農民たちから集めた年貢を使い残し自分のものとするのは盗み同然であり、逆に使い過ぎて借金をするのは愚か者、という意味だ。誰よりも現代の政治家たちに教えてあげたい言葉だ。
つまり三成は集めた年貢はすべて民政のために使い、わずかに残った分で慎ましく暮らしていたのだ。テレビドラマで描かれているように、決して派手な着物を纏っていたわけではなかった。三成は秀吉政権の重臣だったため、どうしてもイメージが秀吉と被ってしまったのだろう。NHK大河ドラマでさえも時に三成を流行に敏感な派手な人物として描いている。
現代に於ける三成のイメージは、すべて江戸時代に捏造されたものばかりだ。確かに武断派と呼ばれた加藤清正、福島正則、黒田長政らとは反りは合わなかったようだが、しかしだからと言って誰からも嫌われるような人物ではなく、逆に身近な人間からは非常に好かれていたのだ。
秀吉が滅ぼした大名家の遺臣たちを三成も多く召し抱えたわけだが、彼らのほとんどは関ヶ原の合戦で三成に命を捧げている。さらには盟友である大谷吉継、島左近、真田昌幸・信繁父子、上杉景勝・直江兼続主従は西軍として三成に味方している。しかも大谷吉継と島左近はここで討ち死にを果たしてもいる。
さらには三成に恩を感じていた佐竹義宣も明確に東軍に味方することはせず、再び三成を助けるために上杉家と密約を結んでいたとも伝えられている。果たして三成が現代に伝わるような冷徹な人間であったなら、彼らのような名将たちが天下を分ける関ヶ原で西軍についていただろうか。
家を守るためには手段を選ばず、秀吉に「表裏比興の者」と称された真田昌幸でさえ西軍に味方しているのだ。恐らく昌幸は
忍城の水攻めでの三成の働きを間近で見て感銘を受けたことにより、西軍の勝利に賭けたのだろう。
「三成は嫌われ者だった」というイメージは完全に間違っている。もし本当に嫌われ者だったとすれば、わずか19万石の小大名に過ぎなかった三成が、関ヶ原の戦いのために8万人以上の兵を集めることなどできなかったはずだ。西軍に味方した大名たちは「三成だからこそ」味方したのだ。
三成の人柄を言い表すならば、取っ付きにくいが話してみると良い奴、と言った感じだったのだろう。そして弁明などは一切しない人物だっため、誤解をされてもその誤解を自ら解くことはほとんどなかったようだ。それによって誤解が誤解を生み、武断派武将たちを敵に回してしまった印象も強い。
だが石田三成が処刑されてからもう400年以上が経過している。そろそろ三成の誤解をすべて解いてあげてもいいのではないだろうか。
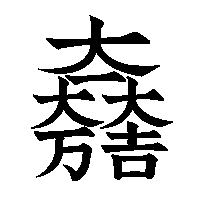
忍城の水攻めに失敗した石田三成だが、実はこの当初、三成を悪く言う者はいなかった。徳川四天王のひとりである榊原康政も、三成と共に忍城を攻めた浅野長吉への書状で「お手柄」と書いているほどだ。やはり三成の戦下手という評価は江戸時代に恣意的に作られたものだと考えるべきだ。
備中高松城を水攻めした際に作られた堤は東南4キロに渡って築かれた。つまり備中高松城を水攻めにするには4キロの堤を作れば良かったわけであり、水攻めをするに適した弱点を持った城だった。一方の忍城を水攻めにした際約1ヵ月かけて作られた堤は28キロにも及んだ。備中高松城攻めで築いた堤の実に7倍の長さだ。これだけの堤を作るためには人員や資金ばかりではなく、大量資材や、人員のための大量の食料まで必要になる。それを手際よく用意したのが他でもない、石田三成なのだ。
土木工事も滞りなく進んだと言い、この三成の活躍を間近で見ていたのが大谷吉継、真田昌幸、真田信繁(幸村)、直江兼続、佐竹義宣、長束正家、多賀谷重経らだった。そして面白いのは彼らは皆、関ヶ原の戦いで三成に味方しているという点だ。もし忍城の水攻めの失敗が三成の戦下手や不手際によるものであれば、名だたる名将たちが果たして天下分け目の関ヶ原で三成に味方しただろうか。
大谷吉継や直江兼続のように、三成と親しかった者が味方するのならばまだわかる。しかし秀吉に表裏非興の者とまで言わせた謀将真田昌幸が、戦下手の三成に果たして味方などするだろうか。いや、しないはずだ。真田父子はこの時に三成の手際の良さや、水攻めはすべきではないという三成の冷静な判断に接していたからこそ、関ヶ原では西軍の勝利を予測し三成に味方したはずだ。そうでなければ家を守るためには手段を選ばなかった真田昌幸が三成に味方する理由はない。
忍城内では実は離反の動きも少なくなかったと言う。そのような状態であれば力攻めをすればあっという間に城は落ちたはずだ。その情報も掴んでいたからこそ水攻めにより無駄な労力や無駄な出費をすることなく、忍城を力攻めにすべきだと三成は秀吉に進言したようだ。
結果的に忍城の戦いは天正18年6月17日から始まり、7月5日に小田原城が落ち、成田氏長がそのことを忍城に伝え開城を説得し、城を守っていた成田長親(のぼうのモデル)らが説得に応じ、7月16日に開城された。
忍城水攻めの失敗により三成を責めるべきではない。三成は秀吉に命じられた無理難題を実現させ、たった1ヵ月で28キロにも及ぶ堤を完成させたのだ。三成の手際の良さと政治力がなければ決してなしえなかっただろう。それなのに三成は水攻め失敗の事実を歪曲され、戦下手として周知されるようになってしまった。
なおこの堤は「石田堤」と呼ばれ、現在では行田市から鴻巣市にかけて250メートルだけ現存している。忍城水攻めでは、三成は本来であれば賞賛されるべき功績を残しているのだ。そして秀吉自身この水攻めの段取りは三成にしかできないと思ったからこそ、「水攻めについては全面的に任せた」という書状を三成に送っているのである。