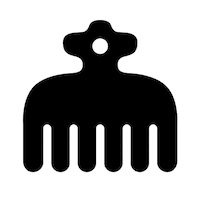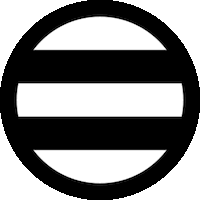戦国大名になるための四つの方法
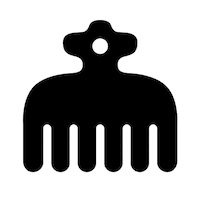
戦国時代に活躍した者たちとして、まず挙げられるのが大名たちです。戦国大名として有名なのは織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、毛利元就、今川義元、武田信玄、上杉謙信などなど、挙げ始めると実に切りがないほどです。
では大名とは何を以って大名と呼ばれたのかと言うと、一般的には二郡以上支配する者が大名と呼ばれたようです。戦国時代は今で言う都道府県を「郡」という単位で分割していたのですが、その郡を二郡以上支配できるようになると戦国大名と呼ばれるようになります。
例えば元々は国人衆の一つだった毛利氏ですが、毛利元就の才覚によって毛利家は国人衆としてどんどん力を付けていきました。その結果二郡以上支配するに至り、さらには他の国人衆を従属化させることで一国人衆から戦国大名へとのし上がっていきました。
ちなみに鎌倉時代を経て、戦国大名へとなっていく方法は主に四つです。一つ目は鎌倉時代より将軍家から守護大名に任命されており、それがそのまま戦国大名になったパターンです。今川氏、武田氏、島津氏がこのパターンですね。ちなみに鎌倉時代には本来守護大名は在京している必要がありましたが、戦国時代になると在国と言って京にはおらず、それぞれの国にいながら政をし、財力・戦力の強化に勤めるようになりました。
二つ目のパターンは守護代から戦国大名に成り上がるパターンです。織田氏、上杉氏、朝倉氏がこれに当たります。守護代というのは、守護大名が在京している際にその国の政を担う、言わば代理監督のような存在でした。尾張の守護大名は斯波氏でしたが、尾張の守護代を務めた織田氏がどんどん財力を付けていき、それに伴い軍も強化され、守護大名であった斯波氏の力を上回ってしまったことで斯波氏は淘汰されていき、自然と織田氏が斯波氏と代わるようにして尾張の戦国大名となっていきました。
三つ目のパターンは国人衆や地侍から成り上がっていく、上述の毛利氏のパターンですね。そして四つ目は下剋上です。例えばマムシと呼ばれた斎藤道三は主家である土岐氏を攻め、土岐氏を尾張に追放することによって美濃国を乗っとりました。以上が戦国大名になる主な四つのパターンです。
守護大名と戦国大名の違い
そして鎌倉時代から続く守護大名と戦国大名は何が違うかと言うと、守護大名は常に幕府の権威に依存していましたが、戦国大名は独自に国力を付けていきました。例えば元々は守護大名である今川氏などは、鎌倉時代にはあくまでも幕府から駿河国などを預かっているという立場で、幕府の意向に沿わない行動を取ることはできませんでした。
一方幕府の力が弱体化して来た戦国時代では、幕府の権威は尊重しながらも、大名たちは幕府に依存することはありませんでした。例えば織田信長が将軍足利義昭の権威を天下取りの道具として使っていた事例などは、まさにそれを象徴しています。
また、上述の通り守護大名は在京している必要がありました。つまり京にいる将軍のお側に常にいなければならなかったわけです。しかし戦国大名は、かつては守護大名だった武田氏も今川氏も京を離れ、それぞれの国に居を構えていました。
そして法律に関しても、戦国大名は自らの領地で勝手に法律を策定し、独自のルールで国を支配して行きましたが、守護大名の場合は室町幕府が定めた通りにそれぞれ任された国を支配し、勝手に独自のルールを作ることは許されてませんでした。このあたりが戦国時代以前の守護大名と、戦国大名の大きな違いだと言えます。

雨の桶狭間でじっと好機を覗っていた織田軍
永禄3年(1560年)5月19日、東海一の弓取り(武将)と称されていた今川義元が、約2万の軍勢を率いて尾張に侵攻してきた。一説ではこの時、義元は上洛の途上だったとされているが実際はそうではなく、信長が今川領への圧力を増していたことから、早いうちに信長を潰しておこうという義元の考えだったようだ。つまり目的は上洛ではなく、信長の居城である清洲城への侵攻だったのだ。
今川軍が織田領の丸根砦、鷲津砦を攻め始めたのは5月19日未明のことだった。この報告を受けると信長は敦盛を舞い、陣触れし、清洲城を飛び出して行く。向かったのは熱田神宮で、ここで必勝祈願を済ますと戦場へと再び馬を駆けて行った。
19日未明は暴風雨だった。織田軍2,500の寡勢が今川軍2万の大軍を攻めるためには、悪天候に乗じて奇襲をかけるのが常套手段だ。だが信長は雨が上がるまで攻撃は仕掛けなかった。その理由は『松平記』で説明されており、この時今川勢として参戦していた松平元康(後の徳川家康)は、織田軍は突如として鉄砲を打ち込んできたと書き残している。当時の火縄銃は濡れてしまっては撃つことができない。そのため信長は雨が上がるまで攻撃を待ったのだ。
雨が上がると織田軍は、今川義元の本陣目掛けて一気に斬り込んでいった。なぜこの時織田軍が迷わず本陣を攻められたかといえば、義元が漆塗りされた輿に乗って来ており、その目立つ輿が信長に義元の居場所を教えてくれたためだった。ちなみに漆塗りの輿は、室町幕府から許可されないと乗ることができない当時のステータスだった。現代で言えばリムジンを乗り回すようなものだ。
奇襲の常套手段を用いずに奇襲をかけた織田信長
周辺の村から多くの差し入れもあり、正午頃、今川本陣はかなりのリラックスモードだった。丸根砦と鷲津砦もあっという間に陥落し、今川の織田攻めは楽勝ムードだったのだ。しかも暴風雨が止んだことで、兵たちは奇襲に対する緊張も解いてしまう。なぜなら上述した通り、雨に紛れて奇襲をかけるのが当時の常套手段だったからだ。だが雨が止んだ空の下、突如として織田軍が鉄砲を打ち込んできた。織田軍はここには攻めて来ないと踏んでいた今川本陣は慌てふためく者ばかりで、武器や幟などを捨てて敗走する兵も多かった。
義元自身、300人の護衛と共に本陣から逃げ出すのがやっとで、その護衛も最後には50人まで減っていた。そして最初に義元に斬り掛かった一番鑓の武功は服部一忠だった。一忠は義元に膝を斬られ倒れてしまうが、直後に毛利良勝が二番鑓として義元の首を落とした。
毛利良勝が義元を討ち取ったことにより午後4時頃、桶狭間の戦いは幕を閉じる。2,500人の織田軍が討ち取った今川兵は3,000にも上った。信長の勝因はまずは雨が止むのを待って鉄砲を用い、兵をすべて今川本陣に一極集中させたことで、一方義元の敗因は大軍を分散させ、さらに輿により自らの居所を信長に教えてしまったことだった。
この桶狭間での勝利を境に信長は天下へと駆け上り、逆に敗れた今川家は滅亡へのカウントダウンが始まり、この8年後に大名としての今川家は滅亡してしまうことになる。
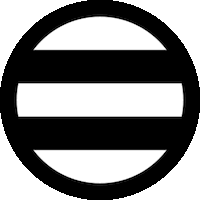
麒麟がくる第6回「三好長慶襲撃計画」は、ほぼ全編フィクションで話が進められたのではないだろうか。劇中の出来事を追っていくと時系列が明確になっていなかったり、年齢設定が正確ではないように感じることが多くなってきた。例えば劇中は天文十六~十七年(1547~1548年)あたりを描いていると思われるが、この頃の第十三代将軍足利義輝はまだ13~14歳程度でしかない。劇中の将軍はさすがに14歳には見えなかったのではないだろうか。
三好長慶の暗殺が企てられた連歌会
さて、今回は細川晴元が画策した連歌会に三好長慶が招待され、そこで長慶が暗殺されそうになるという場面が描かれていたが、この出来事もフィクションではないだろうか。確かに細川晴元と三好長慶という主従の間にはいざこざが生じていた。だがこのような連歌会で暗殺が企てられたという事実は筆者はまだ読んだことがない。確かに戦国時代にはよくある話のようにも見えるため、「絶対にそんな事実なかった」とは言い切れないが、しかしあくまでもこれはフィクションの枠の中に納まっていくは思う。
足利義輝は天文十六年(1548年)7月19日に細川晴元によって京を追われ近江国坂本に父義晴と共に落ちている。その10日後両者は和睦し、義輝も京に戻ってはいるのだが、劇中に描かれたのはこの直後の出来事ということになるのだろう。この時の義輝は確かに細川晴元に対し良い心象は持っていなかったはずだ。そのため三好長慶・松永久秀という細川晴元にとっての天敵(実際には晴元の家臣)に手を差し伸べたことにも理解は示せる。だが義輝の立場は常に不安定だったと言える。
劇中この時代の足利義輝はまだ子供だった
細川晴元は細川家嫡流の名門中の名門だった。同じ苗字の細川藤孝(細川護熙元総理はこちらの血筋)とは異なる細川家であり、細川晴元の細川家は、まさに将軍直属の重臣(室町幕府の官領職)だった。立場的には足利義輝の下に細川晴元、その下に三好長慶(晴元の家臣)、三淵藤英(幕府奉公衆)、細川藤孝(幕府警護役)という形になる。だがこの頃の力関係は細川晴元の臣下である三好長慶が勢力を増してきており、細川晴元にとっては頭痛の種になっていた。それ故の暗殺未遂という描かれ方だったのだろう。
この頃の足利義輝はまだ若年だったこともあり、書状にされそれほどの効力はなかった。そのため大御所として義輝を支えようとした父第十二代将軍義晴や、母慶寿院の署名で書かれることも多かったという。つまりこの頃の義輝はまだそれほど幼かったはずであり、明智光秀が三淵藤英を説得しようとする熱弁を耳にし、それに心を打たれ威風堂々「あの者(光秀)の後を追え」と即興の判断などできる年齢には至ってはいなかった。しかし劇中では能をも楽しむ姿が描かれていた。ちなみに足利義輝となるのは天文二十三年(1554年)であり、それまでは足利義藤という名前だった。
筆者が今一番気になるのは遊女タケの存在
この暗殺を止めようとする光秀だが、もちろん明智光秀が三好長慶と松永久秀を救ったという史実は存在しない。いや、もしかしたらあったかもしれないが、少なくともそれを示す資料は残されてはいない。また、実際には明智光秀と細川藤孝が出会うのは、光秀が美濃を追われ越前に逃れたあとだと思われる。
さて、筆者はタケという人物が今非常に気になっている。劇中のタケは恐らくは伊平次と一緒にいる遊女だと思われるが、実は史実の光秀は越前の竹という人物に世話になったとされている(光秀は竹を助けた服部七兵衛尉に感謝の書状を認めている)。このタケがその竹なのかはわからないが、しかし史実と名前が被っているだけに筆者は個人的には非常に気になっている。もしかしたらこの遊女は越前の人間であり、光秀が越前に逃れた後、もしかしたら劇中で重要な役どころになってくるのかもしれない。いやしかし、ただ偶然名前が被っただけかもしれない。これもまたドラマを見続ければ見えてくるのだろう。


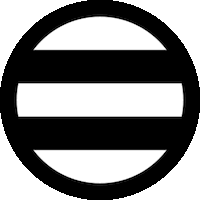
戦国時代のドラマを見ていたり、小説を読んだりすると必ず「上洛」という言葉が出てくるわけだが、果たして上洛とは一体何のために行われていたのか?そして上洛の意味はどこにあったのか?
各国に派遣された元々は外様だった守護大名
上洛について話をする際、まず考えなければならないのは室町幕府についてだろう。室町幕府とはいわゆる足利幕府のことで、戦国時代であれば足利義輝や、室町幕府最後の将軍となった足利義昭などが首長を務めていた幕府のことだ。足利幕府は元来、二十一屋形と呼ばれた各国の守護大名たちと相互関係を結びながら成り立っていた。そして守護大名は本来、洛内(京の都)にいることが義務付けられていた。
守護大名とは足利家の系譜にある人物が、その地を治めるために将軍によって各国に派遣された立場の人物のことだ。そのためその土地とは無縁の者ばかりで、それ故できるだけ早くその土地に馴染もうとし、守護大名たちはその土地の地名を名字に用いることが多かった。このように元々はその土地に所縁のない守護大名だったが、土地を治める年数が長くなるにつれ、その土地の有力者たちの厚い支持を得られるようになって行く。
そうなってくると元々は外様だった守護大名たちも力や経済力を持つようになり、次第に規則を破って洛内を出て下国(げこく:京から自らが守護している国に帰ること)してしまう守護大名が増えていった。そして戦国に世ともなると、洛内になお留まる守護大名はほとんど細川家だけになってしまう。
上洛とは?
将軍家直属の軍隊は1000~2000人程度の規模でしかなかった。この勢力だけではとてもじゃないか謀反や大規模な一揆を抑え込むことなどできない。そのため何か問題が起こると、将軍家は守護大名たちに出陣の要請を出し、それぞれの小規模な軍隊を集結することによって大軍隊を編成していた。だが上述の通り、戦国時代になると洛内に留まっていたのは細川家だけで、足利家は細川家だけを頼らざるを得ない状況に陥っていた。
ただ、その状況は戦国時代に突入する以前から続いており、もし細川家が衰退してしまったら、足利家も滅びの道を辿る運命にあった。それを防ぐために将軍は下国してしまっていた守護大名たちに、幕府に協力するように要請を出していた。その要請に応えて京の都に戻ろうとすることを「上洛」と言った。
では戦国時代において、大名が上洛する利点はどこにあったのだろうか?それは守護職を維持することや、官位を賜ることにあった。幕府から守護職や官位を賜ることにより、大名は幕府という大きな後ろ盾を得られるようになる。守護職=幕府に認められた大名、となるわけで、これによって国衆や有力者などの支持を集めやすくなり、治政も行いやすくなった。過去には守護職を剥奪されて衰退していった大名家もあるため、各国の大名たちはどうしても守護職を失いたくなかったというわけだ。ちなみに武田信玄は甲斐と信濃の守護職を務め、上杉謙信は越後の守護代を務めていた。織田家に関しては尾張守護職である斯波家(三官僚と呼ばれた名家中の名家)の家臣で、ただの奉行でしかなかった。そのため上洛してもなお、武田や上杉などから「田舎大名」と揶揄されることになる。
幕府の役割とは?
さて、幕府の長である足利将軍は一体どのような役割を担っていたのか?「戦国時代の将軍様はお飾りでしかなかった」と言われることもあるが、実際はそんなことはなかった。確かに力を失いつつあったという現実に間違いはないわけだが、しかし将軍の存在意義は戦国時代においても非常に大きかった。だからこそ武田信玄や上杉謙信という超大物であっても、上洛の要請にはしっかりと応じている。
将軍とは、今でいう最高判事のような存在だった。幕府の最大の役割は調停にあり、何か問題が起こると幕府に訴状を提出して裁定を仰ぐというシステムになっていた。つまり幕府とは最高裁判所のような存在だったわけだ。だが力を持った大名たちは問題を自分たちで解決できるようになり、幕府を頼ることも少なくなり、それによって幕府は資金源を失い始め力を失っていたというのが戦国時代においての室町幕府だったようだ。
織田信長が上洛するまでは、経済力を失っていた室町幕府のある京の都は荒れに荒れていた。とても都と呼べるような状況ではなかったわけだが、そこに登場し京の都を再建することによって織田信長はあっという間に幕府の信頼を得ていった。だがこの頃になると頼りの細川家も完全に力を失っており、その細川家はもはや織田の軍門に下っていた。
実は本来世襲制ではなかった守護職
室町幕府最後の将軍となった足利義昭の時代になると、室町幕府を支える家は完全に織田の一強となっていた。そして信長は思いのままに将軍と幕府を利用しようとし、それを嫌った足利義昭が各大名に上洛を求める書状を乱発していった。この義昭の要請により信長は幕府の救世主から朝敵という立場にされ、武田信玄や上杉謙信もその朝敵を討つという大義名分を得て、織田を討つために上洛を目指した。
大義名分という意味では、まだ義昭が将軍になりたての頃、信長は上洛の要請に応じなかった朝倉義景を将軍家に対する謀反者と断罪し、その謀反者を成敗するという大義名分を得ることにより、越前へ侵攻していった。戦国時代において大義名分は非常に重視されており、織田信長でさえも戦を仕掛ける際には必ず大義名分を用意していた。
上洛とはこのように、大義名分として利用されることも戦国時代には多かった。さて、最後にもう一点付け加えておくと、実は守護職というのは元々は世襲制ではなかった。だが長期間にわたり国替えが行われなかったために各守護大名たちが力をつけてしまい、徐々に幕府の手に負えなくなっていった。もし幕府が数年に一度転封(国替え)を実施していたら、室町幕府もまた違った終焉となっていたのだろう。

『惟任退治記』とは、天正10年(1582年)10月15日に行われた織田信長の葬儀の直後、織田信長がどのようにして明智光秀に討たれ、どのようにして羽柴秀吉が光秀を討ち信長の仇を取ったのかということを、秀吉が大村由己(おおむらゆうこ)という御伽衆に書かせた軍記物だと伝えられている。軍記物とは現代でいうところの歴史小説のようなもので、ノンフィクションではなく、フィクションも多分に含まれている。そのため歴史研究においては、ノンフィクションのみが記されていると思われる日記や書状などを一次資料と呼ぶのに対し、フィクションも含まれている軍記物は二次資料と呼ばれている。
ただ、軍記物といっても100%フィクションというわけではなく、史実通りのことが書かれていることが多いのは現代の歴史小説と同様だった。ただ、書いた者や書かせた者の主観が含まれることが多いため、事実が捻じ曲げられていたり、物語そのものが創造されていることも多い。だがそのあたりを踏まえて読んでいくと、軍記物は歴史ファンにとっては非常に楽しめる読み物だと言える。今回、戦国時代記では『惟任退治記』という、12編からなると言われている『天正記』の1編を、現代語訳どころか、現代小説風に書いてみたいと思う。言葉遣いなどはまさに現代小説風になっていくが、書かれている内容や意味は、原文通りにし、筆者の脚色等は一切排除した内容にしていきたい。
惟任退治記(1)皇居が移動して来たかのように賑わう安土城
世間というものは栄えたり衰えたりということを繰り返すことによって成り立っている。南山(なんざん:高野山のこと)の春の花は咲き誇ったかと思えば逆風により散っていき、東嶺(とうれい:京都の東山のこと)に美しい秋月が見えたかと思えば厚い雲がそれを覆い隠してしまう。そして力強く根を張る樹齢長き松の木でさえも伐採されることを自ら避けることはできず、寿命万年といわれる亀でさえもいつかは死んでしまう。また、朝顔の花に落ちる露や、荘子が見たという自ら蝶となり花の上で100年遊んだという夢の目覚めのように、世の栄華というのは実に儚い。
亡くなった後に太政大臣に叙せられた織田信長公は、長きにわたり日ノ本のリーダーとして国家を主導してきたが、その亡くなる前、信長公は近江の安土山に城郭を築いた。大きな石で土台が作られた建物の屋根が連なり、天守閣は天まで届きそうなほどに高くそび、それら煌びやかな建物が鏡面のような琵琶湖の水面に映り、その美しさは言葉で表すことなどできない。
恐れ多くも正親町天皇をはじめとし、朝廷に仕える公家たちも身分の上下問わず、毎日のように信長宛てに連絡を入れ、続々と安土城に集まってきた。その様子はまるで皇居が安土城に移動して来たかのようだった。三管領と呼ばれた室町幕府の名家、斯波家、細川家、畠山家の人間で、信長公を崇拝しない者は誰一人としていない。そして信長公は彼らと、100羽の鷹を集めて鷹狩りに出かけたり、千とも万とも言われた数の馬を集めて馬揃え(軍事力を誇示し諸大名に力を見せつけたり、軍の士気を高めるために行われた一大行事)を行った。
朝廷の者たちは、私欲のない清らかな政治を志し、曲がったことは正すと言いながらも、夜になると奥に控えていた3000人の美女たちを欲しいままにした。正しいことを行うと言いつつ毎夜催された宴は、いくら楽しんでも尽きることがなかった。唐(とう:中国の王朝名)の玄宗皇帝が所有していた温泉付きの驪山宮(りざんきゅう)や、洛陽(らくよう:中国河南省の非常に栄えていた都市)の上陽殿(宮殿)の娯楽でさえも、安土城の物ほどではなかっただろう。


惟任退治記全文掲載

永禄10年(1567年)11月、この頃初めて織田信長が「天下布武」の朱印を使い始めたとされている。一般的には「武力を以って天下を治める」と理解されているが、しかし実際にはそういう意味ではなかった。この言葉は臨済宗妙心寺派である沢彦宗恩(たくげんそうおん)が信長に進言したとされているが、しかし実際にそうであったという明確な記録が残っているわけではないようだ。
天下布武、岐阜命名は沢彦の助言によるものだった
沢彦宗恩は、吉法師(幼少時の信長)の守役であった平手政秀と親交があったことから、その平手政秀の推薦により吉法師の教育係に任命された僧侶だった。そして平手政秀が信長の蛮行の責任を取る形で自刃(自刃の理由は諸説あり)を果たした後も、信長の相談役として仕え続けた。天正15年(1587年)に死去したことはわかっているが、しかし生まれた年などの記録はまったく残っておらず、よく名が知られた戦国時代の僧侶であるにも関わらず、非常に謎が多い人物でもある。
一部ではこの沢彦が「天下布武」という言葉を信長に進言したとされているが、実際にそうだったのかはもはや誰にもわからない。だが常時信長の側に仕えていたことは事実であるため、今日ではその可能性が高いと考えられている。ちなみに稲葉山という地名を岐阜に変えた際の助言も沢彦が信長に与えており、この時沢彦は岐阜、岐山、岐陽という三案を伝え、その中から信長が岐阜を選んだとされている。
天下布武とは武力で天下を治める、という意味ではなかった?!
さて、ここからが本題であるわけだが、「天下布武」とは決して武力を以って天下を治めるという意味ではない。ではどういう意味かというと、「足利将軍を中心にし、乱れていた畿内の秩序を取り戻す」という意味となる。天下というのは日本全国ではなく、政の中心地だった畿内のことを指し、武とは武家、つまり足利将軍のことを指している。
この頃の信長は多くの書状に「天下布武」の朱印を使っているわけだが、仮に「武力を持って天下を治める」という意味であったなら、信長はこの朱印を用いることで、全国の大名たちに宣戦布告していた、ということになる。だが実際には宣戦布告として受け取られることはなく、戦国時代では「天下=畿内」「武=足利将軍」という意味はごく一般的な言葉として使われていたようだ。
天下布武から天下静謐へ
信長は永禄11年(1568年)に足利義昭を奉じて上洛を果たしている。つまり第13代将軍足利義輝が松永久秀と三好三人衆の陰謀により殺害され、その後義輝の従兄弟である足利義栄が第14代将軍の座に就くも約半年ほどで死去したことにより乱れ切っていた畿内の秩序を、信長はその時に取り戻したということになる。これによって天下布武は達成されたと考えることができる。
そしてあまり知られてはいないが、信長は「天下布武」を成した後は「天下静謐(せいひつ)」を自らの政治的標語としている。天下静謐とは、取り戻した秩序を維持するという意味だ。信長と義昭の関係が良好だった頃は、義昭が政治面での静謐、信長が軍事面で静謐を担う分業制を敷いていた。だが仲違いし義昭を追放した後は、信長は天下静謐を全面的に自らの職責としていく。
最後に一点付け加えておくと、信長は義昭を利用し、義昭も信長を利用していたとよく言われるが、しかしこれは信長と義昭に限った話ではない。室町幕府では将軍家とそれを支える大名家、つまり細川氏や六角氏などは、お互いにお互いを利用し合うことで力を維持してきたという歴史がある。つまり信長と義昭がお互いを利用し合ったことは、当時の将軍家と有力大名の間ではごく自然なことだったということを伝えて、この巻を締めくくることにしたい。