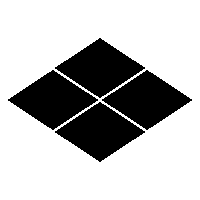
織田信長や上杉謙信が恐れた武田勝頼
武田勝頼の最期は実に呆気ないものだった。父信玄の従甥であった小山田信茂の裏切りに遭い、最期は一説によれば100人にも満たない僅かな共の者と逃げ場を失い、天目山で自害したと伝えられている。勝頼のこの自害により、450年続いた甲斐武田氏は信玄亡き後あっという間に滅亡してしまった。だからと言って、武田勝頼は決して愚直な武将だったわけではない。
事実信玄の死後は強過ぎる大将と謳われるほどの戦いを見せていた。だが負け知らずであったがために勝頼のプライドはどんどん高くなってしまったようだ。本来は退くべき戦を退かずに挑んでしまった。勝者の奢りとも言うべきだろうか。重臣たちはしきりに退くことを提言したが、しかしここで退いてはは武田の名が廃るとばかりに、勝頼は無謀な戦いに挑んでしまう。それが長篠の戦いだった。
織田信長は上杉謙信に対し「勝頼は恐るべし武将」と書状を書き、謙信もそれに異論はなかったようだ。長篠の戦いは1万5000の武田勢に対し、織田徳川連合軍は3万8000だった。数の上では織田徳川連合軍が圧倒的に上回っている。しかし信長はそれでも勝利を確信することができなかった。
そのため佐久間信盛に武田に寝返った振りをするように命じた。勝頼はあろうことかこれを信じてしまい、戦いが始まれば織田方の重臣である佐久間信盛が内応することを前提に戦いに挑んでしまった。つまり武田勝頼は長篠では織田方に騙され、天目山では血族である小山田信茂に裏切られたことになる。武田勝頼は織田信長や上杉謙信が恐れる名将ではあったが、生きるか死ぬかの戦国時代に於いては人を信じ過ぎたことが仇となってしまった。
武田信玄は『孫子』を熟知する軍略家だった。しかし勝頼はこの時『孫子』を無視した状態で戦に挑んでしまう。もし勝頼がもっと織田方が整えていた準備を把握できていれば、武田軍に勝ち目がないことは火を見るよりも明らかだった。だが勝頼は最強の武田騎馬軍団を過信してしまい、信長の誘いに乗り沼地の多い設楽原(したらがはら)に陣を敷いてしまった。沼地ではいくら最強と言えど、騎馬軍団の威力半減してしまう。
一方の織田徳川連合軍が沼地の先に用意していたのは馬防柵だった。騎馬隊が侵攻できないように木でフェンスを作り、その隙間から鉄砲を撃てるようにしていた。この戦略により武田騎馬軍団は一網打尽にされてしまう。
天正3年(1575年)5月21日、早朝に始まった死闘は8時間にも及んだという。だが武田軍に勝機はなく、この戦いで土屋昌次、山縣昌景、内藤昌豊、原昌胤、真田信綱・信輝兄弟(ふたりとも真田昌幸の兄)が討ち死にし、撤退時に殿(しんがり)を務めた馬場信春も、勝頼が無事に撤退したことを知ると討ち死にしてしまった。たった一度の戦でこれだけ名のある武将たちが次々命を失った戦も珍しい。
この敗戦により武田家は一気に衰退していき、天正10年(1582年)3月11日、天目山の戦いで勝頼が自害したことにより、名家武田氏は歴史からその名を葬られてしまった。
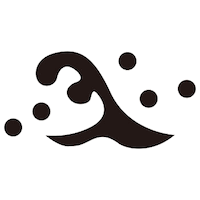
『麒麟がくる』第2回「道三の罠」では、冒頭から終始斎藤軍と織田軍の合戦シーンが描かれた。斎藤道三と織田信秀(信長の父)の時代には、このような戦いが幾度もあったわけだが、しかし信秀は生涯最期まで稲葉山城を落とすことができなかった。この稲葉山城は難攻不落の城と呼ばれ、織田信長でさえも桶狭間の戦い以降何度も美濃に侵攻したが、実際に美濃を手中に収めたのは永禄10年(1567年)だと言われている。
斎藤義龍は側女の子だった?!
劇中で稲葉山城はただの砦のように描かれているが、実際にはもう少し城っぽい形状だったとされている。しかしさすがに城を再現することは困難なため、城そのものはほとんど描写せず、城下町や砦のみを描く形に留まっているのだろう。だが今後話が展開していき、織田信長が稲葉山城を岐阜城と改めた時に、岐阜城の姿も映し出されるのではないだろうか。
さてその劇中、のちの斎藤義龍である斎藤高政が「自分は側女(そばめ)の子だから父は私の話に耳を貸さない」と語っていた。この台詞は後々重要な意味を持ってくるはずだ。ネタバレになりすぎないようにここではあえて書かないが、ぜひこの台詞は覚えておいてもらいたい。きっと後々の放送で大きな意味を持ってくるはずだ。
『孫子』が頻繁に登場する『麒麟がくる』
斎藤利政(のちの斎藤道三)はこの戦の前、明智光秀と叔父の明智光安に孫子について尋ねている。光安は答えられなかったが、光秀はすらすらと答えていた。『孫子』謀攻編に出てくる「彼を知り己を知らば、百戦して危うからず(危の実際の漢字は、かばねへんに台)」という言葉を引用しているが、これは敵のことも味方のこともしっかり把握し切れていれば、百度戦をしても大敗することはない、という意味になる。
ちなみに劇中で利政は最初は応戦させたがすぐに籠城させ、織田軍に戦う意思がないように思わた。そして織田軍が、斎藤軍に忍ばせていた乱破(らっぱ)の情報からそれを知り兵たちが油断し始めると、利政は猛攻をかけ織田軍を大敗させた。ちなみに劇中では乱破がスパイのように描かれているが、実際の乱破は闇夜に紛れて敵を討つ忍び集団だったと言われている。スパイを表現するのであれば、間者(かんじゃ)や間諜(かんちょう)の方が筆者個人としてはしっくり来る。斎藤利政が仕掛けたこの、能力がない振りをして相手を油断させて討つことを、『孫子』計編で「兵とは詭道(きどう)なり」と言っている。
「兵とは詭道なり」とは、戦とは騙し合いであって、本当は自軍にはその能力があるのに、実際にはないかのように振舞って相手を油断させて敵を撃退するという意味だ。ちなみにこの戦法が最大限活かされたのが、本巻では詳しくは書かないが桶狭間の戦いだった。さて、『孫子』からもう一遍。今回の戦で利政は籠城する意図を誰にも話さなかった。そして籠城を解く時になって初めて諸将にその意図を伝えている。『孫子』ではこれを「能(よ)く士卒の耳目を愚にして」と説いている。これはいわゆる、敵を騙すならまずは味方から、という意味になる。
土岐家と織田家は本当に強い絆で結ばれていたのか?!
最後にもう一点、劇中では美濃守護である土岐家と尾張の織田家には強い絆があると描かれている。この台詞だけだと深いところまで知ることはできないが、実際には決して絆があったわけではない。劇中で伝えられている通り、斎藤利政は美濃守護の土岐頼芸(劇中では「よりのり」と読むが「よりあき」など読み方がいくつか存在している)を武力で追放して美濃を手中に収めたわけだが、尾張の織田信秀は追放された頼芸を美濃守護に戻すという大義名分を得るために、頼芸を利用していただけだった。
仮に信秀が稲葉山城を落とせていたとしても、美濃を土岐家に返還するようなことは決してしなかっただろう。つまり土岐家と織田家の間には絆などなく、織田家が土岐家を利用していただけだった。これは織田信長と足利義昭の関係にもよく似ていて、戦国時代はこのような形で大義名分を作り戦を仕掛けることがよくあった。
以上が『麒麟がくる』第2回「道三の罠」を見た筆者の感想と、解説とまでは言えないが、解説のようなものとなる。ところで、前回放送後の予告編のような部分と、実際の今回の内容がけっこう違っていることに少し驚いたのだが、これは昨年起きた出来事による影響なのだろうか。筆者はてっきり、第2回放送で光秀が妻を娶り、今川義元も登場してくるものだと思ったのだが、そうではないようだ。とは言え、第3回放送も心待ちにしたい。



戦国時代を語るにあたり必ず登場するのが軍師の存在だ。竹中半兵衛、黒田官兵衛、直江兼続、山本勘助、立花道雪ら戦国時代にはその他にも名だたる軍師たちの存在が多く見て取れる。だが戦国時代そのものにはどうやら軍師という役職は存在していなかったようだ。
江戸時代後期や明治時代になると歴史小説が読まれるようになり、それらの小説により軍師という言葉は一般的になった。そしてそれらの小説に軍師という言葉が登場するきっかけとなったのは、江戸時代以降の軍学者たちによる研究結果だった。学者たちは大名に様々な知恵を提供する役割を担った人物のことを軍師と呼ぶようになり、それが小説の世界へと広がって行き、一般的にもよく知られる言葉となっていった。
歴史ドラマではたまに軍師のことを「軍師殿」と呼ぶシーンが描かれているが、どうやら実際にそのように呼ばれることはなかったようだ。例えば直江兼続のように守護職を持っている人物の場合は「山城守(やましろのかみ)」や「山城」と呼ばれていた。一方竹中半兵衛のように役職に関心のない人物は「半兵衛殿」「竹中殿」と呼ばれていた。
ここでは便宜上「軍師」という言葉を使うが、室町時代から戦国時代初期にかけての軍師は、占い師的な要素が強かった。例えば奇門遁甲などを駆使し方角や運勢を読み、運を味方に付け戦に勝つ手助けを行なっていた。いわゆる陰陽師のような存在だ。
そのため特に戦国時代初期の軍師は、実際には陰陽師ではないが、陰陽師をルーツにするような僧侶などの修験者(しゅげんじゃ)が務めることも多かった。例えば今川義元を支えた太原雪斎(たいげんせっさい)や、大友家を支えた角隈石宗(つのくませきそう)のような存在だ。だが戦国時代が中期に突入すると『孫子』などの軍学に精通した人物が軍師として重用されるようになる。羽柴秀吉を支えた竹中半兵衛や黒田官兵衛のような存在だ。
これが戦国時代も末期に差し掛かり戦が減って行くと、軍学を得意とする軍師の役割も減って行く。その代わりに台頭してくるのが吏僚型の軍師だ。
石田三成や大谷吉継のような存在だ。彼らは戦のことももちろん学んでいるが、それ以上に兵站(兵糧)の確保や金銭の管理に大きな力を発揮した。特に石田三成は近江商人で有名な土地で生まれ育ったため算術を得意としており、豊臣秀吉が仕掛けた朝鮮出兵などでは後方支援として大きな役割を果たした。
ちなみに日本最初の軍師は吉備真備(きびのまきび)という人物だ。奈良時代(700年代)の学者で、中国の軍学を学ぶことによって戦術面に貢献するようになり、藤原仲麻呂が起こした乱を巧みに鎮圧したことでも知られる人物だ。その後鎌倉時代から南北朝時代に入って行くと、今度は楠木正成という軍師が登場する。楠木正成は、戦国時代で言えば真田昌幸のようなゲリラ戦法を得意とする軍師だった。
強い忠誠心を持っていたことから、戦国時代にはヒーローとして崇められ、例えば竹中半兵衛などは「昔楠木、今竹中」「今楠木」となどと呼ばれ、その高い手腕が賞賛されていた。
軍師とは野球チームで言えばヘッドコーチ、内閣で言えば官房長官のような役割になるのだろう。決してトップになることはないが常にトップの傍らでトップを支え、成り行きを良い方向へと向かわせる役割を果たす。
ちなみに軍師は『孫子』などに精通している必要があるが、現代でMBAを取得する際の必須科目にも『孫子』は加えられている。その孫子(孫武)自身も紀元前500年代に活躍した中国の軍師(軍事思想家)だった。

戦国時代の軍師の存在、意味とは一体どのようなものだったのか。軍師という言葉は歴史ドラマなどでもよく耳にすることがあるが、実際にはどのような役割を担っていたのか。この巻では軍師の役割について詳しく解説してきたいと思います。
まず軍師を英語で言うと「Tactician(タクティシャン)」となり、戦術家という意味になります。つまり軍師を一言で説明するならば、戦術を練る人、ということになります。いわゆる参謀という存在であり、プロ野球チームならば監督が大名ならばヘッドコーチが軍師、総理大臣が大名ならば官房長官が軍師という感じになるでしょうか。
最終的な決断を下すのはもちろん大名や大将の役割です。その大名や大将に対し選択肢を提供するのが軍師の役目でした。例えば城を攻めるならばシンプルな攻城、兵糧攻め、水攻め、火攻めなどなど、どのような戦術を用いれば最も効果的に、かつ効率的に城を落とすことができるのか、それを大名が決断するための情報を提供するのが軍師の役割です。
そのため軍師は圧倒的な情報量を持っている必要がありました。例えば真田信繁(幸村)は情報を集めるために猿飛佐助や霧隠才蔵などの忍者を抱えていたと伝えられています。またその父真田昌幸は、根津のノノウ(歩き巫女)に情報収集をさせていたという説もあります。
軍師は大名や大将から何かを相談されても、その場ですぐに答えられるように圧倒的な情報量と知識が求められていました。知識といえばもちろん『孫子』を始めとする中国の書物への造詣もです。
軍師という存在が目立つようになったのは、戦国時代からだと言います。戦国時代の前期までは軍師は、主に禅僧の役割でした。中国の学問に精通した禅僧が大名の側に控え、知識を提供していたというのが戦国軍師の元々の姿です。その後徐々に自ら勉学に励む竹中半兵衛のような武将が登場し、大名とともに戦う武将型軍師が多くなっていきました。
ちなみに禅僧型軍師として有名なのは織田信長に仕えた沢彦(たくげん、岐阜を名付けた禅僧)などがいます。沢彦などはまさに典型的な禅僧型軍師であり、戦場にまで赴くことはありませんでした。逆に今川義元に仕えた禅僧型軍師である太原雪斎は自ら鎧をまとい戦場にまで赴く勇猛な禅僧でした。
軍師というのはとにかく、大名や大将が欲しいと思った情報を瞬時に提供できる人物だったようです。そしてそれを可能にするためにも情報網を広げ、武芸だけではなく勉学にも勤しむ忙しい毎日を送っていたと言います。竹中半兵衛や黒田官兵衛らは、夜寝る時間を惜しんで本を読んでいたようです。そして『孫子』なども簡単に諳んじられたと言います。
なお戦国時代の武士はだいたい夜8時には寝て、朝4時には起きていたようです。この8時間の睡眠時間を削ってでも勉学や情報収集に努めたのが軍師という存在だったのです。言ってみれば軍師というのは大名にとって、歩く百科事典だったというわけです。
また、戦場での戦術を練るのが得意だった竹中半兵衛や黒田官兵衛などに対し、吏僚型軍師も戦国時代の後期から登場します。それが石田三成や長塚正家ら、算術が得意な人物たちです。そしてその中間的な存在が大谷吉継でした。大谷吉継は戦術にも算術にも長けていたと言われています。
このように戦国時代の軍師には禅僧型、武将型、吏僚型などなど、他にも幾つものタイプがありました。そしてそのタイプは時代と共にニーズが移り変わっていきます。例えば豊臣秀吉の場合、乱世であった頃は竹中半兵衛や黒田官兵衛を重用しましたが、戦が減ってくると黒田官兵衛とは距離を置き、石田三成ら吏僚型軍師を重用するようになりました。
軍師の役割を見直してみると、軍師と呼ばれた人物は非常に忙しい毎日を送っていたようです。なお戦国時代には軍師という言葉はあまり使われていなかったとも言われています。軍師とは江戸時代後期や明治時代から主に使われるようになった言葉であるようで、戦国時代には明確な「軍師」という役職があったわけでは実はないようです。
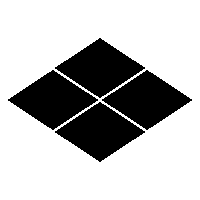
武田信玄は「風林火山」の旗印でも有名な戦国大名であるわけだが、この風林火山とは『孫子』という兵法書に書かれている一節だ。疾きこと風の如し、静かなること林の如し、侵略すること火の如し、動かざること山の如し、という意味となる。戦国時代に『孫子』を愛読した武将は多い。例えば戦わずして勝つことにこだわった竹中半兵衛も『孫子』を学んだひとりだ。
孫子とは簡単に訳すと孫先生という意味になる。つまり『孫子』とは孫先生が書いた兵法書ということだ。だが近年の史家の研究によると、どうやら『孫子』は孫先生、つまり孫武がひとりで書いたものではないらしいのだ。もちろん多くは孫武自身が書いたものとされているが、しかし部分的に文の表現が違うということがわかってきたようなのだ。
となると『孫子』とは、ある意味ではキリスト教の福音書のような存在とも言えるのかもしれない。つまり孫武の弟子たちが孫武から学んだことを、後世になって少しずつ『孫子』に書き加え、長い年月をかけて完成したものが現代に伝わる『孫子』だという可能性があるらしい。確固たる証拠が見つかっているわけではなく、あくまでも史家の文体などの研究結果によるものだが、信憑性は確かに感じられる。
話は少し変わり、ビジネススクールなどで取得できるMBA(Master of Business Administration)という資格がある。日本語で言うと経営学の修士号ということになり、つまりは経営の専門家として認定してもらえる資格となる。現代名の通っている世界的な経営者の多くがこの修士号を取得している。まさにビジネス界の最先端に立つために必要な資格だ。
このMBAを取得するための必須科目に、実は『孫子』が含まれているのだ。『孫子』をビジネスに活かすための書籍やコミックが書店にはたくさん並んでいるわけだが、その理由がここにあるのだ。経営学の専門家になるためには『孫子』を学ぶことが義務付けられている。
『孫子』は紀元前4〜5世紀に書かれたものだとされている。つまり『孫子』とは書かれてから2500年経った今も色褪せていないということになり、その歴史はキリスト教よりも長い。
武田信玄は戦略家として優れた才気を持っていたわけだが、それを身につけるために学んだ教科書が『孫子』だった。現代で言えばソフトバンクを率いる世界的な経営者、孫正義氏もまた、『孫子』を学んだひとりだ。
戦国時代では武田信玄をはじめとし竹中半兵衛、黒田官兵衛、真田幸村などなど、長年かけて『孫子』を学んだとされる武将は多い。武田信玄は最強騎馬軍団を編成し、竹中半兵衛と黒田官兵衛は豊臣秀吉を天下人にした。そして真田幸村は幾度となく徳川家康を苦しめた。
筆者自身『孫子』は長年愛読しており、恐らく過去20冊以上の『孫子』に関する本を読んできたと思う。最後に筆者オススメの読みやすい『孫子』を一冊紹介しておくので、もし興味がある方はお手に取ってみてください。文章も読みやすく、内容もわかりやすく、『孫子』初心者でも楽しめる一冊だと思います。
筆者オススメの『孫子』
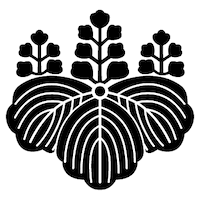
三木城の別所長治はなぜ羽柴秀吉を裏切ったのだろうか。この裏切りが『三木の干殺し』に繋がっていくわけだが、その理由は諸説伝えられている。別所氏の名門意識が百姓上がりの秀吉の下に付くことを嫌ったとか、織田軍の上月城攻めのやり方に反感を持ったなど、信長への信頼感の揺らぎが大きな原因だったようにも伝えられている。
原因はどれか一つではなかったのだろう。いくつもの不安要素が折り重なり、羽柴秀吉に対し反旗を翻す結果になったのだと思う。当初は別所長治も毛利ではなく、織田に味方する姿勢を見せていたのだが、まさかの急展開となってしまった。
羽柴勢による三木城の包囲が始まったのは天正6年(1578年)3月29日のことだった。だが三木城は簡単に攻め落とせるような城ではない。まず城の北側には美嚢川(みのうがわ)という天然の水堀があり、そして城自体も丘の上に建てられているため、下手に攻めれば上から鉄砲や矢の雨が降ってくる。さらには東播磨などから集まってきた7500人もの兵が城を固く守っており、力攻めをしたところで返り討ちに遭うばかりとなる。
この時秀吉の下には竹中半兵衛と黒田官兵衛というふたりの軍師がいた。だが三木城攻めが始まって間もなくすると、今度は攝津有岡城主の荒木村重が信長に反旗を翻す。村重を翻意させるために官兵衛が有岡城を尋ねるのだが、しかし官兵衛は捕らえられてしまい、地下牢に閉じ込められてしまう。
一方の竹中半兵衛は結核を患っており、戦場と病床とを行き来する日々を強いられていた。それでも竹中半兵衛は策を巡らせ、三木城を兵糧攻めにしていく。一説によればこの時、「羽柴軍は別所長治に味方したものは兵士だろうが百姓だろうが構わず皆殺しにする」という噂をわざと流し、百姓たちまで三木城内に駆け込ませたと言う。
すると三木城内は兵だけではなく百姓たちも合わさり、兵糧は見る見る減っていく。そして美嚢川を含めた兵糧の補給路は羽柴勢によりすべて封鎖されており、毛利からの兵糧補給も期待することができない。さらに羽柴勢は周辺の米商人から通常よりも高い金額で米を買い占めていた。これにより三木城内からは米が減っていく一方で、逆に補給路は一切が断たれる形となった。
これらの兵糧攻めを主導したのが竹中半兵衛であったようだ。『
孫子
』の言うところの「戦わずして勝つ」を地で行くような戦法だ。羽柴勢は兵をまったく失うことなく、三木城内の兵士たちはどんどん弱っていく。米が尽きれば兵馬が食べられ、馬もいなくなればそこらへんに生えている草木をも食べ、そして餓死者の肉を貪ってもいたようだ。まさに壮絶な兵糧攻めであり、また生き地獄でもあった。
10日も何も食べていない者ばかりとなり、兵も戦うどころか立ってもいられない状況が続いていた。竹中半兵衛の策略が見事にはまり、天然の要塞と呼ばれた三木城も、内側から見る見る力を失っていく。そして炊飯の煙がほとんど上がらなくなると、秀吉はいよいよ総攻撃を命じた。
だが実際には城は攻めるまでもなく、場内の兵の命を救うことを条件にし、別所長治一族が切腹することで城攻めは天正8年1月17日に終了した。この戦いは実に22ヶ月にも及び、戦国時代で最も長期に渡った戦となった。
ちなみに有岡城に幽閉されていた黒田官兵衛は、天正7年10月19日に無事救出されたのだが、盟友である竹中半兵衛はその救出を見ることなく天正7年6月13日、結核により36年という短い生涯を三木陣中にて終えてしまった。秀吉は京での療養を勧めていたようだが、「戦さ場が死に場所」と自らに定めていた半兵衛はそれを聞かず、三木陣中での最期を選んだのだった。
写真:三木市内にある竹中半兵衛の墓

本能寺の変が起こる少し以前、一説では2〜3年前とも言われているが、織田家臣団の心は信長から少しずつ離れていこうとしていた。怒涛の1570年代は指揮官としての信長に誰もが付いて行こうとしていたが、信長があることを口にし出すと、家臣団の心配はどんどん膨らんでいったようだ。
そのあることとは「唐入り(からいり)」だ。ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスが記した『1582年日本年報追加』と『日本史』に「日本六十六ヵ国を平定した暁には、一大艦隊を編成してシナを武力で征服し、その領土を子息や家臣たちに分け与える」と信長が明言したと書かれている。つまり秀吉が実行に移した唐入りは、実は信長が考えていたことだったというわけだ。
だが家臣団にとって唐入りは不安要素でしかなかった。例え広大な領地を与えられたとしても言葉が通じず、食べ物などの文化もまるでわからない地に移封されれば、それは異国に死にに行くのと同然だった。戦国時代には現代では普通に使われているインターナショナルという言葉など存在していない。そもそも外国がどれくらい存在しているのかも当時の日本人はまるで知らなかったのだ。
『孫子』などを読んでいたため、唐(明)のことはよく知っていた。その当時も唐から渡って来た文化の数多くが日本に根付いていたし、中国や朝鮮から渡って来た茶器も多かったという。そういう意味で唐は親しみのある外国ではあったが、それでも言葉が通じないということは誰しもが知っていることだった。
唐入りに参加したとしても、唐に移封されることだけは避けたい、それが家臣団の正直なところだった。そして『
本能寺の変 431年目の真実 
』を書いた明智憲三郎氏は、これこそが明智光秀が本能寺の変を起こした真の動機だったと言い切る。
政権が長期に渡る場合、将来的には移封されることが一つの前提として考えられていた。例えば本能寺の変を起こす直前、明智光秀は丹波に地盤を築き上げていた。そして明智家をこの地にて磐石なものとしていき、いつかは土岐氏の再興を、と考えていた。だが信長からすれば謀反を防ぐためにも家臣に力を与え過ぎるわけにはいかない。そのため地盤を固める前に移封させ、また地盤を新たに固め直させることを繰り返させ、家臣が必要以上の力を蓄えられない状況を作らなければならなかった。
家臣からすればそれも日本国内なら何とかなる。だが異国となれば話は別だ。言葉が通じなければ善政も何もなく、年貢を納めさせることもままならなくなる。そんな地に行っても家を繁栄させられるどころか、逆に潰してしまう危険性の方が高かった。だからこそ織田家臣団は信長の唐入りに戦々恐々としていたのだ。
そしてその唐入りを阻止しようと実際に行動を起こした人物がいた。明智光秀だ。光秀は信長の腹心だけあり、信長がこのまま日本を平定してしまえば唐入りが避けられない状況になることをよく理解していた。そうなれば織田家で最も力を持っている家臣のひとりである光秀には、真っ先に移封を命じられる危険性があった。
つまり本能寺の変とは唐への移封を阻止し、家を守るため、そして力を蓄えいつかは土岐氏の再興を実現させるため、明智家にとっては必要なことだったのだ。少なくとも明智家を守るためにはそれが最善であると光秀は考えその機会を窺っていたわけだが、そんな折に信長自身が本能寺でほとんど護衛も付けずに滞在するという隙を与えてくれた。
信長は唐入りを目指したことにより光秀に討たれ、実際に唐入りした秀吉は政権を家康に奪われてしまった。そう考えると下手な欲は出さず、とにかく日本という国を平和にすることのみ考えていれば、信長も秀吉ももしかしたら家を滅ぼすことはなかったのかもしれない。
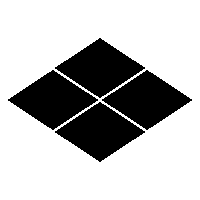
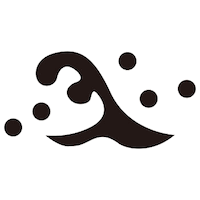


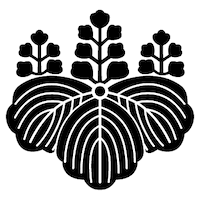

 本能寺の変が起こる少し以前、一説では2〜3年前とも言われているが、織田家臣団の心は信長から少しずつ離れていこうとしていた。怒涛の1570年代は指揮官としての信長に誰もが付いて行こうとしていたが、信長があることを口にし出すと、家臣団の心配はどんどん膨らんでいったようだ。
本能寺の変が起こる少し以前、一説では2〜3年前とも言われているが、織田家臣団の心は信長から少しずつ離れていこうとしていた。怒涛の1570年代は指揮官としての信長に誰もが付いて行こうとしていたが、信長があることを口にし出すと、家臣団の心配はどんどん膨らんでいったようだ。