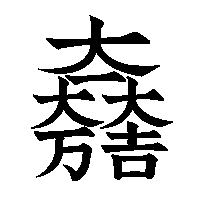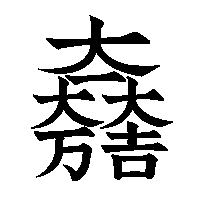
石田三成という人物は本当に誤解されやすい人だ。その理由の一つとして実直すぎるという点を挙げられる。そして実直すぎる故に融通が利かなく、あまり他人を信用しないという性格だったようだ。そしてその性格による対応のせいで、慶長の役では豊臣恩顧の武断派との溝がさらに広まってしまった。
慶長の役とは慶長2年(1597年)に始まった秀吉二度目の唐入りのことで、この朝鮮との戦は慶長3年に豊臣秀吉が死去したことにより終結した。その際、石田三成は国内に留まり、自らが信頼を寄せる軍目付(いくさめつけ)7人を朝鮮に派遣し、戦況や戦功の状況を調査させた。
その7人とは太田一吉(三成家臣)、垣見一直(三成家臣)、熊谷直盛(三成の娘婿)、竹中重利(竹中半兵衛の義弟)、早川長政、福原長堯(ながたか、三成の妹婿)、毛利高政という人選だった。このように三成は軍目付として、自らが信用している人物だけを選んだ。だがこの人選が武断派の不興を買ってしまう。
加藤清正、福島正則、黒田長政、細川忠興らは、軍目付として三成の臣下以外からも選ぶようにと迫ったが、三成はそれを受け入れなかった。その理由は武断派の息がかかった者を選べば、事実を誇張して報告される恐れがあったためだ。それを防ぎ、事実を正確に把握するために三成は自らが信頼している人物のみを軍目付として選んだ。
この7人の報告を受け、最終報告するのは三成の役目だったわけだが、武断派たちはそこで三成が讒言し、自らの武功を過小評価されたのではないかと猜疑したようだ。だが三成は過小評価して報告をしたわけでも、讒言したわけでもなかった。ただ事実をありのままに秀吉の報告したに過ぎなかったのである。決して私情を交えて報告するようなことはしなかった。
武断派たちは三成の思いなどまったく理解しようとはしなかった。文禄の役などでは特に、日本軍は海路を確保することができなかった。そのため兵糧を日本から朝鮮に送ることもできず、送ったとしても輸送船はあっという間に沈められてしまった。それにより朝鮮の日本軍は食糧危機に陥った。それでも武断派は戦いを続けようとしたのだが、三成は兵を無駄に死なせることを嫌い、退却を強く進言したのだった。
慶長の役では慶長3年8月18日に秀吉が死去し、朝鮮攻めが頓挫すると、三成は帰国してきた武将たちを博多で出迎えた。そして「伏見で秀頼公に御目通りされたら一度国に戻り休み、来年また上洛あれ。その折には茶の湯でも楽しもうではないか」と心からの労いの言葉をかけたようだが、加藤清正は「治部少は茶を振舞われるがよかろう。我らは異国で7年も戦い、米一粒、茶も酒もないため稗粥(ひえがゆ)ででも持て成そう」と怒鳴りつけたと伝えられている。
しかし振り返り見れば、兵糧が尽きかけようとしても戦を続けたのは清正ら武断派であり、兵を守るため撤退させようと苦心したのが三成だった。武断派たちはそんなことは決して理解しようとはせず、理不尽にも三成に当たり散らしたのだった。
秀吉の死は、三成にとっては心が千切れるような出来事だったに違いない。自分を武将に仕立ててくれた恩人であり、三成は秀吉の構想を実現させるべき身を粉にして働いてきた。三成にとっては秀吉こそが正義だったのである。慶長の役は8月以降、撤退は12月まで及んだのだが、三成は兵たちが無事帰国できるように、その間も奉行として涙を見せず働き続けた。
石田三成という人物は、自らにかかる疑念に対し弁明することはほとんどしなかった。そのため誤解が解かれることもなく、誤解がさらなる誤解を生んでしまうことも多々あった。そして江戸時代になると徳川家康の敵として、さらに有る事無い事酷く書かれることになってしまう。
秀吉の生前は秀吉のミスをカバーし続け、そのミスも自らが罪を被り、秀吉のカリスマ性が失われないように対応し続けた。そのような事実も武断派たちは決して知らなかったはずだし、知ろうともしなったのだろう。現代の歴史ドラマでも石田三成は未だ悪役として描かれることが多い。だが実際の石田三成は信じた正義を貫き通した、豊臣家最大の義将だったのである。
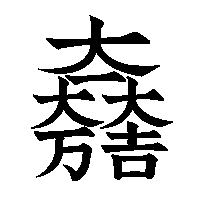
石田三成と加藤清正は本当に仲が悪かったのかと言えば、それは確かであるようだ。そしてその仲を決定的に悪くしたのは文禄の役での一連のやりとりでだった。文禄の役とは天正20年(1592年)4月に始まった唐入りのことだ。ちなみにこの年の12月8日に文禄と改元されたために、この唐入りは文禄の役と呼ばれている。
実は石田三成は唐入りには反対の意を持っていた。だが千利休や豊臣秀次とは違いそれを態度で示すことはなかった。しかし検分のため自らも実際に朝鮮に渡り、兵糧が尽きかけていると知るや否や、三成はすぐに戦線を縮小させようとした。それに異を唱えたのが加藤清正ら、いわゆる豊臣恩顧の武断派武将だちだったわけだ。
唐入り直後は、日本軍は破竹の勢いで朝鮮を攻め立てていた。だが明国が朝鮮の援軍として駆けつけてきた後は日本軍の勢いは少しずつ失われていく。そして見知らぬ土地で食べ物を調達することもできず、病死する者も多数出るようになった。これ以上戦況を悪くしないためにも、三成は戦線の縮小を大将宇喜多秀家に進言したのだった。
しかしこの時点では、槍働きをしている武将たちの手柄はほとんどないに等しかった。つまりこのタイミングで戦が終わってしまうと、兵を消耗しただけで何の得もない状態で帰国させられることになる。それだけは避けたいと躍起になったのが加藤清正だった。
さらに石田三成は軍目付(いくさめつけ)として、加藤清正を讒言(ざんげん)したと伝えられている。讒言とは事実を捻じ曲げて他人を陥れようとする行為のことだが、石田三成は決してそのようなことはしなかった。ただ、事実だけを秀吉に伝えたのである。
どのような事実かと言えば、実はこの戦いで加藤清正は、朝鮮の王子ふたりを捕虜としていた。戦いは少しずつ日本軍が劣勢に傾き始めており、そこへ明国の勅使から清正はある提言を受けた。それは朝鮮の王子をふたりとも無事に返せば、日本軍もこのまま無事に日本に返してくれる、というものだった。
だが清正はこの提案を勝手に蹴ってしまった。しかもあろうことか「豊臣朝臣(あそん)清正」と署名して。しかしこの時の加藤清正は豊臣姓は賜っていない。つまり清正は勝手に秀吉の姓を用い、勝手に交渉を蹴ってしまったというわけだ。三成はこの事実をありのまま秀吉に報告したに過ぎなかった。
さらに清正は明国とのやり取りの中で、小西行長のことを商人扱いし侮辱し、清正の家臣に至っては現地で狼藉を働いてもいた。このような事実が秀吉の怒りを買い、清正はその後帰国と伏見への蟄居を命じられている。ちなみに清正の勝手な越権行為が交渉決裂を招いてしまい、慶長の役へと繋がってしまった。
このように事実は、石田三成は讒言などしてはおらず、事実を報告されたことを加藤清正が讒言されたと歪曲理解してしまっただけの話なのだ。石田三成は、決して加藤清正を陥れようとなどしてはいないのである。だが日頃の不仲が積もり積もったことにより、このような事態になってしまったことは確かだろう。
この出来事により、石田三成と武断派たちとの間には決して埋め切れない大きな溝が生まれてしまった。そしてこの溝を巧みに利用して豊臣家から政権を横奪したのが徳川家康なのである。

関ヶ原の戦いで西軍を裏切った大名の代表格としていつも語られるのは、小早川秀秋だ。だがなぜ小早川秀秋は豊臣秀吉の正室、高台院(寧々、北政所)の甥でありながら西軍豊臣秀頼ではなく、東軍徳川家康に味方したのだろうか?実は秀秋を東軍に寝返らせるための調略を行ったのも、黒田長政だったのである。まさに黒田長政は東軍勝利の大立役者なのだ。
小早川秀秋は最後の最後まで悩み続けたと言う。西軍に味方すべきか、それとも東軍に寝返るか。当初は黒田長政に対し、東軍に味方するようなことを話していた。だがそれをなかなか実行に移そうとしない。それどころか関ヶ原の前哨戦として行われた伏見城の戦いでは、西軍の副将として東軍伏見城攻めに参戦している。
黒田長政は解せなかった。東軍に味方をするようなことを言っておきながら、小早川秀秋は未だ西軍として東軍に攻撃を仕掛けている。本当に家康に味方するつもりがあるのか、長政は秀秋を問い質そうとした。だが秀秋はなかなか態度をはっきりさせなかった。本来であれば豊臣恩顧の大名として西軍で戦うのが筋だ。しかし東軍に味方する大きな理由もあったのである。
その前に秀秋は、唐入り(慶長の役)では戦目付の報告により秀吉の怒りを買い減俸させれていた。その戦目付が三成派であり、秀秋は三成に対してはそれほど良い感情は持っていなかったと伝えられている。しかしそれでも一時は西軍として戦っているのだから、黒田長政や福島正則、加藤清正らに比べればそれほど三成のことを嫌ってはいなかったのかもしれない。
秀秋は迷いに迷った。ただ、東軍に味方すると言いながら西軍に付かなければならない事情もあった。関ヶ原の戦いを前にして大坂城は西軍の大軍で溢れており、仮に秀秋が早い段階で東軍に寝返ったとしたら、あっという間に西軍に討たれてしまう危険があったのだ。そのために最後の最後まで態度をはっきりさせられなかった、と考えることもできる。
だが黒田長政は悠長に待っていることなどできなかった。関ヶ原の戦いが開戦される半月ほど前の8月28日、黒田長政は浅野幸長(よしなが)と連名で小早川秀秋に書状を送っている。その内容は、浅野幸長の母親が北政所の妹であるため、秀秋にも東軍に味方して欲しい、と求めるものだった。ではなぜ長政はこのような書状を送ったのか?
実は小早川秀秋は豊臣秀吉の養子であり、幼い頃は北政所に育てられていた。つまり北政所は秀秋にとって養母であり、母親同然の存在だったのだ。黒田長政は秀秋よりも14歳上なのだが、実は長政にとっても北政所は母親同然なのである。
幼少期にまだ松寿丸と名乗っていた頃、長政は人質として織田家に送られていた。そしてその人質の面倒を見ていたのが羽柴秀吉の妻寧々、つまり若き日の北政所だったのである。子を産めなかった北政所は、長政のことを我が子同然に可愛がった。人質として扱うことなど決してなく、父官兵衛の裏切りが疑われた際に長政の処刑が信長から命じられると、最も悲しんだのが北政所だった。そして
竹中半兵衛により長政の命が救われ最も喜んだのも北政所だった。
その北政所は淀殿(茶々)と反りが合わず、秀吉死後は自然と家康側に傾倒していた。長政は、秀秋にとっても母同然である北政所が東軍にいるのだから、秀秋も当然東軍に味方すべきであると、と説得を繰り返したのだった。この長政の説得もあり、秀秋は関ヶ原の戦い当日になりようやく西軍を離脱することになる。
福島正則の西軍への寝返りを阻止したのも、西軍総大将毛利輝元に出撃させなかったのも、小早川秀秋を東軍に寝返らせたのも、すべては黒田長政の調略によってのものだった。黒田長政は歴史上、父黒田官兵衛ほど目立つ存在ではない。実際黒田官兵衛を特集した書籍、雑誌ならいくらでもあるが、黒田長政を特集したものはほとんど存在しない。
だが関ヶ原の戦いを東軍勝利に導いたというこの功績は、父官兵衛のかつての活躍を凌ぐ働きだったとも言える。なお幼馴染である竹中半兵衛の子、重門とは関ヶ原の戦いでは隣り合って布陣したと伝えられている。
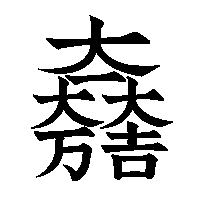
賤ヶ岳の戦いと言えば、とにかく真っ先に出てくるのは七本槍だ。賎ヶ岳の七本槍とは糟屋武則、片桐且元、加藤清正、加藤嘉明、平野長泰、福島正則、脇坂安治のことで、この戦いで武功を挙げた秀吉の若き近習たちだ。しかし賤ヶ岳で活躍したのは七本槍だけではない。賎ヶ岳の先駆け衆と呼ばれた14人の若者もおり、その中には石田三成、大谷吉継らが含まれていた。
先駆け衆とは一番槍の武功を挙げた者たちのことで、その名の通り本体よりも先駆けて戦場で戦った者たちのことを呼ぶ。石田三成という人物は、いわゆる武断派と呼ばれた加藤清正、福島正則、黒田長政らとは反りが合わず、武断派の面々は三成は槍働きをせずに出世したと思い込んでいた。確かに武功という意味では三成は武断派には敵わない。だが武断派の活躍は三成あってこそのものだったことを、決して見逃してはならない。
柴田勝家と戦った賤ヶ岳の戦いに於いて、羽柴軍は5万を超える大軍となっていた。三成はまず、その5万人分の兵糧の調達を秀吉から命じられた。5万人分の兵糧とは、まさに途方もない数字だ。この時三成は大谷吉継に、5万人の軍勢が何日間食べられるだけ兵糧を用意すればいいかと相談していた。それに対し吉継は1ヵ月半と弾き出した。吉継が軍略に富んだ人物であることは三成もよく知っている。三成は吉継の言葉を信じ、5万人が1ヵ月半食べられるだけの兵糧を準備した。事実この戦いは1ヵ月少々期間で勝敗jが決した。
そしてもちろん揃えるのは兵糧だけではない。鉄砲の玉や硝煙などの武器を揃えたのも三成だった。つまり七本槍が心置きなく戦えたのは、三成が兵糧などを抜かりなく準備してくれたお陰なのである。だが武断派たちはそれを持って三成は槍働きをしていない、と不満を募らせる。
さて、この時三成が任されたのは兵站だけではない。賤ヶ岳での決戦に及ぶ前、秀吉は岐阜城の織田信孝を攻めていた。その隙を突いて柴田勢が賤ヶ岳近くの木之本の羽柴陣営に攻め寄せてきた。柴田勢屈指の猛将佐久間盛政だ。だが佐久間盛政は手薄だったはずの木之本を攻撃することができなかった。
秀吉は岐阜城の信孝を攻めているはずだった。しかし木之本には数え切れない程の松明が灯されている。佐久間盛政はそれを見て、秀吉の本陣がもう木之本まで戻って来たと勘違いしたのだった。さすがの佐久間盛政であっても、秀吉の大軍勢を相手に戦うわけにはいかない。そのため盛政はその松明を見ると、すぐに後退していった。
しかしその松明は、羽柴勢本体が木之本まで戻ったものではなかった。三成が先駆けて木之本まで戻り、農民らの手を借りて杭に笠をかぶせ偽装したものだった。つまりは案山子だ。その案山子を羽柴本体だと勘違いして佐久間盛政は撤退していったのである。もしこの時佐久間盛政が攻め入れば、木之本はあっさりと陥落していた。そしてその後の戦いも柴田勢有利に進み、賤ヶ岳の戦いの結果ももしかしたら変わっていたかもしれない。
このような三成の策略があったからこそ、七本槍の若者たちが活躍する機会も生まれた。なお三成の賤ヶ岳での活躍はこれだけではない。早馬や狼煙を活用することにより、情報を限りなく速くやり取りするシステムの構築も行っていた。狼煙の色によって伝達内容をあらかじめ決め、早馬も一里(約4キロ)置きに馬を置き、常に最速の馬の走りで伝達できるように工夫していた。
七本槍の活躍も見事だったわけだが、しかし石田三成ら十四人の先駆け衆の活躍も、この通り見事だったのである。それでも七本槍ばかりが注目されてきたのはやはり、家康の天敵であった三成の情報が江戸時代に入り、恣意的に捻じ曲げられてしまったせいなのだろう。もし三成が関ヶ原で敗れていなければ、賤ヶ岳の先駆け衆ももっと注目されて然るべきだった。

織田家に於いて、前田利家ほど武功により出世した人物はいないのではないだろうか。豊臣家で後に武断派と呼ばれる加藤清正、福島正則、黒田長政らも、前田利家のことをとても尊敬しており、特に加藤清正は利家への尊敬の念が強かったと言う。やはり武断派たちにとって、前田利家という武功によって大出世した人物は憧れの的だったのだろう。
前田利家は尾張荒子城主前田利春の四男として生まれた。四男であれば通常は家督を継ぐことはできず、出世を望むことなどほとんどできない時代だった。だが若き日の信長は家督を継ぐことができない次男以下の有能な人物を集め軍団を形成していた。その1人が前田利家だったというわけだ。
通称又左衛門こと若かりし頃の前田利家は、「槍の又左」と呼ばれたほどの槍の名手だった。6.3メートルもの長槍を悠然と振り回していたらしい。そして時には右目に矢傷を負いながらも槍を振り回し続け、敵将の首を打ち取るという武功も残している。
織田信長は前田利家のことを高く買っていた。だがある日利家は、自らの笄(こうがい・刀の付属品)を盗んだ拾阿弥(じゅあみ)を怒りに任せ惨殺してしまった。拾阿弥は信長の家臣だったため、いくら盗みを働いたとしても惨殺は大きな罪となり、利家は織田家を追放されてしまう。これが永禄2年(1559年)の出来事だった。つまり
桶狭間の戦いの前年だ。
この惨殺事件により利家は織田家臣団として桶狭間に参戦することができなくなってしまった。だが利家はそれでも勝手に従軍し、織田軍の一員としていくつもの武功を挙げた。そして桶狭間でのその活躍により、利家は再び織田家に帰参することが許され、信長の赤母衣衆に加えられた。
前田家の家督は当然だが長男の利久が継いでいた。だが利久が病弱で子もいなかったため、永禄12年(1569年)になると信長は、利久に替わり利家に前田家を継ぐようにと命じた。これによって利家は四男だったにも関わらず家督を継ぐことができ、以降は主に北陸方面でその武力を発揮していった。
そして天正9年(1581年)になると信長から能登一国を与えられ、本来は家督さえ継げないはずの四男が国持大名にまで出世してしまった。翌年信長が横死すると、利家は最終的には秀吉に味方をし、豊臣政権では五大老という立場で徳川家康と肩を並べた。
同じ五大老の中でも利家は特に人望の厚い人物だった。そのため何か問題が起こったとしても、利家が説得をすれば事なきを得ることも多かったと言う。豊臣政権内で石田三成を敵対視していた加藤清正、福島正則、黒田長政らは、三成の暗殺を企てていた。だが利家の存在によりそれを思いとどまっていたのだが、しかし利家が亡くなるとその翌日、三成の襲撃を実行してしまう(ただし失敗に終わる)。
織田家に於いては出世頭のひとりであり、豊臣政権に於いては内外ともに調整役としてなくてはならない存在だった。若い頃は傾奇者として鳴らした利家も、晩年はすっかり温厚な宿老となっていた。だがその温厚さの陰には絶対的な強さや信念があり、だからこそ豊臣秀吉も家康への抑えとして利家には全幅の信頼を置くことができたのだ。ちなみに利家と秀吉は若い頃から夫婦同士での付き合いがあり、犬千代、猿だったにも関わらず犬猿の仲ではなく、むしろ強い絆で結ばれていたのだった。
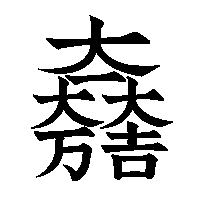
石田三成という人物は、とにかく周囲から誤解されやすい性格だった。どうやら率直に物を言い過ぎてしまう嫌いがあったようで、意に反し言葉にも棘があったらしい。だがその実像は決して冷徹な人間ではなく、心に熱いものを秘めた人物だった。そして誰よりも日本という国と豊臣政権のことを深く愛し、そして考えていた。自身のことなど二の次だったのだ。
近江出身の三成には、近江商人の血が流れていた。近江商人と言えば「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」を信条とする商人たちのことだ。つまり売る側も買う側も幸せになり、それによって世間全体も良くしていこうという信念だ。三成もこの近江商人の信念を受け継いでいた。だが三成自身はと言えば、買い手と世間の幸せばかりを考え、自らの幸せなどほとんど考えていなかった。
その好例となるのが佐和山城だ。佐和山城と言えば「三成に過ぎたるもの」と揶揄されたほどの名城で、三成が関ヶ原の合戦後に京都の六条河原で処刑されると、その城は東軍によって接収され、井伊直政(井伊直虎のはとこ)に与えられた。その際将兵たちは「三成のことだから秀吉のように、さぞや財宝を蓄えているのだろう」と考えていた。だが彼らは佐和山城に入り驚くことになる。
佐和山城内は財宝に溢れかえるどころか、驚くほどに質素だった。壁にも庭にも装飾品らしいものは一切なく、生活感さえ感じられないほどだったようだ。三成は「残すは盗なり。つかひ過して借銭するは愚人なり」という言葉を残している。これは農民たちから集めた年貢を使い残し自分のものとするのは盗み同然であり、逆に使い過ぎて借金をするのは愚か者、という意味だ。誰よりも現代の政治家たちに教えてあげたい言葉だ。
つまり三成は集めた年貢はすべて民政のために使い、わずかに残った分で慎ましく暮らしていたのだ。テレビドラマで描かれているように、決して派手な着物を纏っていたわけではなかった。三成は秀吉政権の重臣だったため、どうしてもイメージが秀吉と被ってしまったのだろう。NHK大河ドラマでさえも時に三成を流行に敏感な派手な人物として描いている。
現代に於ける三成のイメージは、すべて江戸時代に捏造されたものばかりだ。確かに武断派と呼ばれた加藤清正、福島正則、黒田長政らとは反りは合わなかったようだが、しかしだからと言って誰からも嫌われるような人物ではなく、逆に身近な人間からは非常に好かれていたのだ。
秀吉が滅ぼした大名家の遺臣たちを三成も多く召し抱えたわけだが、彼らのほとんどは関ヶ原の合戦で三成に命を捧げている。さらには盟友である大谷吉継、島左近、真田昌幸・信繁父子、上杉景勝・直江兼続主従は西軍として三成に味方している。しかも大谷吉継と島左近はここで討ち死にを果たしてもいる。
さらには三成に恩を感じていた佐竹義宣も明確に東軍に味方することはせず、再び三成を助けるために上杉家と密約を結んでいたとも伝えられている。果たして三成が現代に伝わるような冷徹な人間であったなら、彼らのような名将たちが天下を分ける関ヶ原で西軍についていただろうか。
家を守るためには手段を選ばず、秀吉に「表裏比興の者」と称された真田昌幸でさえ西軍に味方しているのだ。恐らく昌幸は
忍城の水攻めでの三成の働きを間近で見て感銘を受けたことにより、西軍の勝利に賭けたのだろう。
「三成は嫌われ者だった」というイメージは完全に間違っている。もし本当に嫌われ者だったとすれば、わずか19万石の小大名に過ぎなかった三成が、関ヶ原の戦いのために8万人以上の兵を集めることなどできなかったはずだ。西軍に味方した大名たちは「三成だからこそ」味方したのだ。
三成の人柄を言い表すならば、取っ付きにくいが話してみると良い奴、と言った感じだったのだろう。そして弁明などは一切しない人物だっため、誤解をされてもその誤解を自ら解くことはほとんどなかったようだ。それによって誤解が誤解を生み、武断派武将たちを敵に回してしまった印象も強い。
だが石田三成が処刑されてからもう400年以上が経過している。そろそろ三成の誤解をすべて解いてあげてもいいのではないだろうか。
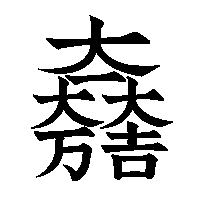
石田三成は自らの弱点をよくわきまえていた。同じ奉行衆であった盟友大谷吉継は、内政も戦も得意としていた。主君豊臣秀吉も、大谷吉継に100万の兵を預け指揮させてみたい、と語っているほどだ。だが石田三成は戦に関しては決して得意ではなかった。
石田三成は知略に優れた武将だった。出身が近江商人で有名な近江であり、父親正継も近江石田村の庄屋で観音寺の檀那職を務めるような人物だった。つまり父親も算術に秀た人物であり、三成もそれを受け継いでいたようだ。その影響で三成は兵站奉行として兵糧、武器などを滞りなく調達し、秀吉の数々の勝利の手助けをし活躍した。
石田三成の人物の良さは、上述したように自らの弱点をよくわきまえていた点だ。つまり奉行職で地位を得てもすべてが優れているとは勘違いせず、槍働きが苦手なことを自認していたのだ。そしてその弱点を補うために、三成はある人物のスカウティングを行った。そして近江水口城主になり4万石の所領を得た三成は、何と1万5千石をその人物に与えてしまった。その人物とは島左近のことだ。
島左近は大和の筒井順慶を支える筆頭家老だった。しかし順慶が病死したあとは家督を継いだ定次に疎まれるようになり、ついには筒井家を去ってしまう。その後左近は蒲生氏郷や豊臣秀長に仕えるも長続きはせず、浪人として放浪することが長くなっていった。どうやら左近は筒井家の筆頭家老だった誇りが邪魔をし、新参者として扱われることを嫌ったようだ。
その噂を耳にし、三成は自らの家臣になって欲しいと左近に頭を下げたのだった。島左近清興と言えばまさに戦国時代きっての猛将だ。鬼左近と呼ばれたのも伊達ではなく、戦場で左近と出会った者は皆慄いたと言う。三成は左近を召し抱えることにより、自らの弱点をピンポイントで補うことに成功した。
島左近は漢気溢れる人物で、三成が所領の半分近い1万5千石で召し抱えてくれたことにより、生涯三成に尽くすことを誓った。その後三成は佐和山城19万4千石の大名となったわけだが、その際三成は左近の所領も増やそうとした。だが左近は自分に1万5千石以上は必要ないと言い、その代わりもっと多くの兵を雇い石田軍を強化なものにしてくれと申し出た。左近とはこのように、意気に感じた相手にはとことん尽くせる漢気溢れる人物だったのだ。
「三成に過ぎたるものが二つあり、島の左近と佐和山の城」という唄が当時巷で流行っていたようだ。これは文字通り、島左近と佐和山城は三成にはもったいない、と皮肉った歌詞だ。だが本当にこれが戦国時代に唄われていたのだろうか。これも恐らく江戸時代に捏造されたものなのだろう。
関ヶ原以前に於いて、三成を悪く思っているのは豊臣家のいわゆる武断派(加藤清正、福島正則、黒田長政など槍働きを得意とした武将たち)だけだったと言う。そう考えるとこの唄も、恐らく関ヶ原後の江戸時代の創り話なのではないだろうか。この唄については『古今武家盛衰記』という作者不明の古文書に記されており、恐らくは江戸時代後期に書かれたものだと思われる。
関ヶ原で三成は敗れてしまうわけだが、戦場から無事逃げ出すため命を張ったのが島左近だった。とにかくまずは三成を無地戦場から逃がそうと、左近は自ら先頭に立って黒田長政勢と戦った。だが最期は黒田勢の鉄砲で蜂の巣とされてしまい、壮絶な討ち死にを遂げてしまう。
左近としてはこの直前に家康暗殺に失敗しているため、それを挽回するためにも死に場所を探していたのだろう。西軍を何とか立て直すというよりは、左近の最期の行動は自ら華々しく散ることを優先に考えられていたように感じる。もし左近がもっと策を巡らすことができれば、西軍があそこまで総崩れになることはなかったのかもしれない。そして家康暗殺がもし成功していたら、関ヶ原の戦いが起こることもまたなかったのかもしれない。