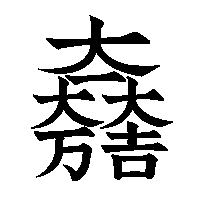
石田三成という人物は本当に誤解されやすい人だ。その理由の一つとして実直すぎるという点を挙げられる。そして実直すぎる故に融通が利かなく、あまり他人を信用しないという性格だったようだ。そしてその性格による対応のせいで、慶長の役では豊臣恩顧の武断派との溝がさらに広まってしまった。
慶長の役とは慶長2年(1597年)に始まった秀吉二度目の唐入りのことで、この朝鮮との戦は慶長3年に豊臣秀吉が死去したことにより終結した。その際、石田三成は国内に留まり、自らが信頼を寄せる軍目付(いくさめつけ)7人を朝鮮に派遣し、戦況や戦功の状況を調査させた。
その7人とは太田一吉(三成家臣)、垣見一直(三成家臣)、熊谷直盛(三成の娘婿)、竹中重利(竹中半兵衛の義弟)、早川長政、福原長堯(ながたか、三成の妹婿)、毛利高政という人選だった。このように三成は軍目付として、自らが信用している人物だけを選んだ。だがこの人選が武断派の不興を買ってしまう。
加藤清正、福島正則、黒田長政、細川忠興らは、軍目付として三成の臣下以外からも選ぶようにと迫ったが、三成はそれを受け入れなかった。その理由は武断派の息がかかった者を選べば、事実を誇張して報告される恐れがあったためだ。それを防ぎ、事実を正確に把握するために三成は自らが信頼している人物のみを軍目付として選んだ。
この7人の報告を受け、最終報告するのは三成の役目だったわけだが、武断派たちはそこで三成が讒言し、自らの武功を過小評価されたのではないかと猜疑したようだ。だが三成は過小評価して報告をしたわけでも、讒言したわけでもなかった。ただ事実をありのままに秀吉の報告したに過ぎなかったのである。決して私情を交えて報告するようなことはしなかった。
武断派たちは三成の思いなどまったく理解しようとはしなかった。文禄の役などでは特に、日本軍は海路を確保することができなかった。そのため兵糧を日本から朝鮮に送ることもできず、送ったとしても輸送船はあっという間に沈められてしまった。それにより朝鮮の日本軍は食糧危機に陥った。それでも武断派は戦いを続けようとしたのだが、三成は兵を無駄に死なせることを嫌い、退却を強く進言したのだった。
慶長の役では慶長3年8月18日に秀吉が死去し、朝鮮攻めが頓挫すると、三成は帰国してきた武将たちを博多で出迎えた。そして「伏見で秀頼公に御目通りされたら一度国に戻り休み、来年また上洛あれ。その折には茶の湯でも楽しもうではないか」と心からの労いの言葉をかけたようだが、加藤清正は「治部少は茶を振舞われるがよかろう。我らは異国で7年も戦い、米一粒、茶も酒もないため稗粥(ひえがゆ)ででも持て成そう」と怒鳴りつけたと伝えられている。
しかし振り返り見れば、兵糧が尽きかけようとしても戦を続けたのは清正ら武断派であり、兵を守るため撤退させようと苦心したのが三成だった。武断派たちはそんなことは決して理解しようとはせず、理不尽にも三成に当たり散らしたのだった。
秀吉の死は、三成にとっては心が千切れるような出来事だったに違いない。自分を武将に仕立ててくれた恩人であり、三成は秀吉の構想を実現させるべき身を粉にして働いてきた。三成にとっては秀吉こそが正義だったのである。慶長の役は8月以降、撤退は12月まで及んだのだが、三成は兵たちが無事帰国できるように、その間も奉行として涙を見せず働き続けた。
石田三成という人物は、自らにかかる疑念に対し弁明することはほとんどしなかった。そのため誤解が解かれることもなく、誤解がさらなる誤解を生んでしまうことも多々あった。そして江戸時代になると徳川家康の敵として、さらに有る事無い事酷く書かれることになってしまう。
秀吉の生前は秀吉のミスをカバーし続け、そのミスも自らが罪を被り、秀吉のカリスマ性が失われないように対応し続けた。そのような事実も武断派たちは決して知らなかったはずだし、知ろうともしなったのだろう。現代の歴史ドラマでも石田三成は未だ悪役として描かれることが多い。だが実際の石田三成は信じた正義を貫き通した、豊臣家最大の義将だったのである。