
酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政の4人を俗に徳川四天王と呼ぶ。だがこの4人年齢が実にバラバラなのである。その中でも井伊直政は最も若く、酒井忠次とは親子以上の歳の差があった。それでも井伊直政が徳川四天王に名を連ねたということは、物凄い速度で出世していったということになる。
酒井忠次・・・大永7年(1527年)生まれ
本多忠勝・・・天文17年(1548年)生まれ
榊原康政・・・天文17年生まれ
井伊直政・・・永禄4年(1561年)生まれ
酒井忠次と井伊直政は34歳差、本多忠勝・榊原康政と井伊直政は13歳となる。ちなみに直政を除く3人はみな三河出身で、つまりは家康と同郷となる。まだ新興大名だった頃から家康を支えていた3人だった。一方直政は遠江出身で、家康に出仕したのは天正3年(1575年)、直政が15歳の時からだった。この時はわずかに300石の知行だった。
それから7年後、
本能寺の変が起こる天正10年(1582年)には4万石にまで加増されている。そして
関ヶ原の戦いでの功績として石田三成の居城であった佐和山城を与えられた時には、18万石の有力大名となっていた。まさにトントン拍子で出世して行ったと言える。
この出世に対し一説では徳川家康が男色家であり、直政を寵愛していたためだと言われている。だがこれは真実とは言えない。多くの史家たちが言うように、家康に男色の気はなかったのである。これは織田信長が森蘭丸を寵愛したことになぞらえられていると考えられるが、実は織田信長も男色家として森蘭丸を寵愛していたわけではなかった。
信長が蘭丸を寵愛したというのは、信長の死後に秀吉が吹聴した作り話だった。森蘭丸という漢字も秀吉が勝手に変えてしまったものであり、実際の漢字は森乱丸だった。 当時、蘭という言葉には女性らしい男子という意味合いがあったらしく、信長を男色家としてしまうために、秀吉はあえて蘭丸と書かせていたようだ。秀吉の場合、男色家の信長より、自分の方が天下人に相応しいとアピールするために、このような捏ち上げをしている。
話を井伊直政に戻すと、直政の父親は直親であり、直親の祖父は井伊直平だ。この井伊直平という人物は、実は築山殿の母方の祖父なのだ。築山殿とはもちろん、徳川家康の正室だ。築山殿は直政が家康に仕えた4年後に殺されてしまうのだが、正室の血縁者ということで家康も直政を重用するようになった。
そしてもう一つ家康が直政を重用した理由がある。直政の父、井伊直親は謀反の嫌疑をかけられ謀殺されてしまったわけだが、その原因は直親と徳川家康が遠江について話し合ったことにあった。もちろん謀反の相談ではなかったわけだが、それを謀反だと讒言され、直親は今川氏真の命により殺害されてしまう。
このような経緯もあり、家康は直親の子である直政を重用するようになった。井伊直虎の死後、まだ万千代と名乗っていた22歳の直政に「井伊を名乗るようにと」命じたのも家康だった。
井伊直政の驚異的なスピード出世の陰には直政自身の高い能力に加え、築山殿の血縁者、直親の死に家康が関係していた、という要因があったようだ。そして最終的には近江佐和山藩初代藩主にまで昇り詰め、慶長7年(1602年)2月1日、関ヶ原で追った怪我が原因で41歳という若さで亡くなっている。
幼き頃から今川から命を狙われ、14歳でようやく井伊谷に戻ることができ、15歳で家康に出仕してからはスピード出世し、そして関ヶ原から1年半後に亡くなってしまった。まさに井伊直政は太く短く生きた戦国の名将と言えるだろう。

天正10年(1582)年6月2日、本能寺の変はなぜ起こってしまったのか?!誰が黒幕だったかということでも様々な論争が行われているが、黒幕がいたようには感じられない。本能寺の変について書いた他の巻でも書いたことではあるが、これは織田信長の将来構想に対する家臣たちの不安の産物だったと考えられる。
筆者はこれまで多数の本能寺の変に関する書物を拝読してきた。その中でも多くのことを証拠を用いてスッキリさせてくれたのが明智憲三郎氏の『
本能寺の変 431年目の真実
』という一冊だった。この中で筆者が最も衝撃的だったのが、信長が手勢僅か100人程度で本能寺に滞在していた理由だった。
さて、信長と家康と言えば兄弟同然の間柄として有名だ。信長は家康のことを弟のように可愛がり、家康も信長のことを兄のように慕っていた。これが通説であるわけだが、事実そうだったと思う。本心はさておき、信長と家康の仲を悪く書いた当時の書物はないようだ。
信長が本能寺に滞在していた通説は、本能寺で家康を接待するためだったと言われている。だが明智憲三郎氏の歴史調査によると、事実はそうではなかったようだ。確かに家康を接待するために信長はわざわざ本能寺に家康を呼び寄せた。しかし事実は決して接待するためではなかったと言う。
この時、明智光秀は手勢を控えて本能寺の近くに控えていた。通説のうちにはノイローゼ気味だった光秀が、突発的に本能寺を襲撃したと書かれたものもあるが、これらの考察はすべて推察でしかなく、何の根拠も示されてはいない。だが明智憲三郎氏の著書は違う。証拠をいくつも並べ立てた上で、信長が家康を本能寺に呼び寄せたのは、家康を暗殺するためだと証明して見せている。他の本能寺の関連本とは異なり、証拠が示されているだけにとにかく説得力があるのだ。
信長は、家康に警戒されないように100人程度の手勢だけで本能寺に滞在していた。つまり油断していたわけではなく、家康を警戒させないための芝居だったと言うわけだ。だが信長の誤算は、光秀を信じ過ぎたことだった。これは
金ヶ崎撤退戦と同様だ。金ヶ崎撤退戦でも信長は義弟浅井長政を信じ過ぎ、危うく命を落とすところだった。
一度目は何とか命拾いした。だが二度目は浅井長政よりも遥かに智謀に優れ、経験豊富な明智光秀が相手だった。光秀は影で家康と密約を結んでいたと言う。光秀は、本能寺に入った家康一行を暗殺するために本能寺近くで待機していた。だが光秀は家康と手を結ぶことにより、これを家康暗殺ではなく、信長暗殺に計画を仕立て直してしまったのだ。詳しくはぜひ明智憲三郎氏の著書を読んでもらえたらと思う。
つまり本能寺で本来討たれる相手は徳川家康だったのだ。信長は家康のことを高く買っていた。それだけに自身亡き後、家康が子孫たちの脅威になると考えたようだ。その後家康が豊臣家から天下を奪い取ってしまうように。それを未然に防ぐため、信長は早いうちに家康を屠ってしまおうと考えたらしい。
話をまとめるとこうだ。信長は、家康を暗殺するために本能寺に呼び寄せ、光秀に暗殺を命じていた。だが光秀は家康と手を結んでしまい、家康ではなく主君信長を討ち果たしてしまったというわけだ。
戦国時代に武将たちが最も重視していたのは、いかにして家を守るかということだった。家を守るためなら身内であっても討ち果たすことなど日常茶飯事だった。信長が家康の暗殺を企てたのも織田家を守るためなら、光秀が信長を討ったのも明智家(土岐家)を守るためだった。そして家康が光秀の企てに力を貸したのもやはり、徳川家を守るためには光秀と手を結んだ方が上策だと考えたからだった。
明智憲三郎氏の著書を拝読しながら改めて本能寺の変を考えていくと、これは決して偶発的に起こったクーデターなどではなく、起こるべくして起こった出来事だったということがよくわかるのである。

第一次上田合戦以降、真田家と徳川家の間には険悪なムードが漂い続けていた。まさに一触即発といった状況で、家康としては状況さえ許せばすぐにでも真田を潰してしまいたい思いだった。自ら真田のために築いた上田城で、自ら真田に大敗を喫してしまったのも家康としては内心忸怩たる思いだったはずだ。
この頃の真田は上杉家の庇護を受けており、弁丸(のちの真田信繁、通称幸村)が人質として送られていた。第一次上田合戦では母山之手殿を海津城に代わりの人質として送ることにより一時的な帰国と、上田合戦への参加を許されはしたが、あくまでも弁丸は上杉家の人質という立場だった。
真田昌幸は徳川対策を考え始める。もちろん上杉の傘下に入ったことがその一つではあるのだが、同時に羽柴秀吉とも交渉を進めていたようだ。一説では秀吉と交渉をすることは、上杉側から許可をもらっていたと言う。義の上杉に対し、義を立てて接した昌幸と思いきや、これもやはり昌幸一流の芝居だった。
昌幸の交渉が実り、秀吉が真田と徳川の仲裁をしてくれることが決まった。その条件として秀吉は真田昌幸に人質を求めたわけだが、その人質として昌幸は弁丸を送ろうとする。だが弁丸はもちろんまだ上杉家の人質だ。一人の人間がふたつの家の人質になることはできない。では昌幸は一体どのようにしたのか?
天正14年(1586年)6月、上杉景勝は羽柴秀吉の軍門に下り上洛することになった。昌幸はこの隙を突き春日山城から勝手に弁丸を奪還してしまったのだった。上杉景勝はさすがに怒りを露わにするが、しかし弁丸が再び送られた先は羽柴秀吉の元であり、これにより真田家は羽柴家の臣下となっていた。つまり上杉が真田を攻撃するということは、上杉が羽柴を攻めるのに等しい行為であり、これは当然謀反となってしまう。そのため景勝は真田に対し何も行動を起こすことができなかったのだ。
真田昌幸はそこまで予測し、弁丸の奪還を実行した。秀吉に「表裏比興の者」と呼ばれたのもこの辺りの出来事が所以となっているのだろう。だが結果的には第一次上田合戦の翌年、秀吉の仲裁により真田家と徳川家の和睦が成立した。上杉家はこの和睦を実現させるために利用された形となったわけだが、昌幸は最初からその腹づもりだったようだ。
真田と徳川の全面戦争になれば、さすがの謀将真田昌幸にも勝ち目はない。国力に差があり過ぎるのだ。つまり徳川との火種をいつまでも燻らせていては、いつか徳川に真田が滅ぼされると昌幸は考えていた。昌幸の目的はあくまでも真田の家の存続だ。真田の家と真田の郷を守ることに命を賭している。そして真田を守れるのであれば手段など問わないのが昌幸のやり方だった。
この一連の流れにより真田は上杉とも険悪になってしまうのだが、しかしこれは後々解消されていくようだ。恐らく景勝自身、真田はそうまでしなければ家を守ることができなかったと考えるようになり、そして許したのだろう。だからこそ関ヶ原の戦いで真田と上杉は同じ西軍として石田三成に味方し、徳川家康を敵に回し戦ったのだろう。

真田と徳川による第一次上田合戦が始まったのは天正13年(1585年)8月2日だった。戦いが始まる前、真田昌幸は上田城下に千鳥掛けを仕掛けていた。千鳥掛けとは柵を斜めに並べ配置し、まるで迷路のように敵の行く手を阻む防衛線のことだ。この千鳥掛けを仕掛けた上で、昌幸は徳川勢を上田城内に誘き寄せた。
この時上田城を攻めたのは鳥居元忠、大久保忠世、平岩親吉で、彼らの下には信濃勢や甲州勢など武田の旧臣たちが付けられ、総勢7000の軍勢となっていた。対する上田城に籠る真田勢は2000程度で、数の上では真田勢が圧倒的不利な状況だった。だが7000という大所帯が徳川勢を逆に不利に追い込んでしまう。昌幸が仕掛けた千鳥掛けにまんまとはまってしまったのだ。
徳川勢は誘き寄せられるまま上田城内に侵入していくと、本城まで間近の二の曲輪で千鳥掛けによる迷路に迷い込んでしまった。進むことも戻ることもできず兵は右往左往している。徳川勢はやむなく一度城外に戻り体勢を整えることにした。この時徳川勢は放火してから城下に出ようともしたらしいが、結局味方への損害も鑑みられ火は放たれなかった。だが千鳥掛けを縫うように退いて行く徳川勢の動きを謀将真田昌幸が見逃すはずはなかった。
徳川勢が上田城から出ようとするその背中を昌幸は急襲した。するともう徳川勢は大混乱に陥る。後ろからは真田勢が追い打ちをかけてくるし、出て行こうとする城下町には真田自ら放火し、徳川勢は退くことも進むこともできなくなってしまった。それでも何とか城門まで退くと、今度は上から岩や大木、火の着いた松明が徳川勢に向け次々と投げ込まれた。徳川勢は「卑怯だ!」と皆喚くが真田勢は意に介さない。もはや人対人の戦ではなく、ゲリラ戦の様相となり、どんどん岩などを投げ込んで行った。だが真田昌幸の謀略はこれだけではなかった。
昌幸は百姓たちを城下町周辺に忍ばせておき、紙で急拵えした真田の旗を掲げさせた。これ見た徳川勢はさらに大混乱に陥り、完全に包囲されたと錯覚してしまった。徳川勢がここから体勢を整えることなど、もうほとんど不可能に近かった。大久保忠教は上田城から退く際に、やはり火を放っておくべきだったと後悔したと言う。
だが真田の攻撃はまだまだ終わらない。命辛々上田城を出た徳川勢を待っていたのは、砥石城から援軍に駆けつけた昌幸の長男、真田信幸の部隊だった。もはや徳川勢にできることと言えば逃げることだけだ。部隊はそれぞれ壊滅状態で、軍としてはまるで機能していない。それでも何とか信幸の部隊を振り切った徳川勢だったが、神川まで落ち延びるとさらなる悲劇が待っていた。
この戦いが始まる前まで、上田は連日の大雨に見舞われており、川はどこも増水していたのだ。そんな増水している神川を渡っている最中に、鉄砲水が徳川勢を襲ったのだった。これにより徳川勢には多くの溺死者が出てしまう。最終的に7000の兵のうち1300人が命を失ってしまったと伝えられている。だがこの1300という数は、真田信幸が家臣に送った書状に書かれていたものであり、かなり誇張され書かれたものだと思われる。
一方徳川方の『三河物語』には300人の損害と書かれており、これもやはりかなり少なめに書かれている。ちょうど中間をとるならば、実際には800人前後の損害だったのではないだろうか。それでも兵の内11%が戦死してしまったのだから、これは非常に大きな損害だったと言える。しかも相手はたかだか2000の真田勢だったのだからなおさらだ。なお真田勢の被害は40人程度だったと伝えられている。
ちなみに第一次上田合戦には、上杉家に人質として送られていた昌幸の次男弁丸(真田信繁、通称幸村)も参戦していたようだ。小説やテレビドラマなどの物語では、上杉景勝が義を以って信繁を信じ、人質として再び戻ってくることを条件にし、ほとんど無条件での参戦を許していることが多いだ。だが近年の歴史家たちの研究によれば、信繁が参戦する代わりに、母親である山之手殿(昌幸正室)が一時的に海津城に人質に出されていたことがわかってきたようだ。つまり上杉景勝は戦国時代随一の義将ではあったが、決してお人好しではなかったということだ。
さて、上田城の攻防後も徳川は真田に味方した丸子城の岡部長盛を攻めるなど、20日間ほど小競り合いを繰り返した。だがその最中に重臣石川数正が出奔し、羽柴秀吉側に寝返ってしまった。これにより徳川家康は、真田昌幸を相手にしている場合ではなくなってしまい、8月28日になると上田城攻めから完全撤退していった。これにより第一次上田合戦は、完全なる真田昌幸の勝利でを幕を閉じたのである。
NHK大河ドラマ『真田丸』第13話 決戦の史実

天正10年(1582年)3月11日に武田勝頼が
天門山の戦いに敗れ自刃したことにより武田家が滅亡すると、その武田の旧領を他家や国衆たちが奪い合った。これを「天正壬午(てんしょうじんご)の乱」というわけだが、ここで最も大きくぶつかり合ったのが徳川家康と北条氏政・氏直父子だった。この時真田昌幸は徳川家康に味方をし、策を巡らすことにより北条軍を撃退している。だが徳川と北条の戦いも、家康と氏政が和睦を結んだことにより唐突に終結してしまった。
だがその後が問題だった。和睦が締結した後には必ず国分けという、大名同士の境界線を設定する作業があるのだが、この国分けが、真田家にとって不都合なものとなってしまったのだ。多くの小説やNHK大河ドラマ『真田丸』では、真田が所有していた沼田領を家康が勝手に北条に譲ってしまったように描かれている。だがこれは事実ではない。恐らく物語を面白くするために原作者たちが脚色したのだろう。
事実としては、真田家にとって不都合なのは変わりないわけだが、北条が武力を以ってして沼田領が含まれる上野(こうずけ)を制圧することを家康が認めるという内容の和睦だったようだ。つまり家康が勝手に沼田領を北条に譲渡し、その上で真田に沼田を明け渡すように言ったわけではないのだ。
この和睦内容により、北条はすぐに沼田攻めを開始した。この攻撃により真田は中山城を奪われてしまったが、それでも沼田城代を務めていた矢沢頼綱(真田幸隆の弟で、昌幸の叔父)の奮闘により何とか沼田城は死守することができた。この後も北条の攻撃は続くのだが、それにより沼田城が落ちることはなかった。
天正11年になると、真田の本拠である小県郡で、国衆が蜂起するという出来事が起こってしまう。真田昌幸はその鎮圧に苦労し、家康にも援軍を求めている。そしてその流れで昌幸はどさくさに紛れて上杉景勝を刺激しようと企てる。この時の真田は徳川に従っていたため、真田が上杉領に侵攻すれば、上杉は徳川を攻めることになってしまう。
事実上杉の徳川への牽制が入るわけだが、上杉に攻め込まれないようにと昌幸は上田に城を築くことを家康に提言する。上田は、上杉領である虚空蔵山城(こくぞうさんじょう)の目と鼻の先だ。だが真田家の力だけでは簡単に城を築くことはできない。そのため昌幸は、上田に城を築くことが上杉を抑えるためにも、徳川にとっての得策であると家康を説得し、上田城を家康に作らせることに成功した。
だが同じ頃、城の請取を求めに沼田城に入った北条の使者を矢沢頼綱が斬り捨ててしまうという事件が起こった。実はこれは昌幸の策略だった。矢沢頼綱に北条の使者を斬らせ、それを手土産に叔父矢沢頼綱を単独で上杉に寝返らせた。この時代で使者を切り捨てるということは、相手に対し宣戦布告をしたことになる。つまり昌幸は沼田城を守るために上杉の義を利用しようとしたのだ。上杉は助けを求める者は必ず助ける。それを昌幸が逆手に取ったのだった。
これにより困ったのは家康だ。北条に対しては切り取り次第北条領にして良いと密約を結んだ沼田領の援軍として、上杉がやってくることになったのだ。これでは北条も簡単に沼田城を攻めることはできなくなるし、上杉が動けば北条は本領を手薄にはできなくなる。当然家康自身も徳川に従う形となっている真田をここで攻めるわけにはいかない。形式上上杉に寝返ったのは矢沢頼綱だけなのだから。
この状況に困った家康は小県群の国衆である室賀正武を上手く言いくるめ、昌幸の暗殺を企てる。だがこの暗殺を事前に察知していた昌幸は室賀を返り討ちにしたことで、逆に室賀の所領を奪い取り勢力を増すことに成功した。家康としては暗殺の失敗によりますます状況が悪化してしまったというわけだ。
上田城は、沼田城の件の侘びのつもりで家康が築城を許したと伝えられている。つまり家康側からすれば「徳川で上田城を作り進呈するから、沼田は北条に譲ってくれ」という思惑だ。だが真田昌幸は上田城をありがたく頂戴したあげく、沼田城の引き渡しは拒否し続けたのだった。
この一連の騒動により、真田と徳川の関係は日に日に悪化していく。そもそも昌幸は、天正壬午の乱で真田が徳川に味方した直後に、家康が沼田領攻めを北条に対し容認したことで、家康への不信感を募らせ徳川から離れる時期を早々から図っていた。そしてその時期は天正13年6月にやってくる。昌幸は徳川と絶縁し、次男である弁丸(のちの真田信繁)を人質として送ることにより、上杉に従属していった。
ここで真田と徳川は正式に敵対関係となり、徳川が真田昌幸の居城となっていた上田城に侵攻し、
第一次上田合戦が始まっていくのである。それにしても自分で作って真田昌幸に与えた城を自分で攻めることになるとは、家康からすれば実に皮肉な出来事となってしまった。
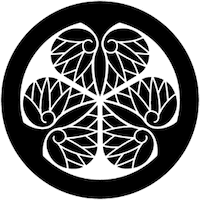
諱(いみな)という言葉をご存知だろうか。これは身分の高い者の実名のことで、存命中は実名では呼ばないことが戦国時代以前の礼儀だった。戦国時代後期になるとこの風習もやや廃れ始めてはいたようだが、しかし実際にはまだ高位な者を諱で呼ぶことは憚られていた。
例えば内大臣になっていた徳川家康のことを「家康殿」「家康様」と呼ぶのは失礼に当たり、この頃人々は家康のことを「内府殿」「内府様」と呼んでいた。内府(だいふ)とは内大臣の唐名(中国での呼び方)のことだ。現代では例えば最高経営責任者のことを英語でCEOと呼ぶが、戦国時代では役職を唐名で呼ぶのが一般的だった。
そんな時代背景がある中での慶長19年(1614年)の夏、慶長4年(1599年)から豊臣秀頼が復興作業を続けていた方広寺が完成しようとしていた。復興作業中は流し込んだ銅が漏れたことにより火災が起こってしまったりもしたが、しかしようやく完成というところまでこぎつけた。そして総仕上げとして梵鐘(ぼんしょう)が吊り下げられるわけだが、その梵鐘に刻まれた銘文を目にし、家康が文句を言い出したのである。
梵鐘銘文の一部には「国家安康」「君臣豊楽」と書かれていた。先述の諱の風習からすると、当初家康は将軍職は秀忠に譲っていたとは言え、大御所として幕府の実権を握った実際には武家最高位という立場だった。その大御所のことを諱で呼び、しかもその文字を逆さまにしたことは呪い以外のなにものでもない、との言いがかりだった。
だが銘文を作った文英清韓という臨済宗の僧侶は、単に敬意を込めて家康の名を織り込んだと話している。だが家康は清韓の人物調査を命じているほど、粗探しに躍起になっている。と言うのはこの時、家康はとにかく豊臣の力を少しでも削ぎたかったのだ。必ずしも豊臣を滅ぼすつもりはなかったようだが、極力豊臣の影響力は小さくしておきたいという思いは強かったらしい。
そのような思惑もあり、家康はこの銘文を好機と捉えた。「家康の諱を逆さにし呪詛するばかりか、「君臣豊楽」と豊臣を君主として世を楽しむとまで書いてある」。そう言った家康の言葉は傍目にはまさに言いがかりでしかなかった。
家康はこの出来事を豊臣の幕府への逆心だと宣言し、豊臣秀頼に対し以下のいずれかを選ぶように迫った。
- 大阪城を退去し、伊勢もしくは大和への転封
- 淀殿を人質として江戸に送る
- 秀頼が駿府、もしくは江戸に参勤する
どの要求も決して豊臣を滅ぼすような内容ではなく、むしろ豊臣を臣下に組み込もうとしたと言える。しかし秀頼と淀殿はこの要求をすべて突っぱねてしまった。もしこの要求のどれか一つでも受諾していれば、大名家豊臣が滅亡することもなかった。しかし一度は天下を治めた豊臣が家康の臣下になることなど、到底プライドが許さなかったのである。
この時徳川方と豊臣方の取次役は片桐且元が勤めていたのだが、豊臣方は且元が徳川方に付いていると考え暗殺を企てた。それを察知した且元はすぐに大阪城を逃げ出して助かったわけだが、しかし戦国時代に於いて取次役を殺害するという行為は宣戦布告と見なされていた。
つまり豊臣方は要求を突っぱねるどころか、宣戦布告までしてきたと家康は捉えたのである。これによって引き起こされたのが真田丸でも有名な大坂冬の陣だった。つまり大坂冬の陣とは、悪意なきたった一つの梵鐘に家康が言いがかりをつけたことから始まっていった戦なのである。
家康が梵鐘に正式に言いがかりをつけたのは慶長19年7月26日のことで、
大坂冬の陣が始まったのはその僅か4ヵ月後の11月19日だった。

大坂夏の陣を戦った際、真田幸村の腰には村正という名刀が長短2本差されていた。現代では妖刀村正として知られる、あの村正だ。そもそも村正というのは伊勢国桑名の刀工の名であり、彼が鍛えた刀に「村正」の名が授けられていた。
刀工村正の詳細は詳しくは残されてはいないが、室町時代の終盤に活躍した刀工だったようだ。つまり1500年代前半〜中盤にかけて数多の名刀を生み出し、その後江戸時代初期まで三代に渡り名刀村正を作刀し続けたという。
なぜ村正が妖刀と呼ばれるのか。実は妖刀伝説には明確な根拠が残されているわけではない。ただ徳川家との巡り合わせが悪かったというだけの話である可能性が高く、そこに尾ひれが加えられ伝承されてきたようだ。
天文4年(1535年)12月5日、徳川家康の祖父である松平清康が尾張守山城の織田信光(信長の叔父)を攻めた際、突然家臣の阿部正豊の裏切りに遭い斬られてしまった。この時正豊が使っていた刀が村正だったと言い、守山崩れと呼ばれるこの裏切りで清康は25歳でこの世を去ってしまった。
そして家康自身村正によって傷を負ったことがあり、家康の父である松平広忠も岩松八弥が振った村正によって殺害されている。さらには嫡男信康が武田への内通を疑われ切腹した時介錯された刀も村正だった。ちなみにこの事件は信長が切腹を命じたことが通説になっているが、近年の研究では父家康との確執が原因だった可能性が高くなっている。
このように徳川家と村正の巡り合わせは非常に悪かった。そのため徳川幕府では村正の所持を禁止する触れを出すほど、徳川家は村正を嫌気していた。だが寛永11年(1634年)2月2日、豊後府内藩主の竹中重義(竹中半兵衛の従弟の子孫)が24本もの村正を密かに収集していることが見つかった。これにより徳川幕府は重義に対し切腹を命じている。これほどまでに徳川家は村正を嫌気していたのだ。
つまり村正とは徳川家にとっては天敵そのものであり、だからこそ幸村も大坂夏の陣では千子村正(せんじむらまさ)を脇に差し戦いに挑んだのだった。まさに妥当徳川への執念が感じられる。ちなみにこの話は水戸黄門こと徳川光圀によって語られたわけだが、「武士ならば幸村のような心がけをしていたい」と合わせて語っていたようだ。
幸村は、大坂夏の陣では家康本陣まであと一歩のところまで迫った。この時危機を感じた家康は真田に討たれるくらいなら切腹する腹積もりもあったらしい。だが真田勢3000で徳川の大軍を最後まで切り崩すことなどやはり不可能だった。最後は力尽き幸村勢は壊滅してしまうわけだが、その直前に家康の目前まで迫った際、幸村は最後の力を振り絞り力いっぱい家康目掛けて村正を投げつけた。幸村は無意識にそんな行動に出てしまうほど、打倒徳川に燃えていたのである。
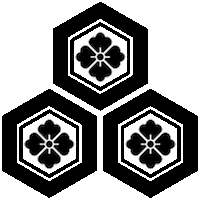
朝倉からの助勢は朝倉景健の8000だった。これは織田への援軍である徳川5000と比較をすると3000も多い。ここだけを見ると、朝倉義景は本気で浅井を救いに行ったようにも見える。しかし事実は違う。朝倉義景は浅井を救うこと以上に、8000の軍勢をできるだけ消耗させずに連れ帰るようにと景健に命じている。
さらに徳川勢は当主である徳川家康が直参しているにも関わらず、朝倉義景は他で戦をしていたわけでもないのに義景自身が出陣してくることはなかった。つまり体裁を保つために8000という軍勢を送ってはいるが、義景自身はまったく浅井を本気で救う気はなかったようだ。織田の朝倉攻めでは浅井に助けられていたにも関わらずだ。もし義景が本気で浅井を救おうとしていれば、間違いなく義景自身が出陣していたはずだ。
元亀元年(1570年)6月28日午前4時頃、姉川の戦いは開戦された。まず戦ったのは徳川勢と朝倉勢だった。数の上では8000の朝倉勢が5000の徳川勢を圧倒しているわけだが、戦いはほとんど互角で膠着状態が続いた。一方織田とぶつかり合う浅井は必死だ。3万5000の織田軍に対し、自軍は僅かに5000の兵のみで打って出ている。だが5000の兵すべてを織田本陣に向けて突撃させた浅井勢の突破力は凄まじい。11段構えを敷いていた織田軍を次々と打ち破っていく。
このままでは信長は討たれてしまうのではないか、そう感じた家康は機転を利かせ、榊原康政に浅井長政勢の横を突かせた。突如として横を攻められ浅井勢は大混乱に陥る。信長の首にたどり着くまでもう少しのところで総崩れとなってしまった。
徳川家康は信長に対して大きな恩を売ることができ、逆に朝倉勢は何の役にも立たないまま足早に越前へと引き返していった。そして小谷城へと撤退する浅井勢を織田勢も追撃したが、長政を討ち取るには至らず、その足で横山城への再攻撃に転戦して行った。
こうして姉川の戦いはあっという間に終わったわけだが、浅井・朝倉の被害は甚大だった。まず長政は最も信頼していた重心である遠藤直経と弟の浅井政之ら、名だたる武将たちが討ち死にを果たした。そして朝倉勢も猛将真柄直隆らが討ち死にを果たす。真柄直隆と言えば長さ221.5センチ、重さ4.5キロという非常に長く重い真柄太刀で戦ったことでも有名な猛将だ。朝倉軍で多くの武功を立てた武将だったが、彼もこの戦いで討たれてしまった。
ちなみに「姉川の戦い」というのは徳川方の呼び名だ。それぞれの家記ではそれぞれが布陣した場所で呼ばれており、織田・浅井方では「野村合戦」、朝倉方では「三田村合戦」と呼ばれている。やはり後々歴史に残るのは滅んだ家の話ではなく、栄えた家の話であるようだ。
さて、姉川の戦いから2ヵ月経った9月、浅井・朝倉連合軍は態勢を整え、合わせて3万の軍勢で信長不在の京に攻め込んだ。織田・徳川、浅井・朝倉にとって姉川の戦いとは、これから始まる壮絶な戦いのまだ序章に過ぎなかったのである。



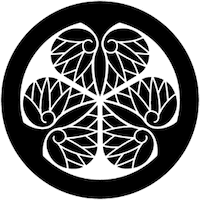 諱(いみな)という言葉をご存知だろうか。これは身分の高い者の実名のことで、存命中は実名では呼ばないことが戦国時代以前の礼儀だった。戦国時代後期になるとこの風習もやや廃れ始めてはいたようだが、しかし実際にはまだ高位な者を諱で呼ぶことは憚られていた。
諱(いみな)という言葉をご存知だろうか。これは身分の高い者の実名のことで、存命中は実名では呼ばないことが戦国時代以前の礼儀だった。戦国時代後期になるとこの風習もやや廃れ始めてはいたようだが、しかし実際にはまだ高位な者を諱で呼ぶことは憚られていた。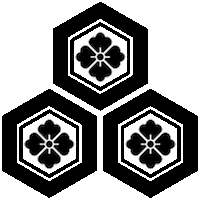 朝倉からの助勢は朝倉景健の8000だった。これは織田への援軍である徳川5000と比較をすると3000も多い。ここだけを見ると、朝倉義景は本気で浅井を救いに行ったようにも見える。しかし事実は違う。朝倉義景は浅井を救うこと以上に、8000の軍勢をできるだけ消耗させずに連れ帰るようにと景健に命じている。
朝倉からの助勢は朝倉景健の8000だった。これは織田への援軍である徳川5000と比較をすると3000も多い。ここだけを見ると、朝倉義景は本気で浅井を救いに行ったようにも見える。しかし事実は違う。朝倉義景は浅井を救うこと以上に、8000の軍勢をできるだけ消耗させずに連れ帰るようにと景健に命じている。